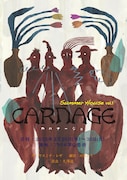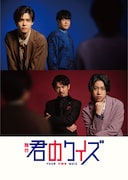ピーター・パンは、なぜ永遠に少年の姿になったのか。その謎に迫る音楽劇「ピーター&ザ・スターキャッチャー」が今冬、新国立劇場に登場する。同作は、2012年にブロードウェイで開幕し、同年のトニー賞で9部門にノミネート、5冠を獲得した。
今回、新国立劇場では本作を“こどももおとなも楽しめる”企画の第3弾として上演。演出をはえぎわのノゾエ征爾が担当する。音楽監督を担うのは、近年のノゾエ作品に欠かせないミュージシャン・田中馨だ。初日を約半月後に控え、まさに今、稽古場で戯曲と格闘している2人に、作品とそれを豊かにする音楽について話を聞いた。
また、特集の後半では出演者の宮崎吐夢が、稽古場の様子をたっぷりと語る。
取材・文 / [対談]川添史子 [宮崎吐夢インタビュー]大滝知里
撮影 / Junko Yokoyama(Lorimer)
“雑然さ”は芝居の体温を上げるエネルギー
──「ピーター&ザ・スターキャッチャー」は、日本でも「ピーターと星の守護団」として知られる児童向けファンタジー小説をもとに、米国の劇作家リック・エリスが戯曲化した作品です。孤児の少年(のちのピーター・パン)と仲間たちが繰り広げる冒険物語は、「ピーター・パン」の前日譚となっていて……という趣向ですね。最初に戯曲を読んだ印象を伺えますでしょうか?
ノゾエ征爾 さらっと読んだだけではつかみきれない戯曲だと思いました。話が進むにつれて集約する筋はあるけれど、それだけではなく、雑然としているというか、いろいろな要素が絡まっているような印象があって。でも、不思議とその“雑然さ”が心地良いんですよ。当初は「少し削ぎ落としたほうが良いのかな?」とも考え、その場面で見せたい登場人物だけで構成してみたりといろいろ試してみたのですが、整理してしまうと途端にさびしくなってしまう。ちりばめられた無数のパーツが、芝居自体の体温を上げていく効果を生む戯曲だと、稽古しながら気付かされました。
──舞台はビクトリア朝時代の大英帝国。孤児院の卑劣な院長によって“ネバーランド号”へ売られてしまった少年たちは少女モリーと出会い、宝を狙う海賊たちに立ち向かう……確かに、出てくる登場人物も要素も盛りだくさんです。キャスティングノートに「この劇の真骨頂は『全員』でやること」とありますが、船の上、浜辺、不思議な島と、どんどん切り替わっていく場面を、船乗り、孤児、海賊、人魚など複数の役を兼ねる俳優たちの身体で表現していくような戯曲です。
ノゾエ 今作は“プア・シアター”(編集注:書籍「実験演劇論―持たざる演劇めざして」などで知られるポーランドの演出家イェジュイ・グロトフスキが提唱した演劇スタイルで、可能な限り簡素な空間で、俳優の肉体・身体性を中心に据えたパフォーマンスのこと)と呼ばれるスタイルを意識して作られた作品だそうです。俳優の身体性で物語を演じていくフィジカルシアターに近いものだと思うのですが、なるほどそれは1つの有効な手段だろうと納得しました。子供向けの演劇はつい、わかりやすさを求めて、子供っぽい表現に陥りがちじゃないですか。そうならないようにこの芝居では、物語を、想像力を刺激するような演劇表現と結び付けることで、ジャンルの垣根を取っ払った。「ピーター・パン」の起伏ある物語の親しみやすさ、子供たちの想像力のたくましさを上演手法自体に取り入れている、素晴らしい発見ですよね。俳優さんたちは動きも多く、やることがたくさんあって本当に大変なんですよ。たぶん僕が出演していたら、段取りを、消えないペンで手に書き込んでいたと思います(笑)。ベテランの俳優さんの身体を酷使させる場面も多くて申し訳ない気持ちでいっぱい。いつも稽古前に更衣室で稽古着に着替えるんですが、昨日、宮崎吐夢さんが「ノゾエさん、今日から着替えるんですね」っておっしゃったんですね。でも僕、稽古初日からずっと着替えているんですよ。そこでハタと、俳優さんが毎日いかに大変なのかを思い知りました(笑)。みんな、他人の服まで見ている余裕なんてないんです。
一枚岩でスポンジ?この作品に挑むには“劇団”であれ
──田中馨さんは今回、音楽監督を担当されます。戯曲、そしてオリジナルの音楽の印象について伺えますか。
田中馨 僕もノゾエさんがおっしゃるように、稽古をしながら、この作品のぶ厚さに気付いていきました。戯曲同様、音楽にもいろいろなものが詰まっていて、演奏法にもあらゆる技術が駆使されている。舞台上で起こる多様な要素と一緒に練り上げて、練り上げて、この形に決めたのだろうな、ということが伝わる戯曲であり、音楽なんです。「音楽からはこうアプローチしよう」といった一方通行ではなく、俳優さんたちと渾然一体となることが求められている作品のような気がしますね。「自分の役割はこれです」と線を引かず、チーム全体が一枚岩にならないと成立しない気がしています。
ノゾエ そうなんですよね。僕も稽古初期に「劇団みたいにならないとダメだ」と感じました。いろいろな出自の方が集まった座組なので、もちろんそれぞれの魅力を持ち寄ってほしいけれど、「そこに対して強固にならないでほしい」と伝えました。それぞれが強い個体で存在しつつ、お互いを吸収しながら柔軟に応えていく、スポンジであるかのようなスタンスというか。
──舞台だけではなく、声優・歌手としても活躍する入野自由さん、数多くのミュージカルに出演している豊原江理佳さん、大人計画の宮崎さん、文学座の櫻井章喜さん、ほかにも、お笑いや小劇場、蜷川幸雄さんのもとで経験を積まれた俳優さんなど、幅広いジャンルの演じ手たちが集結したユニークな座組が、1つになって取り組むわけですね。音楽に関しては、お二人の間でどんなお話をされたのでしょう?
ノゾエ 翻訳の仕方について本国のスタッフとやり取りしていたときに、「例えばこういうのはどう?」と提案してくれるアイデアが、想像以上の許容範囲なんですよ。それは、言いたいことがきちんと伝わって、面白くありたいというクリエイターの思いがベースにあるからなんです。じゃあ音楽にもそのスタンスを取り入れようと思って、ある朝いきなり馨くんに、「身近にある和楽器も使ってみてください」ってお願いしました(笑)。
──おお、突然の意外なリクエスト。
田中 普通、身近に和楽器ないですからね(笑)。でも、たまたま持っていたものをいくつか持ち込んでみました。
──あ、お持ちだったんですね(笑)。
ノゾエ 本当にいろんな楽器を持ってる。
田中 この曲を作ったウェイン・バーカーが何をしたかったのかということは僕なりに読み解きたいとは思っていますし、自分の個性を出すためではなく、僕がやるならピアノじゃなくてベースだろうとか、舞台上の音楽が最大限に豊かにできる手法は見つけたいと思っています。人が作った曲の解釈に取り組むのは初めての経験で、今すごく楽しい。演奏自体もやりがいがあるし、純粋に音を出すことに集中できている気がします。
次のページ »
相手の感性に揺さぶられ、カチ割られている