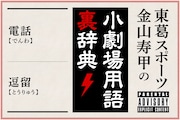ステージナタリー Power Push - 上田誠×角田貴志が語る「モンスターストライク THE MOVIE はじまりの場所へ」
ゲームを愛するヨーロッパ企画の2人が紐解く“引っ張って離す”モンストの魅力
ゲームをプレイしている側の様子を観たい
角田 あとモンストをやってる人だったら、自分の持ってるモンスターが映画に出てくるのはうれしいですよね。
上田 そういうのきっとありますよね。
角田 最初のほうに出てくる坂本龍馬(ゲームに出てくるキャラクター)とか、持ってるやつが活躍したらうれしいし。
上田 ビックリマンの話にまた戻しますと(笑)、シールではどんなキャラクターかも、縮尺もわからないんですよ。アニメを観たとき初めて「こんなに大きかったんや」とか「こんなしゃべりかたやったんや」とかがわかる。立体になってること自体うれしかったりするのが、この映画にもあるんでしょうね。
──現実味が増すというか。
上田 そうそう。でも例えば「スーパーマリオ(ブラザーズ)」の実写版は、髭のおっさんたちがいろいろなアクションを繰り広げるけど、それはそんなにワクワクはしなかった(笑)。というのも、マリオのほうの悲喜こもごもというよりは、ゲームをプレイしている側の様子を観たかったりするんですよ。
角田 確かにマリオの感情とか別にいいですね(笑)。マリオが跳んでるときは自分がマリオを操作して跳んでる感じなんで、別にマリオに感情移入してるわけではないというか。
上田 そうなんですよね。ゲームの思い出って“ゲームの中の思い出”なのか、“ゲームをやってる自分込みの思い出”なのか、これすごい重要です。前に「ノーコン・キッド(~僕らのゲーム史~)」っていうゲームをテーマにしたドラマの、ドラクエ(ドラゴンクエスト)IIの回の脚本を書かせてもらったことがあったんですけど、ドラクエの中の世界を映像化するのもなと思って。そうじゃなくて、例えばそれが流行っていた受験の時期の「受験勉強とかせなあかんのにドラクエやってもうてた」みたいな感じ。つまりそこにはゲームの中の世界観とゲームをやっている自分の体験と、レイヤーが2枚あって、それをどう作品に取り込むかは、めちゃくちゃ大事かもしれない。
角田 そうだね。確かに。
上田 この映画では、ゲームをプレイしているユーザーの体験が大事にされているのを感じました。
“引っ張って離す”ことが一番の体験
上田 でもこれってゲーム独特の話かもしれないですね。例えば小説を映像化するときに、小説を読んでる人は主人公にはならないじゃないですか。
角田 ゲームの持つ身体性みたいなのが関係してるのかな。モンストだと“引っ張って離す”ことがユーザーには一番の体験なんで。例えばこの映画で言うと、飛ばされるモンスター側の映像化をメインにされても、ユーザーとしての自分は飛んで行ってないから感情移入できない。こうやってる(引っ張って離すリアクション)ほうなんで、やっぱり飛ばしてる、こっち側も描いてくれないと。
上田 一方で、うまいこと途中からゲームの中へ導いてほしい気持ちもあるんですよ。それこそ昔「プラモ天才エスパー太郎」っていうプラモデルをテーマにしたマンガがありまして。“プラモイン”という概念によって、プラモ好きな少年が、プラモを作って、それに乗って戦うというシステムだったんですって。これをいきなりプラモに乗った世界観でやってもガンダム的じゃないですか? でも「模型屋でプラモ買ってきたぜ!」から始まって、プラモに乗って戦うまでの導入感。これが大事なんじゃないですかね。この映画もオープニングの戦闘シーンを観て「なるほどこういう感じか……」って思っていたときに、“っていうゲームをプレイしてる人たち”という視点に切り替わったので、いいぞ!と思いました。
ゲームの原初的な喜びがちゃんと再現されてる
──ヨーロッパ企画の作品の中には、「火星の倉庫」や「ボス・イン・ザ・スカイ」「ビルのゲーツ」などゲームの世界観が投影されている作品が多くあります。そういった作品は、最初にルールのようなものをみんなで共有して、ゲーム的に作っていくのでしょうか?
上田 わりとそうですね。僕ら舞台を作るときに先に舞台装置から考えていくんですよ。最初にみんなに模型を見せて、「この中でやれることをやりましょう」っていう。
角田 「建てましにつぐ建てましポルカ」は中世のお城の一部を切り取って舞台セットにしたんですけど、「この窓からこの屋根に下りて、こっちの窓に行けるかな」とかゲームのステージみたいな作り方でしたよね。立体にしてみたら「意外と見えないな」「会話できないな」とか。
上田 “迷路コメディ”だったので、舞台上をびっしり迷路で埋めようとしたんですけど……地獄でしたね(笑)。とにかく動きが不自由で。舞台上の力学が関係してるのかな。角田ともこの間話してたんですけど、宮本茂さんの、あれどんな話だっけ? 吸血鬼の……。
角田 あるゲームのワークショップで、主人公の吸血鬼が人の血を吸うゲームを考えた人がいたんですけど、周りが設定についていろいろ言う中、ゲームプロデューサーの宮本茂さんだけは「これ血を吸うときの感覚が大事だね。それをコントローラーにどう反映するかだ」「ボタンを押したときなのか、吸うときなのか、押して溜めて離すときなのか」みたいな動作に関することをおっしゃってたそうで。それが物語の設定と同じくらい大事だって。
上田 キャラクターは“吸う”のに、ユーザーは“押す”っていう動作の不一致は致命的じゃないか、っていう指摘だったと思うんですよ。僕らのお芝居で言うと「ビルのゲーツ」は舞台上にドーンとゲートがあって、それを登場人物たちがカードをかざして開けて、どんどん上っていくっていう話なんですけど、それもたぶん舞台上の力学。「開けたいゲートがあって、開けて、ガンガン進んでいく」っていうのが直感的に納得できて、お客さんがそれを観てて気持ちよくなければ、作品として成立しないんですよ。ゲームで言うと操作感覚、つまりインターフェースがうまくいってるということだと思うのですが。この映画では、最後に立ちはだかるものに対して、こうやって放つ(モンストをやる動作)ことが、最後に用意されているので、観てて爽快だった。モンスターに玉を当てるっていう原初的な喜びがちゃんと再現されてる誠実な映画だなと。ただモンストをやったことがないんで、想像で話してるんですけど(笑)。
次のページ » ただのゲームの映画化じゃない
- CONTENTS INDEX
- 特集トップ・作品紹介
- ジャングルポケット 斉藤慎二
- ヨーロッパ企画 上田誠&角田貴志
- スタジオジブリ 鈴木敏夫
- 超特急 リョウガ&ユーキ
- 大久保篤
小学4年生の焔レンは、3人のチームメイトとともにゲーム「モンスト」の開発に協力していた。ある日レンたちは研究所の地下で、現実世界にいるはずのないドラゴンを目撃する。弱っているドラゴンをもとの世界に戻すため、“ゲート”を目指し旅に出ることになった4人。その目的地は、かつてレンの父が失踪した場所でもあった。身勝手なレンはチームの輪を乱し仲間と衝突するが、徐々に自分が1人で生きているわけではないことに気付いていく。
スタッフ
監督:江崎慎平
脚本:岸本卓
ストーリー構成:イシイジロウ、加藤陽一
キャラクターデザイン原案:岩元辰郎
モンスターデザイン原案:近藤雅之
キャラクターデザイン・総作画監督:金子志津枝
美術監督:加藤浩、坂上裕文
色彩設計:大西峰代
チーフCGIディレクター:福島涼太
CG演出:川原智弘
音響監督:明田川仁
音楽:MONACA
撮影監督:野村竜矢
編集:長谷川舞
制作:ライデンフィルム、ウルトラスーパーピクチャーズ、XFLAG PICTURES
製作:XFLAG
配給:ワーナー・ブラザース映画
キャスト
焔レン:坂本真綾(小学生時代)/ 小林裕介(中学生時代)
水澤葵:Lynn
神倶土春馬:村中知
若葉皆実:木村珠莉
影月明:河西健吾
石橋健太郎:北大路欣也
オルタナティブドラゴン:福島潤
アーサー:水樹奈々
ゲノム:山寺宏一
エポカ:水瀬いのり
主題歌
ナオト・インティライミ「夢のありか」
©mixi,Inc. All rights reserved.
上田誠(ウエダマコト)

1979年11月4日生まれ、京都府出身。ヨーロッパ企画の代表であり、すべての本公演の脚本・演出を担当。外部の舞台や、映画・ドラマの脚本、テレビやラジオの企画構成も手がける。2003年以降、OMS戯曲賞にて「冬のユリゲラー」「囲むフォーメーション」「平凡なウェーイ」「Windows5000」がそれぞれ最終候補に。2010年、構成と脚本で参加したテレビアニメ「四畳半神話大系」が、第14回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門で大賞受賞した。
角田貴志(スミタタカシ)

1978年3月2日生まれ、大阪府出身。2004年、第16回公演よりヨーロッパ企画に参加。以降、ほとんどの本公演に出演。ラジオ番組の構成も務める。また、イラストやアートワークを得意とし、書籍の表紙絵や、DVDのジャケットイラストなども手がける。「タクシードライバー祗園太郎」「銀河銭湯パンタくん」では、脚本やキャラクターデザインも担当。「煙どろん」というペンネームで、マンガも発表している。
2016年12月15日更新