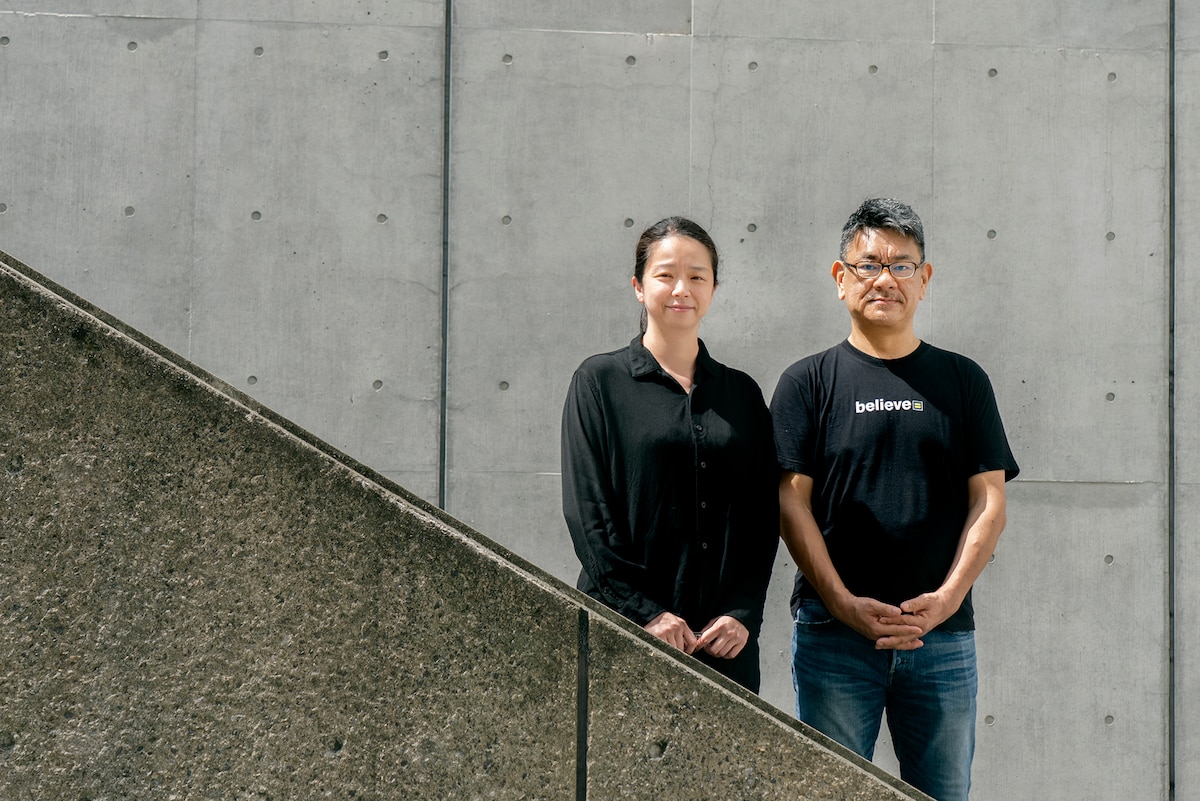今年開場25周年を迎えた新国立劇場が、そのアニバーサリーイヤーを飾る1作品として、演劇芸術監督・小川絵梨子演出による「レオポルトシュタット」を上演する。本作は、イギリスを代表する名匠トム・ストッパードの最新作で、2020年にロンドンで初演され、オリヴィエ賞作品賞を受賞した。ステージナタリーでは、小川に本作の上演を勧め、本作に翻訳で携わる戯曲翻訳者の広田敦郎と、小川の対談を実施。ストッパード作品の尽きせぬ魅力を聞いた。
取材・文 / 熊井玲撮影 / 川野結李歌
自伝的要素も織り込まれた、壮大なフィクション
──小川さんは今年3月に行われた新国立劇場「2022 / 2023シーズン」ラインナップ発表会(参照:開場25周年の新国立劇場「2022 / 2023シーズン」、演劇の新シリーズは“未来につなぐもの”)で「レオポルトシュタット」について「トム・ストッパードの最新作です。ストッパードはユダヤの方なのですが、彼自身の出自をたどっていくような作品になります。ただ、迫害や悲劇の中でも命をつないでいった一家の歴史をひも解く家族の話になっていますので、今の人たちにも通じるものがあるのでは」とおっしゃいました。劇中では20世紀初頭のウィーンを舞台に、ユダヤ人居住区・レオポルトシュタットを抜け出して瀟洒な地区に暮らすメルツ一家の1899年、1900年、1924年、1938年、1955年と約55年にわたる4世代の物語が描かれます。稽古が始まって、戯曲に対する思いが変化した部分はありますか?
小川絵梨子 家族の物語だという印象は変わりませんが、劇中で最も現代に近い1955年に、物語がある意味ちゃんと収斂していくというか、そこでつながってくる作品だなと思いました。過去を回顧するような台本ではなく、現在と過去の関係性が描かれているし、それが個人でも社会のレベルでも起きている。なので、演出するときは1955年に向けてそれまでのシーンをどう立ち上げていくかということを考えていかないといけないなと。もちろん台本が素晴らしいので自然とそうなるのですが、時代ごとに断絶したシーンにならないように意識しないといけないと思っています。
──本作を小川さんに紹介されたのは広田さんだそうですね。
広田敦郎 そうです。2020年にロンドンで初演されるときに「トム・ストッパードの最後の作品になるかもしれない」とニュースで知ったのですが、ロンドンでの初演は結局、新型コロナウイルスの影響で開幕直後に中止になってしまいました。その後「日本で『レオポルトシュタット』は上演しないんですか?」とある方からメッセージをいただいたことをきっかけに、具体的に動いてみようと思ったんです。
僕は2009年にシアターコクーンで上演された「コースト・オブ・ユートピア」という作品を翻訳しています(編集注:19世紀ロシアの革命思想家ゲルツェンの生涯を軸に、同時代の革命家、作家、文藝批評家との友情、論争を描いたストッパード作品で、上演時間9時間に及ぶ3部作。日本では蜷川幸雄の演出で上演された)。そのときちょうどストッパードさんが世界文化賞の授賞式で来日され、千秋楽をご覧になったんですが、別れ際に「また何か訳してね」と言ってくださったんです。だから「いつかまた何か訳さなきゃ」と思ってはいたのですが、“知の巨人”とも言われる彼の作品に対する畏怖のようなものもあり、なかなか腰を上げられずにいて。でも今回、「上演しないんですか?」と促していただいたことで、「今やらなきゃ一生やらないかも」と思い、絵梨子さんに連絡しました。
小川 ありがとうございます!
広田 ストッパード戯曲って情報量が多くて教養が詰め込まれていて、大演出家がいかにもな手つきで演出するイメージを持たれることもあります。でも彼自身は、演劇は何よりも娯楽だと考えていて、複雑だけど面白い人間を描いた面白い芝居を作ろうとしているんですよね。そういった繊細でリズム感の良い演出家に上演してもらいたいなと思ったときに、絵梨子さんの顔が思い浮かんだんです。
小川 広田さんに連絡をもらったとき、面白そうだなと思いつつ「私にできるのかな」とも思いました。ちょうど中劇場でやる作品を探していて、これは確かにふさわしい作品だと思いました。けれど、最終的にはやっぱり演出してみたいと思ったのが決め手です。
──本作では、ほかのユダヤ人とは異なる生き方をしようとしていたヘルマン・メルツらが、歴史の流れの中でユダヤ人として迫害を受けつつ、人生を営む様が描かれます。本作にはストッパードの自伝的要素が織り込まれているそうですね。
広田 ただ、“チェコ生まれのユダヤ人で、ナチスによる迫害を逃れてアジアに脱出し、最終的にイギリス人になった”という自身の人生が劇中にそのまま描かれるわけではありません。本作の登場人物では、第4世代のレオが、少しだけ作者の実人生に近い描かれ方をしていますが、基本的には彼自身の人生や思想のさまざまな要素が戯曲のいたるところに使われていると思います。
小川 そうですよね。ヘルマンにもトムさん的要素が入っているような気がしています。
広田 うん。それから、ヘルマンとユダヤ人国家について議論する数学者ルードヴィクも、いかにもストッパード的な人物だと思います。あとフラッパーの格好をしてチャールストンを踊るヘルミーネという若い女性が出てきます。作者の母親が1920年代にフラッパーの格好をしている写真があるのですが、ヘルミーネはそのお母さんをもとにイメージしたんじゃないかな、と。また「ウィーン 最後のワルツ」(著:ジョージ・クレア ほか)というウィーンからイギリスに逃れたユダヤ人の回顧録があって、そこに書かれたエピソードもたくさん取り入れられています。とはいえ、それらはあくまで創作のヒントで、最終的に人の心を動かすのは、トムさんが描いたドラマの部分。本当に打ちのめされますし、同時にコメディの要素も多々あります。
すべてはより良い上演のために、劇作家・ストッパードの魅力
──小川さんは「ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ」、広田さんは「コースト・オブ・ユートピア」で以前もストッパード作品に取り組んでいます。改めてトム・ストッパード作品の魅力をどんなところに感じますか?
小川 後ろにあるものや歴史的背景などをいかに読み解くかが非常に重要です。特にトムさんの作品はその厚み、深さがすごいので、本当に作品からいろいろ学び取らないといけないと感じます。
広田 それと、単純に読み物としての言葉ではなく上演を意識した言葉だというところが大きいと思います。「レオポルトシュタット」はコロナ危機が始まったころに開幕したのですが、その後1カ月ぐらいでロックダウンになり、1年半上演できなかった。そして昨年、ロックダウン後の再演にあたり、もともと2幕で上演していたものを、休憩なしで一気に上演する形にしたんです。実際に稽古して上演した経験からたくさん学んで、それを生かしてリライトしているんだと思います。ただ言葉を書いているのではなく、“劇作家”の仕事をしているんですね。この9月に始まるニューヨークの公演に向けてリライトは続いていて、新国立劇場の公演でもできるだけそれを反映しています。
小川 広田さんがトムさんと戯曲についてメールでやり取りするときに私も入れてもらっているんですけど、先日広田さんがあるシーンについて「ここは新しいバージョンでカットされているけれど、戻したほうが豊かではないでしょうか」と提案したんです。そうしたらトムさんが「確かにそうだね。ほかにも敦郎と絵梨子が気になっているところがあれば適宜判断していってほしいよ」と返信してくれて、そのことに私はものすごく感動して。
広田 現場の実際的なことを大切にされているんでしょうね。あるメールには「終わりがないんだよね!」とも書かれていて、変化を恐れず、より良い表現を求め続ける姿勢がカッコいいなあと。
小川 そうですよね! トムさんの中では何かを守るなんて思いはなく、常に“良い作品を作るために”を考えていらっしゃるんだなと、そのことに感動します。そして作品の何が本質かということをコミュニケーションの中で感じさせてくれるのがすごくありがたいです。
次のページ »
“わからない”を超えていくドラマの力