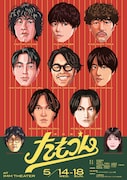毎年、1月に東京の半蔵門にある国立劇場で開催されてきた「初春歌舞伎公演」。正月らしい華やかな演目に、獅子舞や曲芸、舞台上からの手拭いまきといったイベントが魅力的な同公演だが、国立劇場が建て替えによる閉場中のため、2024年は東京の初台にある新国立劇場で初めて行われる。今回の公演のテーマは“継承”。上演演目には、尾上菊之助が梶原平三景時役、坂東彦三郎が大庭三郎景親役、中村梅枝が六郎太夫娘梢役、中村萬太郎が俣野五郎景久役で出演する「梶原平三誉石切」、中村時蔵が安倍保名を、梅枝が女房葛の葉 / 葛の葉姫を勤める「芦屋道満大内鑑 -葛の葉-」、そして出演の皆々で正月を祝う舞踊「勢獅子門出初台」が並んだ。
ステージナタリーでは、時蔵と梅枝親子の対談を実施。梅枝は大役となる「葛の葉」だけではなく、「梶原平三誉石切」でも初役に挑むが、いずれの役も時蔵が繰り返し演じてきた役だ。それぞれの役が、時蔵から梅枝にどのように“継承”されているのか、たっぷりと語ってもらった。なお取材は、当代時蔵の祖父で、梅枝の曽祖父である三代目中村時蔵の「女暫」の絵がかけられた、国立劇場の一室で行われた。
取材・文 / 川添史子撮影 / 田口真佐美
初の新国立劇場での「初春歌舞伎公演」
──令和6年の国立劇場「初春歌舞伎公演」のテーマは“継承”。今回は、連綿と続いてきた「芸の継承」について伺いつつ、公演の見どころなどを伺って参ります。本格的な歌舞伎が演じられるのは初となる新国立劇場で、先日取材会が行われました(参照:尾上菊五郎、「勢獅子門出初台」は“初春歌舞伎らしい演出”を入れ「ちょっとお遊び風にできたら」)。初台での初芝居、いよいよですね。
中村時蔵 準備のため事前に道具帳(舞台を真正面から描いた完成図)や図面は見ていましたが、絵で見るのと実物では違いますからね。取材会の日は「間口はこのくらいかな」とか、「立ち位置はこのあたりだろう」といった具体的なことを実際の空間で確認でき、改めて「お客様に喜んでいただけるよう勤めるのが、私たちの役目」という思いが、実感できる日となりました。
中村梅枝 初台は歌舞伎座や新橋演舞場のある東銀座エリアとも違いますし、国立劇場に通ってくださった歌舞伎ファンの皆様にとってあまりなじみがない土地かもしれません。でもターミナル駅である新宿や渋谷からのアクセスはとっても良い場所。ここでの公演が、これまでいらしたことがない方々、あるいは若い世代のお客様との出会いのきっかけにもなれば……という期待もしております。
坂田藤十郎から時蔵に、時蔵から梅枝に“継承”されていく「葛の葉」
──お二人がそろう「芦屋道満大内鑑-葛の葉-」は、古い説話から、説経節、古浄瑠璃、義太夫節、そして歌舞伎と、形を変えながら現代に伝わってきたファンタジー。仲睦まじく暮らす安倍保名と葛の葉の夫婦愛、実は白狐の化身であった葛の葉と家族の切ない別れを描きます。時蔵さんの保名は、2001年の御園座公演以来ですね。
時蔵 保名は風情がものをいう役です。あのときは山城屋のおじさま(四代目坂田藤十郎、当時中村鴈治郎)が葛の葉をなさっていて、とってもステキだったんですよ。その時のご縁で「歌舞伎鑑賞教室」(2013年国立劇場)で初めて葛の葉を勤める際、「ぜひ教えてください」とお願いいたしました。しかも(藤十郎夫人の)扇千景さんがお手紙も添えてくださり、小道具についてのご工夫についても丁寧に伝えてくださいました。実はそのお手紙を先日息子にも渡しましたので、「少しは継承できたかな」とホッとした部分があります。この演目は曲書きと呼ばれるケレンが眼目。筆の工夫についても、そのお手紙に詳しく書いてくださいました。
──狐だと知られた葛の葉が、子供をあやしながら裏文字や口や左手を使い、「恋しくば尋ねきてみよ和泉なる信田の森のうらみ葛の葉」と障子に別れの一首を書き残す曲書きの場面は、大きな見どころです。
時蔵 山城屋のおじさまは筆に切れ目を入れ、くわえやすいようにしていらっしゃったとか。私も小道具さんが持ってきてくれた筆は使わず、筆がちょっと上に向くように角度を変えたりと、さらに自分に合うように改良を加えています。初役の際、国立劇場がいろいろな資料を見せてくれた中に、前の方が書かれた曲書きの写真がいくつかあったんですね。やっぱり成駒屋のおじさま(六代目中村歌右衛門)はお上手でしたねえ。うちの祖父(三世中村時蔵)はあまりうまくない。これぐらいなら私も大丈夫と思いました(笑)。
梅枝 あとの人のことを考えると、下手に書いてハードルを下げておいたほうがいいかもしれませんね(笑)。とはいえ大きな見せ場ですから、私もまずは座って普通の筆で書くことから始めて、慣れてきたら大きい筆に持ち変え……と、お習字のお稽古からスタートしました。どのくらいの墨汁を筆に含ませておけば最後まで書き切れるか、立って書いたときの筆の状態はどうなるのか、義太夫さんに合わせて書いてみないとスピードもつかめません。実際の舞台で知っていくことも多いと予測しています。
時蔵 滴れた墨汁が衣裳につかないように細心の注意を払ったりと、想像以上に神経を使うんですよ。慣れても不測の事態が起こりますし。
梅枝 明治座で中村七之助さんがなさったとき(2016年明治座)に保名で出ていたので、曲書きの場面は毎日障子の後ろから見ていたんですね。あのときは「大変だなあ」と思いながらのんきに眺めていただけでしたが(笑)。
──時蔵さんは2015年、旧金毘羅大芝居(金丸座)でも葛の葉をなさいました。
時蔵 金丸座独特の人力で動かす廻り舞台を使ったり、花道のスッポンにぽんと飛び込んだり、装置をフル稼働してやりました。あのときはちょうど千穐楽が還暦の誕生日だったこともあり、思い出深いですね。新国立劇場では盆を使った三方飾りでお見せしたいと考えています。
梅枝 ケレンの芝居はお客さまに楽しんでいただくことが肝要ですから、決まったやり方がないんですよね。資料によると、曲書きの途中で力者(主役に絡み立廻りや所作ダテをする役)が出てくる……なんてやり方もあるそうですよ。花道に連れていかれた葛の葉が筆を「えいっ」と障子に投げると、最後の文字が完成するとか。
──え! それまたすごいやり方ですね。
梅枝 村芝居でも随分と手がけられた演目なので、いろいろなやり方が残っているみたいです。
時蔵 これはさすがに、私も見たことがない(笑)。葛の葉姫との2役早替わりもありますし、衣裳さん、床山さん、そして弟子たちみんなが力を合わせてやり抜くチームワークのお芝居でもあるんです。私のやり方はすべて伝えますが、最終的には自分の工夫を見つけてもらえればと思っています。
「石切梶原」の梢は四世時蔵が最後に勤めた役
──梅枝さんは、名刀をめぐる物語「梶原平三誉石切(通称石切梶原)」で、青貝師(装飾工)六郎太夫の娘、梢も演じられます。
梅枝 父は幾度となく梢を演じていますが、私は演目自体にご縁がなく、「この年までなかったら、もうやることはないのかな……」と諦めておりました。こうして機会をちょうだいし、ありがたいですね。六郎太夫との親子の情を大事に勤めたいと思っています。
時蔵 私が初めて梢をやったとき(1977年新橋演舞場)は、中村富十郎のお兄さんの梶原でした。まだ二十歳そこそこで何もできないときでしたから、二世中村又五郎のおじさまがとても丁寧に教えてくださった思い出があります。初代中村吉右衛門の元で修業された方で、祖父の梢もご存知でしたし。
梅枝 1962年1月の千穐楽に亡くなった祖父(四世中村時蔵)が、その月に勤めていたのが梢だったとか。
時蔵 そう。当時、追悼番組として日本テレビが「石切梶原」を放送した映像が残っていて、今見返すとやっぱりみなさんすごく良いんですよ。息子にはビデオも渡してあるので、しっかり勉強してくれたらと思っています。
梅枝 昭和30年代ですからね……そもそも皆さんがまとっている匂いからして違うんです。もちろん修業量の差もあるでしょうし、どうやったって歌舞伎になる。「こういう風にできたらな」とは思いますけれど、現代であの雰囲気を出すのはかなり難しいですよ。技術的なことを近づけることは可能ですが、日々スマホをいじってYouTubeを見ているような時代ですから。
時蔵 でも、近づけることはできるでしょう。
梅枝 もちろん、目指すのはあの匂いですけれど。まあ、あれを「いいな、ステキだな」と思える感覚が大事なのでしょう。ヘンな固定観念はある程度捨てて、「それでも歌舞伎になります」という技量を示せるのが歌舞伎俳優。型で押し通さなくてはいけないときもありますが、1時間30分の芝居がずっと型で進行してしまったら、面白くもなんともないじゃないですか。リアルなところがあるから型が生き、型があるからリアルな芝居も生きてくる。これが大事なのではないかと。もちろん基礎的な技量があったうえでのリアルですね。
時蔵 あの映像を観ているとね、警護の役人2人が「通さないぞ」と棒で梢を止めるところがとってもリアルで良いんですよ。昔の俳優さんには、こんな些細なところにも技が伝承されていたのでしょう。だから私がやるときはいつもここで注文を出すんです。今回も、少しでも理想に近づけるよう工夫したいと考えています。
梅枝長男・大晴も出演、時蔵は孫のリクエストに応え…
──初芝居を締めくくる舞踊「勢獅子門出初台」では、三世代が華やかに揃います。梅枝さんのご長男、小川大晴くん(8歳)も出られますね。
梅枝 私が出ずっぱりなので、お兄ちゃんたち3人(坂東彦三郎の長男・坂東亀三郎、尾上菊之助の長男・尾上丑之助、寺島しのぶの長男・尾上眞秀)に相手していただくことになりますが(笑)。
──大晴くんはすでにいろいろな舞台でご活躍されていますし、お芝居ごっこも大好きだとか。時蔵さんはお孫さんのリクエストに応えて、手作りの小道具をプレゼントされるそうですね。
時蔵 大晴が「義経千本桜 大物浦」に安徳帝で出させていただいたとき(2022年歌舞伎座)、「(知盛が海中に身を投げるときに使う)碇が欲しい」と言われましてね、硬い発泡スチロールを一生懸命カッターで削って作ったこともあります。DIYが得意なんです(笑)。
──碇!? すごいですね。ご自宅で遊んでらっしゃいましたか?
梅枝 後ろに大きなクッションを置いて倒れ込んで遊んでいましたが、やりすぎて壊れちゃいました(笑)。子供の吸収力って本当にすごくて、細かなところもよく見ているんですよね。丑之助さんが小四郎役、大晴が小三郎役を演じた「盛綱陣屋」(2022年国立劇場)が終わったあと、ご褒美で2人を連れてディズニーランドへ行ったんです。アトラクションに並ぶ間ずっと2人で「盛綱陣屋」を再現して遊ぶのを眺めていたら、義太夫の語りもしっかり覚えていました。
時蔵 梅枝と弟の萬太郎が「伽羅先代萩」の千松と鶴千代をやったとき(1996年歌舞伎座)は、腰元の動きを覚えて、よく芝居ごっこをしていましたよ。
梅枝 あのとき、政岡をなさっていた先代の京屋のおじさん(四世中村雀右衛門)に、ご褒美でポケモンのゲームを買っていただいたことはよく覚えています。
──頑張った子役には、いろいろなご褒美が(笑)。
時蔵 うちの弟(中村錦之助)なんて、亡くなった坂東三津五郎さんのおじいさま(八世三津五郎)に「ニワトリが欲しい」とリクエストしたら、本当に2羽もくださったんですよ。しばらくうちの鳥小屋で飼っていました(笑)。
──そうやって大人の皆さんに励まされながら、子役さんたちはハードな公演を乗り越え、先輩方の芸を“継承”していくのでしょうね。
時蔵 ひと月見ているうちに、全部覚えてしまいますからね。うっかりセリフや段取りをトチったら、「間違えたね」なんて言われてしまいそうで。こちらも気が抜けません(笑)。
プロフィール
中村時蔵(ナカムラトキゾウ)
1955年、東京都生まれ。萬屋。四世中村時蔵の長男。1960年に三代目中村梅枝を名乗り初舞台。1981年に五代目中村時蔵を襲名。1979年に重要無形文化財保持者(総合認定)に認定、2010年に紫綬褒章を受章。2017年から一般社団法人伝統歌舞伎保存会理事を務めている。
中村時蔵 (なかむら ときぞう) | 公益社団法人 日本俳優協会
中村梅枝(ナカムラバイシ)
1987年、東京都生まれ。萬屋。五代目中村時蔵の長男。1991年に初お目見得。1994年に四代目中村梅枝を襲名し初舞台。1995年、NHK大河ドラマ「八代将軍吉宗」に七代将軍家継で出演。2018年に重要無形文化財保持者(総合認定)に認定された。