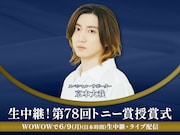2020年3月に初開催された「かながわ短編演劇アワード」は、神奈川県が主催する「かながわマグカル演劇フェスティバル」のメインイベントの1つ。本アワードは、最終審査で上演を競う「演劇コンペティション」と、「戯曲コンペティション」の2本柱で構成され、いずれも30分以内の短編作品が、ジャンルやスタイルを問わず募集される。審査員を岡田利規やスズキ拓朗などの第一線で活躍するアーティストが担当。「演劇コンペティション」でグランプリを受賞した団体には、賞金として100万円が贈呈される。
2回目となる今年の「かながわ短編演劇アワード」は、新型コロナウイルスの影響で、昨年に続き無観客配信で実施される。両部門の出演団体と候補作はすでに出そろっており(参照:「かながわ短編演劇アワード2021」無観客開催が決定、安住の地ら7団体が作品披露)、来たる3月20・21日の最終上演審査と公開審査会に向けて緊張感が高まる。
ステージナタリーでは、本アワードのプロデューサーで、「演劇コンペティション」の一次審査委員を務める楫屋一之と、昨年の「演劇コンペティション」でグランプリを受賞したモメラス主宰・松村翔子の対談を実施。楫屋はこれまで、プロデューサーとして如月小春を支えたほか、世田谷パブリックシアターのチーフプロデューサー・劇場部長として多くの舞台作品を手がけた。対する松村は、俳優としてチェルフィッチュの初期を作り上げたほか、自身の劇団・モメラスを立ち上げてからは、劇作家・演出家として注目を浴び続けている。
長年にわたり、日本の演劇シーンを見つめてきた楫屋と、演劇シーンの渦中にいる松村。第1回を振り返りつつ、コロナ禍だからこそ生まれるアワードの意義や、これからについて思いを馳せる。
取材 / 熊井玲 文 / 櫻井美穂 撮影 / 毛利竜尚

「かながわ短編演劇アワード」とは?
神奈川県が主催する、短編演劇を対象とするアワード。「戯曲コンペティション」と「演劇コンペティション」から成り、2020年にスタートした。今回が第2回となる。
30分以内での上演を想定した短編戯曲を対象とするコンペティションで、今年は「COVID-19」をテーマにした作品を公募。3月20日には一次審査を通過した最終候補作品6作品を対象に、KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオにて審査会が行われる。一次審査員を大竹竜平、オノマリコ、河野遥、杉浦一基、半澤裕彦、本橋龍、最終審査員を市原佐都子、北川陽子、西尾佳織、松井周、矢内原美邦が務める。賞金は20万円。なお3月20日12:00まで最終候補作品が公式サイトにて公開されている(参照:かながわ短編戯曲賞2021 - かながわ短編演劇アワード2021 - 神奈川県ホームページ)。
- ノミネート作品(五十音順)
-
- 田中瑞穂「コントロールが終わるとダンスが始まる」
- 寺内淳志「ライブパフォーマンス」
- 長谷川優貴「口」
- 三橋亮太「【H+】アポトーシスしてみた」
- 村田青葉「@Morioka(僕=村田青葉の場合)」
- 山田志穗「集合!」
最低5年、できれば10年の継続を目指す
──楫屋さんは2018年に神奈川県立青少年センターの参事に就任されましたが、就任当時から「かながわ短編演劇アワード」の立ち上げに関わられていたのでしょうか?
楫屋一之 僕が就任した最初の年は、「神奈川かもめ『短編演劇』フェスティバル」という短編演劇のコンペティションを開催しましたが、賞金と審査員を変えれば、もっと面白いものに変わるだろうという確信がありました。そこで、まずは、「演劇コンペティション」の賞金を30万円から100万円に上げることにしました。審査員については、いろいろな方からアドバイスをいただきました。最終的に、「演劇コンペティション」の審査員を「美術手帖」総編集長の岩渕貞哉さん、演劇作家・小説家の岡田利規さん、作曲家の笠松泰洋さん、振付家・演出家・ダンサーのスズキ拓朗さん、演劇ジャーナリストの徳永京子さん、演劇制作の林香菜さんの6名にお願いしました(参照:「かながわマグカル演劇フェスティバル」始動、短編演劇と戯曲のアワード開催)。さらに副賞として、神奈川県立青少年センター スタジオHIKARIでの上演権も加え、この3つの新要素で2020年に「かながわ短編演劇アワード」として再スタートを切ったんです。リニューアルしたことで、これまで応募してこなかった層が応募してくるようになりました。
──「かながわ短編演劇アワード」は、「演劇コンペティション」と「戯曲コンペティション」で構成されています。この2つ柱にするというのも、楫屋さんのアイデアでしょうか?
楫屋 これは「神奈川かもめ『短編演劇』フェスティバル」からの受け継ぎです。全部を変えるつもりはなかったですし、戯曲賞と公演と、両方でやるのがいいだろうと。「戯曲コンペティション」もいろいろな方に相談しながら……若干の好みも入れつつ(笑)、審査員を全部変えました。
──「かながわ短編演劇アワード」は、プロ・アマ・年齢問わず、応募条件がかなり自由ですね。「演劇コンペティション」では、“30分以内”という規定さえ守れば、ノンバーバルな作品や、フィジカルシアター的な作品でも応募可能ということで、「演劇賞だから」という縛りがあまりない印象です。
楫屋 「戯曲コンペティション」も「演劇コンペティション」も、ジャンル・スタイル含め、間口は非常に広くしています。ただやはり県が主催するイベントなので、あまりマニアックにやってもだめだし、社会に貢献するようなキーワードがあったほうが良いだろうと。なので、「戯曲コンペティション」では、昨年はSDGs(編集部注:2015年に国連サミットで採択された、持続可能な世界を実現するための開発目標)、今年はCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)をテーマに作品を募集しています。そもそも作家がその時代の感覚で書けば、おのずとそういったテーマが作品に表れてくると思うので、SDGsにしても、COVID-19にしても、縛りを強くしているという意識はありません。なので、自由度の高さは担保されているかと。こういうコンペティションは、最低5年、できれば10年は続けないと、何の意味もない。どう転ぼうと、継続していきたいですね。
応募の決め手は「岡田利規と100万円」
──松村さんは、昨年の「演劇コンペティション」グランプリ獲得後のインタビューで「審査員の顔ぶれが応募の決め手になった」と話しています。審査員には、松村さんがかつて作品を共に作られていた、チェルフィッチュの岡田さんもいらっしゃいますね。
松村翔子 前身となる「神奈川かもめ『短編演劇』フェスティバル」も、存在は知っていました。リニューアルしてから、審査員含め、ガラッと賞の雰囲気が変わった印象があります。私にとっては、岡田さんが審査員に入っていたことはとても大きかったですね。実はコンペまで、岡田さんに作品を観てもらったことがなかったんです。だから、観てもらって、認めてもらおう、という気持ちもありました。
──審査員以外で、魅力を感じた部分はありましたか。
松村 賞金ですね。
楫屋 大きいよね。
松村 コンペに向けて作品を作ること自体にもお金はかかるので。賞金がないと、そもそも生活ができない。
楫屋 ものづくりって、もちろん“気持ち”も大事だけど、それを支えるお金も必要。100万円くらいの賞金がないと、モチベーションはちょっと下がるよね。
──松村さんは、これまで岸田國士戯曲賞に2回ノミネートされており、劇作家としても高い評価を受けています。昨年の「戯曲コンペティション」では、市原佐都子さん、北川陽子さん、瀬戸山美咲さん、矢内原美邦さんが審査員を務められましたが、松村さんは「戯曲コンペティション」にも応募されましたか?
松村 してないですね。変な話、作家としての自覚が芽生えたのがつい最近なんですよ。どちらかというと、演出のほうが自信ありますし、モメラスで勝負できるのは上演だと思っていたので。
──今年の「戯曲コンペティション」審査員には市原さん、北川さん、矢内原さんのほか、昨年の審査会で司会を担当していた松井周さん、西尾佳織さんが新たに加わりました。田中瑞穂さんの「コントロールが終わるとダンスが始まる」、寺内淳志さんの「ライブパフォーマンス」、長谷川優貴さんの「口」、三橋亮太さんの「【H+】アポトーシスしてみた」、村田青葉さんの「@Morioka(僕=村田青葉の場合)」、そして山田志穗さんの「集合!」の6作品が最終候補作としてノミネートされ、3月20日に行われる公開審査会で大賞が決定します。
楫屋 「戯曲コンペティション」の応募数は、昨年とあまり変わらないと予想していたんです。コロナ禍で実際の公演数は減っているけど、作家は1人でも書けるから。結果は予想した通りでした。
チェルフィッチュの松村翔子、モメラスの松村翔子
──楫屋さんは、チェルフィッチュを通して松村さんをご存じだったそうですね。
楫屋 僕が初めて観たチェルフィッチュが、2003年の「マリファナの害について」。それは松村さんの一人芝居だったんですけど、「これはすごい演劇が始まったぞ」と引き込まれましたね。僕は、チェルフィッチュの文体を作るのに、松村さん、山崎ルキノさん、山縣太一さんの3人の身体性が重要な要因になったと思っているんですよ。岡田さんが海外に出て行ってから、3人もそれぞれの道を進み出しましたが、彼らにとって、チェルフィッチュでの経験はプラスになっているし、つながっていると思います。
──松村さんは、チェルフィッチュを離れてから、モメラスを結成するまではどのような道のりがありましたか。
松村 2012年に離れたときは、すべて出し切った、という気持ちが強くて、このまま演劇自体を辞めてしまうだろうと思っていました。離れてからは、時間ができたこともあり、100本くらいさまざまな演劇を観ましたね。そうしたら、今度は自分で書いて、演出してみたくなったんです。それで、2013年にモメラスを立ち上げました。当時はいかにチェルフィッチュから離れるか、ということに必死でした。フリーの役者としても活動していたんですけど「一番チェルフィッチュから遠いところはここだ!」と思って、アングラの、月蝕歌劇団に出演したり……。
楫屋 すごい(笑)。
松村 モメラスの旗揚げ公演って、実はアングラの俳優さんで構成されているんですよ(笑)。今はようやく、チェルフィッチュ的なものも、素直に受け入れられるようになりました。やはり、チェルフィッチュを作り上げたうちの1人、という自覚もありますし。コンペが終わったあと、岡田さんと、すごく久しぶりにお話ししました。「観てもらえて良かったです」とお伝えしたら、「観られて良かった」と言ってもらえて。
楫屋 松村さんは、岸田國士戯曲賞にノミネートされるような言葉を書いてもいるけど、作品を観る限り、身体の使い方や表し方に主眼を置いているように見えますね。
松村 そうですね。作品を作るとき、まず“舞台上で身体がどのように存在するか”ということが最初にあります。言葉はそのあとに出てくるかもしれません。
次のページ »
審査会は“けっこう怖い体験”