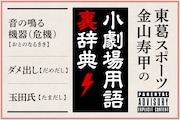スタッフがそれぞれのアプローチで挑む「花の御所始末」
ここでは「花の御所始末」に携わる演出の齋藤雅文、舞台美術の中嶋正留、衣裳の藤戸詠子、床山の市川純也らスタッフ陣に、幸四郎とどのような話し合いを行い、それぞれどのように作品を立ち上げていこうと考えているのかを聞いた。
演出・齋藤雅文(新派文芸部)
現代の“国崩し”を作り出したい
──演出において、「ここはこだわりたい」と思われているポイントを教えてください。
新しい“国崩し”の誕生ということですね。古典に頼るのではなく、現代の“国崩し”を幸四郎さんと作り出したいと思っています。
──そんな世界観を作り出す舞台空間について、幸四郎さんからのリクエストは?
小手先ではなく、大歌舞伎らしい堂々とした舞台美術にしようと話し合いました。なにせ「花の御所」ですから、花もいっぱいの美しい舞台を、と。
──作品の下敷きになる「リチャード三世」を知っている方が観るとさらに面白いポイントがある作品です。演出上、シェイクスピア作品を意識しているところがあれば教えてください。
王の“血(血統)”にこだわり続けるところが歌舞伎の世界と二重写しに見えるところ。虚と実が裏表となる、スリリングな楽しさでしょうか。
──仁木弾正や松永大膳のような“大きな悪”の役です。こういった古典を参考にしたという部分があれば教えてください。
これは幸四郎さんに聞いてください(笑)。
──幸四郎さんとの舞台も多い齋藤さんだからこそ知る、幸四郎さんの魅力を教えてください。またそんな幸四郎さんから今作で、どんな部分を引き出したいと思われていますか?
都会的で、スタイリッシュで、繊細なのですが、実は頑固で、骨太な人です。子供のままの魂の人。ですので、常人には理解できないアイデアが突然出ます。
舞台美術・中嶋正留
彼岸花も使って、今回は特に派手な舞台美術に
──今回の舞台美術について、幸四郎さんからどんな要求やリクエストがありましたか?
幸四郎さんは常に舞台転換をスムーズに早く見せることを望みますので、転換に時間がかからない舞台にしています。また今回は地下の土牢の場で仕掛けのある道具を望まれました。
──お客様が作品をご覧になる際、舞台美術のこんなところを意識するとさらに面白く観られる、というポイントがあれば教えてください。
歌舞伎座は毎月公演する劇場の中で一番広い舞台なので、大平の御殿など立派に見えますし、特に今回は派手な道具にしました。演出の齋藤さんも造花を使うのが好きなので、一度使ってみたかった彼岸花を飾りました。きっと綺麗だと思います。
衣裳・藤戸詠子(日本演劇衣裳)
「リチャード三世」が背後に見えるような衣裳に
──今回のお衣裳について、幸四郎さんからどんな要求やリクエストがありましたか?
今回は資料が少なかったので、すべてにおいて探り探りでした。ただ今回は大前提として、“(松本)白鸚さんのために宇野信夫さんが書き下ろし演出された原型を核に据え、少ない記録や想像、考察によって作品を立ち上げたい”というお気持ちだと感じたので、衣裳もその意向に沿ってやろうと思い、まずは前回に則って準備しました。記録を見てもわからないところはありましたが、歌舞伎は映像と違い、時代考証に正確なだけではない自由さがあるので、その武器をもって役柄がわかりやすい衣裳立てをしてみました。
──仁木弾正や松永大膳のような“大きな悪”の役です。こういった古典から参考にした部分などを教えてください。
「花の御所始末」という作品自体、シェイクスピアの「リチャード三世」の和製という意識が根底にセンスとしてあると思いましたので、衣裳作りではそのムードを考えました。ですので、今回は歌舞伎の古典からの引用は意識せず、「リチャード三世」が背後に見えるムードを作りたく、歌舞伎ならこんな感じだろうかと考えながらやりました。時代の違う芝居ではなかなか出ない古い衣裳も使っています。お客様にはそんなところも観ていただけたらと思います。
──お客様が作品をご覧になる際、衣裳のこんなところを意識するとさらに面白く見られるというポイントがあれば教えてください。
演出の齋藤雅文さんからは、特に序幕の場面を華やかにしたい、と。時代感を出して、さっぱりしないように華やかに。花の御所の華やかさは念頭におきました。明との交易、義満が取り立てた能が盛り込まれるなか、この時代に起こった辻が花染めを上手く取り入れることができなかったのが残念でした。義満がお能の世阿弥を見出だしたり、明との交流などがあった時代ですし、衣裳で言えば辻が花が出た時代ですので、幸四郎さんの衣裳でも一部、そのイメージを意識した箇所はあります。室町時代のお芝居自体があまり多くないので難しかったですが、あくまでもお芝居ですので、お客様にその人物の立場などがわかりやすくなるように、時代考証はしながらも、お客様には、そのままを観ていただき、それぞれに、感じていただきたいですね。
床山・市川純也(東京鴨治床山)
カツラは今のところ6枚。比べて見ると違いがあります
──今回のカツラについて、幸四郎さんからどんな要求やリクエストがありましたか?
今回は映像も残っていないので、資料は当時の写真だけでした。若旦那(幸四郎)は、旦那(白鸚)の写真を見せてくれて「まずは同じようにお願いしたい」と。ただ、前回の鬘は写実的に見せるために網だったものを、今回は「より歌舞伎らしく見えるように羽二重にしてほしい」と言われました。
──仁木弾正や松永大膳のような“大きな悪”の役です。こういった古典を参考にしたという部分があれば教えてください。
“悪”としての表現を強めるために、仁木や大膳がそうであるようにクリ(生え際)、特に小額(眉毛の延長線上の生え際)の部分を強くしています。小道具さんが用意する烏帽子から、クリがピッと出るようにしたり、鬘自体が見えるように工夫しています。
──お客様が作品をご覧になる際、カツラのこんなところを意識するとさらに面白く見られるというポイントがあれば教えてください。
今回、幸四郎さんが演じる義教は、最初の登場時は若者で次男、次の登場では5年の時を経ていて、将軍への謁見場面など、登場する度に立場も位も上がっていきます。寝所の場面もありますし、後半は狂気に苛まれるなど、心の変化が激しいお役ですので、場面ごとの鬘を用意しています。今のところ、6枚。比べて見ると細かい違いがあります。
今月の黙阿弥
放蕩生活が作品に寄与、黙阿弥ってどんな人?
没後130年を迎える河竹黙阿弥にちなんだこちらのコラム、舞台では“昭和の黙阿弥”と称される宇野信夫作品をご堪能いただくとして、今回は作者部屋の人となる以前の黙阿弥について書いていこう。
黙阿弥は幼名を芳三郎といい、江戸日本橋で湯屋の株の売買をする越前屋勘兵衛の長男として文化13年(1816年)に誕生。祖父はなかなかの通人だったらしく、「江戸町中喰物重宝記」(江戸のグルメガイド)を伴侶に、初鰹、初鮎、初鮭を食す江戸っ子だった……なんてエピソードも残っている。
黙阿弥は若い頃から遊蕩にふけり、14歳の春、柳橋の料亭へ上がり込むところを見つかり勘当に。黙阿弥の述懐によると、当時は悪友の家を渡り歩き、茶番狂言を考えたり、狂歌も詠み、雑俳の点者もし、貸本屋の手代となったり……と、毎日を呑気に遊び暮らしていたとか。
父が亡くなってからも弟に家督を譲って遊興生活を続けていたところ、転機が訪れる。踊りの師匠の紹介で五代目鶴屋南北(大南北=四代目鶴屋南北の孫)の門に入り、天保6(1835)年、20歳のとき、勝諺蔵(かつげんぞう)を名乗って市村座で狂言作者見習いに。遊蕩の賜物となった。一時劇場を退いた時期を挟みつつ、河原崎座に勤め、芝(のちに斯波)晋輔の名前を経て、天保14(1843)年、28歳で、二代目として河竹新七の名を継いで立作者(座付作者の筆頭)となった。
「歌舞伎座で会いましょう」特集
![松本幸四郎と中村七之助が“因縁の二人”を演じる、1月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 松本幸四郎と中村七之助が“因縁の二人”を演じる、1月は歌舞伎座で会いましょう
![片岡仁左衛門が“一世一代”で「霊験亀山鉾」に挑む、2月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 片岡仁左衛門が“一世一代”で「霊験亀山鉾」に挑む、2月は歌舞伎座で会いましょう
![中村隼人、晴明神社へ。宮司から聞く“安倍晴明”像 4月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 中村隼人、晴明神社へ。宮司から聞く“安倍晴明”像 4月は歌舞伎座で会いましょう
![尾上眞秀、小さな身体に勇気と闘志をみなぎらせ初舞台「音菊眞秀若武者」に挑む! 5月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 尾上眞秀、小さな身体に勇気と闘志をみなぎらせ初舞台「音菊眞秀若武者」に挑む! 5月は歌舞伎座で会いましょう
![片岡仁左衛門、“憎めない男”いがみの権太の悲劇を色濃く描き出す 6月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 片岡仁左衛門、“憎めない男”いがみの権太の悲劇を色濃く描き出す 6月は歌舞伎座で会いましょう
![市川團十郎、江戸っ子らしいダイナミックな世話物「め組の喧嘩」、エンタテインメント性たっぷりな舞踊劇「静の法楽舞」で“歌舞伎の幅広さ”をお届け]()
- 市川團十郎、江戸っ子らしいダイナミックな世話物「め組の喧嘩」、エンタテインメント性たっぷりな舞踊劇「静の法楽舞」で“歌舞伎の幅広さ”をお届け
![「新・水滸伝」中村隼人ら15名の“荒くれ者”が大集合! 8月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 「新・水滸伝」中村隼人ら15名の“荒くれ者”が大集合! 8月は歌舞伎座で会いましょう
![中村歌六・中村又五郎、「秀山祭」で中村吉右衛門をしのぶ、9月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 中村歌六・中村又五郎、「秀山祭」で中村吉右衛門をしのぶ、9月は歌舞伎座で会いましょう
![山田洋次・中村獅童・寺島しのぶが新たに立ち上げる「文七元結物語」、10月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 山田洋次・中村獅童・寺島しのぶが新たに立ち上げる「文七元結物語」、10月は歌舞伎座で会いましょう
![尾上菊之助・中村米吉・中村隼人、宮城聰演出の壮大なインドエンタテインメント「マハーバーラタ戦記」再演に挑む! 11月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 尾上菊之助・中村米吉・中村隼人、宮城聰演出の壮大なインドエンタテインメント「マハーバーラタ戦記」再演に挑む! 11月は歌舞伎座で会いましょう
![初演以来のスタッフが語る“「超歌舞伎」の足跡”12月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 初演以来のスタッフが語る“「超歌舞伎」の足跡”12月は歌舞伎座で会いましょう