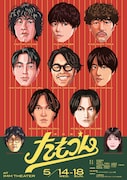澤瀉屋魂が宿る、宙乗りのコツ
──猿翁さんによる大掛かりな宙乗りは、1968年に始まりました。カチャッとワイヤーを付け、だんだんと役者の身体が地上から離れて宙に浮いてグングンと飛び、客席の幸福感や高揚感がマックスになると次第に観客の目から綱が見えなくなる……澤瀉屋の宙乗りはスタートからゴールまで、動きや目線の運び、随所が計算されていて美しく、やはり特別感があります。心がけているポイントはありますか?
猿之助 「“宙吊り”になってはいけない」とは言われますね。でも細かなコツは、僕も経験を積んで自然にわかってきたことです。あと、あくまで芝居の一部ですから、宙乗りだけが目立つのではなく、物語を積み重ねた流れの中になくてはいけません。つまり、お客様がここで飛ぶ“必然”を感じる瞬間に飛ばないと盛り上がらないんです。
──猿翁さんもご著書で「観客の期待、ここで宙乗りがあったらな、と思う夢、願望が一致した時に盛り上がる」「宙乗りは肉体プレイではなく頭脳プレイ」と書いていらっしゃいます。猿翁さんの宙乗りで印象に残っているものはありますか?
猿之助 やっぱりキレイだと思うのは、十二単姿の化け猫が飛ぶ「獨道中五十三驛(ひとりたびごじゅうさんつぎ)」でしょうね。六代目尾上梅幸の「羽衣」の天女の宙乗りのような前例もありますが、布がたなびく形は惹かれるものがあります。宙乗りはやはり、美しくなくてはいけないと思いますね。
笑也 僕はスーパー歌舞伎の第1作、「ヤマトタケル」が豪華で好きです。
──ヤマトタケルが「天翔ける心、それが私だ!」と言って、一羽の白鳥となって飛び立つ感動的な宙乗り。
笑也 随分前、師匠が「ヤマトタケル」をなさったときに私が宙乗りのテストをしたのですが、師匠の胴回りに合わせたパンツ型のハーネスがゆるゆるで、吊られたときに大事な所に食い込んで大変な苦しい思いをしました。一生忘れられない痛みです!
一同 (笑)。
猿之助 「ヤマトタケル」は大きな翼を動かすために両手がふさがっているから、いざというときに手が使えなくて、神経を使う宙乗りなんですよ。
まだまだあるぞ、澤瀉屋の宙乗りバリエーション
──「ワンピース」(参照:スーパー歌舞伎「ワンピース」開幕、猿之助が宙乗りで新アイテムのタンバリン鳴らす)でのサーフボード乗り、「新版 オグリ」の左右同時宙乗りなど、猿之助さんも現代的で印象に残る宙乗りで趣向を凝らしています。幸四郎さんとのコンビで人気シリーズ「弥次喜多」は、毎回コミカルな宙乗りがお楽しみ。紙吹雪に文句を言いつつの宙乗りや、ポップな音楽に乗せて3階から1階に逆流する形で登場……なんてこともありました。
猿之助 「弥次喜多」では、2人が花火で打ち上げられて宙乗りするのが1つのお約束になっています。趣向は変えつつ、作品をまたいで“ご存じ”のような形でやる宙乗りのスタイルは珍しいですよね。でもこれもやはり、芝居の中から導き出して考えないと浮いてしまう。飛ぶのが眼目ではなく、物語の中に溶け込んでいないと「なんで飛ぶの?」ということになってしまうんです。
──いつか歌舞伎座でやりたい宙乗りの構想はありますか?
猿之助 両花道の宙乗りは歌舞伎座でいつかやりたいと思っています。客席を減らすことになるのでなかなか難しいのですが、機構としてはできるはずなんですよ。あと、愛知・中日劇場「雪之丞変化」(2015年)でもやった、客席の上を斜めに飛ぶ“筋交い(すじかい)の宙乗り”。いつか歌舞伎座でやりたいですね。
──今年1月の「義経千本桜 川連法眼館の場(四ノ切)」では、コロナの感染症対策でできなかった宙乗りを久々に披露、また猿之助さんが2017年の怪我からご復帰されて初の狐忠信ということもあり、ダブルで感動的。ご一門の皆様が侍や腰元姿で舞台にずらりと並んで宙乗りを見送る形はスペシャルバージョンで、賑々しく胸熱でした。
猿之助 澤瀉屋にとって宙乗りは大事なものですし、お正月なので華やかに、祝祭劇としてやってみましょうと、少し目先を変えてみました。劇中の腰元のセリフにもともと「何はともあれ木陰にて、ことの様子を伺いましょう」とあるんです。最後に出ない通常の形でも、みんな密かに狐の物語を木陰から見ているのだと思います(笑)。
笑也 義経と静御前だけが見送る形に慣れたお客様は、驚かれたかもしれませんね(笑)。
──それぞれの家の工夫 / 持ち味で、さまざまなバリエーションが見られるのが観客の幸せです。
笑也 澤瀉屋の「四ノ切」は師匠が練り上げたものですから、思い出が詰まっています。“テンポ”については、師匠にかなり鍛えられましたね。古典は通常、黒御簾の頭を聞いてから曲に乗ってセリフを言い出すのが普通です。でもうちの師匠は我々弟子に「頭を聞くな。倍間でしゃべろ」といつもおっしゃっていました。これが古典をスピーディーに見せる隠し味なんだと思います。もちろん主役の方はご自分のペースでなさりますが、脇は聞かせなくちゃいけないセリフだけにインパクトを与えて、あとは走って回す。脇の仕事はそういうことだと思っています。邪道なのかもしれませんが、こういったことの積み重ねが“澤瀉色”の秘訣だと思います。
──緩急のメリハリが効くことで、より内容もわかりやすく感じられます。澤瀉屋さんは立廻りも、とりわけ早くて爽快です。
笑也 とにかく早い早い(笑)。主役がオーケストラの指揮者でその日のペースを決めるわけですが、脇はそれを察知して「今日は昨日より遅めかな」「今日はとりわけ早いな」と、その日の速度に合わせて行きます。今も四代目に合わせてとにかくスピーディーです。
──3月に上演された「新・三国志」(参照:「新・三国志」市川猿之助&市川青虎が関帝廟を訪問「関羽様にお祈りを」)関羽の宙乗りでは、桃の花が大量に客席に降り注ぎました。当初「三部制で入れ替え時間が短いので量は抑えめに」と指示していたのを、劇場側が「スピードを上げて清掃作業するので、量は減らさないで宙乗りしてください」とおっしゃったと聞きました。
猿之助 僕もそのことを人づてで聞いて驚きました。心意気ですよね。花びらの量が増えていったのは、飛んでいてもわかったんですよ。歌舞伎は裏方も芝居をしてくれないと成立しないということを、ひしひしと感じました。
──3階に鳥屋(とや。花道奥の控え所)をつくり、テストを重ねて初日を迎え、日々神経を使いながら実現する宙乗りは、裏で活躍するお弟子さんも含めたスタッフ&キャスト、チームワークの結晶だと思います。
猿之助 事故も見ているし、経験も失敗も重ねていますから、歳を重ねれば重ねるほど怖くなる部分もあります。チーム全員が力を合わせないと宙乗りは決してできません。
──最後に改めて、「當世流小栗判官」の小栗&照手の宙乗りの見どころを伺って参ります。初演当時ヒットしていた映画「E.T.」の、空中を駆ける自転車から想を得たという逸話も残っています。
猿之助 そうなんです。あと、馬の二人乗りは通常女性が前で男性が後ろですよね。伯父が映画「イージー・ライダー」を見ていたとき、後ろに女性を乗せる形を思いついたとも聞いています。また“人馬一体”は技としても珍しいですし、馬が飛ぶのは新しい歌舞伎座になって初めて。そして白馬に赤姫が乗っている画自体が美しいですよね。お姫様は横座りで、またげないから怖いでしょう?
笑也 念の為2つのベルトを装着するのですが、師匠と飛んだときに一度、うっかり片方だけで出てしまったことがあって。あのときは本当に怖かったです(笑)。
──艱難辛苦を乗り越えた小栗照手が、天馬で天空高く駆けてゆく姿は心が弾みます。
猿之助 あそこは義太夫の三味線も良い手がついていますしね。2人は将軍に反旗を翻した悪者の横山大膳親子討伐に向かうわけですが、熊野の山中(三重)から常陸国(茨城)はあまりにも遠いじゃないですか。まあ、天馬が一番便利で早いんですよ(笑)。
プロフィール
市川猿之助(イチカワエンノスケ)
1983年に「御目見得太功記」で二代目市川亀治郎を名乗り初舞台。女方から立役まで幅広い芸域と舞踊の名手として若手の頃より注目を浴び、2012年にスーパー歌舞伎「ヤマトタケル」で四代目市川猿之助を襲名。伯父の三代目猿之助が創出したスーパー歌舞伎をⅡ(セカンド)として継ぎ「ワンピース」など話題作を生み出す。NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」、8月に歌舞伎座「八月納涼歌舞伎」、9月に「市川猿之助 春秋座 特別舞踊公演」に出演。
市川猿之助 ENNOSUKE ICHIKAWA Ⅳ (@ennosuke_ichikawa4) | Instagram
市川笑也(イチカワエミヤ)
1980年に国立劇場第五期歌舞伎俳優研修終了、同年本名で初舞台。1981年に三代目市川猿之助(現・猿翁)に入門し、二代目市川笑也を名乗る。1990年に三代目猿之助(現・猿翁)の部屋子となる。復活狂言やスーパー歌舞伎では多彩なヒロインを演じている。8月に歌舞伎座「八月納涼歌舞伎」に出演。
「歌舞伎座で会いましょう」特集
![歌舞伎座で会いましょう 松本幸四郎×市川猿之助×中村獅童が語る、1月は「壽 初春大歌舞伎」で会いましょう]()
- 歌舞伎座で会いましょう 松本幸四郎×市川猿之助×中村獅童が語る、1月は「壽 初春大歌舞伎」で会いましょう
![歌舞伎座で会いましょう 尾上菊之助が語る、2月は「鼠小僧次郎吉」で会いましょう]()
- 歌舞伎座で会いましょう 尾上菊之助が語る、2月は「鼠小僧次郎吉」で会いましょう
![奇跡の五右衛門対談!松本幸四郎と古田新太が語る、3月は「石川五右衛門」で会いましょう]()
- 奇跡の五右衛門対談!松本幸四郎と古田新太が語る、3月は「石川五右衛門」で会いましょう
![尾上松緑とペリー荻野が“時代劇愛”を込めて語る“大岡越前”、4月は「天一坊大岡政談」で会いましょう]()
- 尾上松緑とペリー荻野が“時代劇愛”を込めて語る“大岡越前”、4月は「天一坊大岡政談」で会いましょう
![坂東彦三郎・坂東巳之助・尾上右近・中村米吉・中村隼人“令和の白浪五人男”撮影レポ、5月は「弁天娘女男白浪」で会いましょう]()
- 坂東彦三郎・坂東巳之助・尾上右近・中村米吉・中村隼人“令和の白浪五人男”撮影レポ、5月は「弁天娘女男白浪」で会いましょう
![市川染五郎と齋藤雅文が新たに作り出す信康像、6月は「信康」で会いましょう]()
- 市川染五郎と齋藤雅文が新たに作り出す信康像、6月は「信康」で会いましょう
![市川染五郎と市川團子が過去作&新作を語る! 8月は「弥次喜多流離譚(やじきたリターンズ)」で会いましょう]()
- 市川染五郎と市川團子が過去作&新作を語る! 8月は「弥次喜多流離譚(やじきたリターンズ)」で会いましょう
![松本白鸚・松本幸四郎・尾上菊之助が語る、9月は二世中村吉右衛門を思いながら「秀山祭九月大歌舞伎」で会いましょう]()
- 松本白鸚・松本幸四郎・尾上菊之助が語る、9月は二世中村吉右衛門を思いながら「秀山祭九月大歌舞伎」で会いましょう
![尾上松緑と西森英行が語る“講談を歌舞伎に”、10月は「荒川十太夫」で会いましょう]()
- 尾上松緑と西森英行が語る“講談を歌舞伎に”、10月は「荒川十太夫」で会いましょう
![市川海老蔵改め十三代目市川團十郎白猿の誕生を見届けに、11月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 市川海老蔵改め十三代目市川團十郎白猿の誕生を見届けに、11月は歌舞伎座で会いましょう
![坂東玉三郎が魅せる“江戸っ子の意気地や粋”を味わいに、12月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 坂東玉三郎が魅せる“江戸っ子の意気地や粋”を味わいに、12月は歌舞伎座で会いましょう