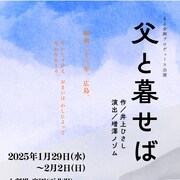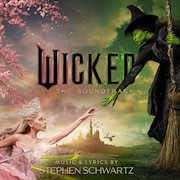アナログと人力と映像と…
──倉持さんの作品は、具体性と抽象性のバランスがいつも絶妙だと思います。戯曲の中で、具体的に出さなくても成立しそうなものをあえて美術として出現させたり、そのままリアルに出しても良さそうなものを書き割りなどで表現したりと、具象と抽象の取り合わせが独特で、そこが驚きと笑いを生むのではないかと思うのですが、「イロアセル」も、倉持さんがどういった表現を選ぶのか、楽しみなシーンがいくつもあります。
抽象性と具体性については毎回意識しているかもしれないですね。演劇だから、リアルにやっても限界があるというか、リアルにやりすぎるのは面白くない。それならなるべくふざけたいという思いがあって。「イロアセル」も、映像で表現すれば色がついた言葉もイメージした形で出せると思う。でもそれだけは絶対にやりたくないと思っていて、「ちょっとそれ無茶だろ」って思われるギリギリの線を突きたいなって思いがあるんですよね。だから序盤ではちょっと強引な表現じゃないかって笑われちゃうような演出を、後半で成立させたいと思って取り組んでいます。
──スタッフも魅力的な方ばかりです。美術の中根聡子さん、照明の杉本公亮さん、映像の横山翼さん、音響の高塩顕さん、音楽の田中馨さん、衣裳の太田雅公さん、振付の小野寺修二さんと、これまでにも倉持作品に関わりのある方々がそろいました。倉持さんの作風を知る方たちが、「イロアセル」の作品世界をさらに膨らませてくれるのではないか、と期待が高まります。
そうですね。アナログと人力と映像と、いろいろなセクションが合わさって良いバランスになると思います。小野寺さんにはカンチェラという架空のスポーツについて考えていただいて、「カンチェラとは何か」というところから話し合って作りました。すごく楽しい作業でしたね。
──カンチェラのイメージは、ご執筆時は……。
(きっぱり)ないです! 色に関わる島だから、電球照明と反射板とプリズムとか水晶みたいなもので7色になる芸術が生まれたら面白いなって思ったところから、カンチェラをイメージしていったんですけど、実際にどうやるかというところまでは考えずに書いていて。色の出し方についてもカンチェラについても、10年前に無責任に書いたものの責任を、今自分で取ろうとしてるわけですが(笑)、その作業は面白いですね。どちらも僕は僕なりのアイデアを稽古場に持ってはいくけど、各セクションの人たちと話し合って一緒に作り上げている。その共同作業は普段より濃いものになっていると思います。
クリエーションの在り方に変化を感じる
──先ほど、匿名性の言葉が10年前より激化しているのでは、というお話がありましたが、近年、SNS上での発言が現実に大きく作用する社会になってきました。書き手も、これまで以上にさまざまな配慮をするようになってきたと聞きますが、倉持さんはその点について実感はありますか?
意識はしているんでしょうね。現に、「イロアセル」の台本の中でも、あるセリフを直しました。あくまでそれは芝居の中のセリフなんだけど、そのセリフが引っかかって芝居全体がつまらないと思う人がいたらイヤだなと思って。僕は、どのセリフも作家の主張とか思想そのものではないと思うし、その役が戯曲の中でどういう人間で、どういう言葉を話す人物かということを考えてセリフを紡いでいるのだけれど、今は「そういう考えを持った作家が書いたものだ」と捉えられてしまうんじゃないか、と意識するところが確かにあるかもしれないですね。
その一方で、例えば映画の脚本の仕事などでは、一般公開の前に一般の人を何人も呼んで何度も試写をやり、ちょっとでも「わからない」って感想があると直していくんです。でもそれを繰り返していくと、一番感度が低いところに合わせていくことになってしまい、それはすごく良くないことだとも思っていて。「誤解されないように書こう」とすることは大事ですが、誤解を恐れてものを作るべきなのか、ということも感じるのでそこで闘っている部分はあります。
──また、小川さんが芸術監督になってからスタートしたフルオーディション企画やこつこつプロジェクトは、どれも創作の現場を根底から見直し、創作に関わる人たちや作品そのものを変化させていこうという試みです。さらにこの1年半、コロナ禍によって配信が当たり前になり、“演者と観客が同一空間で同じ時間を共にする”という舞台作品の前提も問い直されました。クリエーションの場に大きな変化が起こり始めていると感じますが、倉持さんはその点についてどのように感じていらっしゃいますか?
それは僕も感じます。過渡期だなって。どんどん作り方が変わってきていますよね。またクリエーション現場でのハラスメント問題なども近年問題になってきています。そうやって考えると、これまでは原初的な……野蛮な作り方だったのかもしれないなと思います。例えば小川さんは、クリエーションに時間をかけることの大切さを提唱していますが、確かに僕らは突貫工事で作ってきたところがあって。テレビも映画も演劇も「時間とお金がない」って、みんな睡眠時間を削って精神論で作ってきたけれど、みんながそれを変えようとしているのは感じるし、僕も変えたいと思っています。
──そういう点でも、このフルオーディション企画は今後のクリエーションの在り方に影響しそうですね。
本当にそうですね。時間はかかると思いますけど、これも大きな改革の1つだと思います。
プロフィール
倉持裕(クラモチユタカ)
1972年、神奈川県生まれ。劇作・演出家。2000年にペンギンプルペイルパイルズを旗揚げし、すべての作品の作・演出を務める。2004年に「ワンマン・ショー」で第48回岸田國士戯曲賞を受賞。近年は外部への書き下ろしのほか、映像作品も多数手がける。近年の主な劇作作品にミュージカル「HEADS UP! / ヘッズ・アップ!」、劇団☆新感線 いのうえ歌舞伎「乱鶯」「けむりの軍団」、ヴィレッヂプロデュース「浦島さん」(脚色)、作・演出作品に「お勢登場」「誰か席について」、竹生企画「火星の二人」、M&Oplaysプロデュース「DOORS」、「鎌塚氏、放り投げる」をはじめとする“鎌塚氏”シリーズなど。
M&O Plays 森崎事務所 所属アーティスト 倉持 裕(くらもち ゆたか)<劇作・脚本・演出>
ペンギンプルペイルパイルズ - 劇作家・演出家の倉持裕が主宰する、東京を拠点に活動する劇団「ペンギンプルペイルパイルズ」の公式ウェブサイト
次のページ »
スタッフが語る「イロアセル」