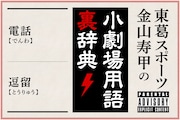2017年にKAAT神奈川芸術劇場にて劇団最終公演を行ったサンプルが、松井周ソロユニットとして再始動。KAATとタッグを組み、深沢七郎の名作「楢山節考」の“姥捨て”のエピソードに焦点を当てた、「グッド・デス・バイブレーション考」を上演する。主演を務めるのは、12年ぶりの舞台出演となる戸川純。“グッドデス(安楽死)”が推奨される近未来の世界を舞台に、閉ざされた地域に暮らすある一家が、どのような“選択”に至るかを描く。「これまでとは異質で、面白いものになると思う」と自信を覗かせる松井に、4月上旬、稽古場で話を聞いた。
取材・文 / 熊井玲 撮影 / 三浦一喜
“捨てられる”は創作テーマの1つ
──執筆中の台本を拝見して、ページを読み進めるのが怖くなるような、SF感と現実感が共存する作品になりそうだと思いました。“姥捨て”の慣習がある村を描いた深沢七郎の「楢山節考」から想を得ているとのことですが、そもそも松井さんが「楢山節考」に興味を持たれたきっかけは?

「楢山節考」深沢七郎著(新潮文庫)
確か大学の頃に、先輩から「面白いから読んでみろ」って言われたんじゃないかなと思うんですけど、最初は“切っても切れない親子の情”を描いた感じの話なのかなと思っていたんですね。ちょっと湿っぽいと言うか、ウエットな話なのかなと。でも実際は全然印象が違って、どちらかと言うとカラッとした話。それでずっと、興味を持っていたんです。姥捨てって両義的と言うか、非常に前近代的で人権がないひどい話とも読めるし、その一方で家族の状況に合わせた合理的な話とも読める。「楢山節考」はどっちの意味で書かれているんだろうってことがずっと頭に引っかかっていました。また、僕がさいたまゴールド・シアターに書き下ろした「聖地」(10年)も捨てられる老人たちが老人ホームに立てこもる話でしたが、“捨てられる”ということが1つ、自分のテーマとしてあるのかなと思います。
──このインタビューの前に、「楢山節考」や深沢さんのエッセイを改めて読み返したのですが、深沢さんの社会の捉え方、死生観にはどこかサンプルの作品世界と近いものを感じました。
そうですね、僕も近いのかなって感じを持っています。自分がやりたいものの基準の1つに深沢作品があって、もしかしたら僕がそれに合わせるように作品を作ってきたのかな、という感じもしていて。
──本作で描かれるのは、近未来の閉ざされた地域に暮らすある家族。新・輪廻転生法により、貧困家庭の65歳以上の人間は、肉体を捨てることを政府から望まれています。その65歳という年齢設定や、登場人物の名前、方言ふうの話し方は、まったくのフィクションというよりどこか現実味を帯びていて、それゆえに身に迫ってくる不気味さを感じさせます。
この世界では例えば、あまり意味がある名前を付けづらくなっているんじゃないかと思うんです。名前って1つの差別じゃないですけど特権ですから、もはやあまり意味がない、例えばザラザラとかブルブルとかツルツルとか、擬音になりそうなものが名前になっている。参考にしたのはガンダムのモビルスーツなんですけど(笑)、グフとかザクとかゲルググとか、語感の気持ちよさで付けけられたようなもので、しかも意味のある文字もあまり使ってはいけないような時代になっているんじゃないかなと。
──なるほど、それで一番上の世代がツルオ、中間世代がヌルミ、一番下の世代がザラメ、クッコと名前の質がかなり違うんですね。
そうです。ツルオはまだ人の名前っぽいですけど、下の世代になればなるほど意味を持たない名前になってくる。
──劇中で「苗字ありか」というセリフが出てきますが……。
苗字ありの人はちょっとエリートと言うか、限られた人たちですね。それ以外の人たちは苗字で仕切られず、子供たちもみんなで育てていこうというような、そういうポリティカルコレクトネスが蔓延している世界なんじゃないかなと。
自分は社会でどういう歯車になっているか
──「楢山節考」では楢山詣りに行く年齢を70歳としていましたが、本作では65歳と少し若く設定されています。65歳にボーダーラインを引いたのはなぜですか?
(この世界では)政府が力を持っていて、個人が国に直接的に管理されているのではないかと。だから働けるうちはいいんですけど、年齢と共にだんだん働けなくなり、国のためにならなくなると政府は緊縮を推し進めていく。それで、65歳。65歳って「まだまだできるぞ」って本人は思ってる年齢だと思うんですけど、そこに境界線が引かれてしまう。
──現在の延長線上に、そういった“役に立つ人間とそうでない人間”を仕分ける世界があると、松井さんはお感じになっているということでしょうか?
感じますね。どんどん個人が直接管理される世界になっている感じがするし、その中で自分はどういう歯車になっているかを提示することが常に要求される感じがしています。
──お話を伺うと、ますますSF作家の伊藤計劃の作品のような壮大な世界観を感じます。
ああ、伊藤計劃は僕も好きです。
──また登場人物たちは「~だべ」など、方言のような言葉で会話しますが、場所についてはどのように考えていらっしゃいますか?
今よりすごくシンプルになっていて、中央とその周囲という二極化した世界、という感じがしています。山の中の村落という設定にしたのは、そういう場所のほうが慣習みたいなものを作りやすいと思ったからなんですけど。
──でも山の話でありながら、姥捨ての儀式を「入江に行って船出する」と表現するなど、海のイメージも内包しています。海と言うと1月に兵庫・城崎国際アートセンターでリーディング上演された作家・村田沙耶香さんとの共同執筆作を思い出します(参照:松井周&村田沙耶香の初共作をリーディング試演「思い描いた島の風景が見えた」)。同作では古い祭の慣習が残る、ある島が舞台でしたが、そのイメージもどこかに反映されているのでしょうか?
それもちょっとあるでしょうね。海のイメージにしたのは直感的なもので、山があったら海があると言うか、山に捨てに行くなら海に流す慣習もあるだろうと発想して、山の神様だけじゃなく海の神様に捧げるということを考えました。
──個人的に、山に男性的なもの、海に女性的なものを感じたので、ツルオが男から女になり、海に捨てられ波間に溶けていく、というイメージが1本のラインとしてつながりました。
なるほど! そういうのうれしいですね(笑)。
次のページ »
もっと情けないほうがいいんじゃないかなって
- KAAT×サンプル「グッド・デス・バイブレーション考」
- 2018年5月5日(土・祝)~15日(火)
- 神奈川県 KAAT神奈川芸術劇場 中スタジオ
- 作・演出:松井周
- 出演:戸川純、野津あおい、稲継美保、板橋駿谷、椎橋綾那、松井周
- 松井周(マツイシュウ)
 ©平岩享
©平岩享- 1972年東京都出身。劇作家、演出家、俳優。96年に平田オリザ率いる青年団に俳優として入団。その後、作家・演出家としても活動を開始し、2007年に劇団サンプルを旗揚げする。04年に発表した「通過」で第9回日本劇作家協会新人戯曲賞入賞、10年上演の「自慢の息子」で第55回岸田國士戯曲賞を受賞した。また、さいたま・ゴールドシアター「聖地」(演出:蜷川幸雄)、文学座アトリエの会「未来を忘れる」(演出:上村聡史)、新国立劇場「十九歳のジェイコブ」(演出:松本雄吉)、KAAT神奈川芸術劇場「ルーツ」(演出・美術:杉原邦生)など戯曲の提供も多数。17年「ブリッジ」にてサンプルは劇団として解体、18年「グッド・デス・バイブレーション考」より松井の1人ユニットとして再始動する。小説やエッセイ、テレビドラマ脚本などの執筆活動、舞台、CM、映画、テレビドラマへの出演なども行うほか、桜美林大学、四国学院大学、東京藝術大学、尚美学園大学では非常勤講師を務める。また上演台本・演出を手がける舞台「レインマン」が7月から8月にかけて東京、静岡、福岡、大阪、宮城、愛知にて上演される。