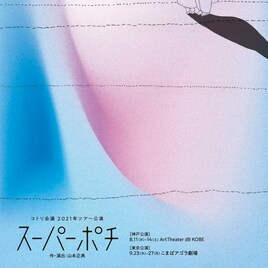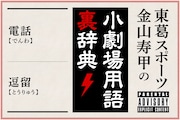現実を演劇という手法で面白がりたい
──上演に向けて、これまで何度かオンラインミーティングを重ねられているそうですが、お互いの話を聞きながら共通点や似た感覚を感じる部分はありますか?
中島 共通点かあ……。
一同 (笑)。
──例えば3劇団ともベースとして現実世界を描きつつも、現実をそのまま書くというより、大きくフィクションが入るところが共通しているのではないでしょうか。コトリ会議は数世紀先の日常を描いていたり、ウンゲツィーファは目の前で起きている出来事を別の角度から照射していたり、いいへんじは人間の皮を1枚剥がすようなアプローチをしていたり……。
中島 私の場合は、フィクションにしないと私自身がつらくなるということがあります。先ほど山本さんがおっしゃっていたことに通じるかもしれませんが、現実はつらかったり厳しかったりするので、それをそのまま描くのではなく、演劇という手法で何とか面白がれないかなと思っていて。
本橋 僕は、どちらかというとネガティブな意味で、現実と作品がどうしても切り離せない感覚があって。だからお二人は作品に現実が“入って”くるのか、それとも“入れて”いるのか、現実をどう扱っているのかは気になりますね。
中島 本橋さんはどうなんですか?
本橋 僕は、まず脚本を書くのがすごく苦手だってことが前提としてあって。それで今回、脚本を書ける人と一緒にやることにしたんですけど、僕は自分の経験から書くってことしかできなくて、そこから離れたいとずっと思っているんです。
中島 私も、自分のことしか書けないことにコンプレックスを感じています。だから突飛なこととかスペクタクルを生み出すことができないコンプレックスというか、強固なフィクションやエンタテインメントが作れる人ってすごいなと思うところがあって。ただ、自分が個人的なことだと思ったり、恥ずかしいと思っていることを、何とか演劇として面白くできないかと思ってやっているうちに、形にしたものに共鳴してくれる人とたまーに出会う、という経験をこれまでしてきて、それで続けてきたところがあります。
それと、本橋さんは自分の経験を書くスタイルから離れたいとおっしゃってましたが、私は脚本を書くときに、つらいけどそこをさらにやってみたいと思うところがあって。0から1を生み出すことができないなら、1を見極めてみようというような覚悟を決めた……と言って数年後に揺らいでいたらいやだから言い切れないんですけど(笑)、劇作家の自分と演出家の自分を分けて、今は書く期間と演出する期間を分けて、それぞれに注力するやり方を始めたところです。
本橋 もう1つ中島さんに聞きたいんですけど、自分のことを書くって人にも干渉するじゃないですか。例えば誰かと話した話を書いたときに、相手の人のことも関わってくる。そういったことで怒られたことはありますか?
中島 あります! カフカとカフカの恋人の手紙のやり取りを書いた作品のときに、自分と恋人のことを重ね過ぎてしまって、怒られるというか「気分が悪くなってしまった」と言われて(笑)。それまでは自分のエピソードを直接書くことが多かったんですけど、それ以降は自分のエピソードを何かに置き換えるようになってきました。現実をそのまま演劇にするってさすがに力が強いんだなと感じて、それをそのまま演劇にすることの力を良くも悪くも自覚したというか。
本橋 共感します。
──山本さんはこの3人の中で一番フィクション性が高いかもしれませんね。
山本 そうかもしれないですね、でもガスマスクって強烈だなって思いました(笑)。中島さんと同じく、僕も現実をそのまま舞台には乗せないんですけど、ちょっと方向を修正しないといけないなと日々感じることがあって。実は現実って、とても豊かで面白いんですよね。今、僕は、とある施設で用務員みたいなことをしてるんですけど、今日も草むしりをしてて、一緒に働いている人たちと休憩時間に空を見上げたら、雲が良い感じでたなびいていたんです。その雲や空の広さみたいなものってすごく美しいし、心に沁みるんですよね。でもそれをそのまま舞台に上げようとしても、とても敵わない。現実って、とてもスケールが大きいんです。またちょっと話が変わってしまうかもしれませんが、僕は自分が書いた台本を役者さんが声に出して話し出す瞬間を求めて、演劇をやってるんだなって思うことがあるんです。その瞬間、自分の内にこもっていた何かの皮が1枚剥がされて、何かが現実空間に放出される感じがあるんです……と考えると、自分はやっぱり現実を見たいのだろうか?と思って、現実と演劇の泥沼にハマっていくんですけど……。
一同 あははは!
シアターイーストは大きい?
──現実、という点で、昨年からコロナ禍により公演をすること自体が難しい状態が続き、演劇をやるために演劇の必要性や意義を声高に言わなければならない状況がありました。皆さんはそういった状況をどう感じていましたか?
中島 先ほどお話しした通り、いいへんじは10月に「器」という公演をやる予定でした。でも公演するかどうかで、劇団員とも何度も話し合いを重ねて……。そのとき、私個人としては「コロナに負けずに」とはあまり思えなかったんですね。それよりは悲しくなって、気力がなくなってしまって。また現実はどうしたって無視できないので、自分たちが生きるうえで怖いなとか不安だなと思う気持ちを、演劇のために抑えたくないな、そうやって演劇を嫌いになるのが一番いやだなとも思い、劇団員とも「自分の気持ちに正直になろう」と話しました。結局公演は中止になったのですが、そのように都度都度、個人や1団体としてできることを考えてやっていくしかないなと今は思っています。
山本 「コロナ禍でも演劇が必要だ」ということについて、自分の中ではまだ全然答えが見つかっていなくて探している最中です。でもどんな状況であっても、舞台に誰かが立って、その人が緊張しながら何かやっていることを受け取る、そういう空間はとても豊かだとは思っていて。ただそれがどういう形で行われるべきかについては、今悩んでいるところですね。
本橋 僕はちょっと難しくてわからないなって思ってます。ただ僕に関して言えば、特にこの1年状況は変わってなくて、もともと劇場で演劇をやっていたわけでもないし、その時々でできることをやってきただけで、その流れの中に昨年のこともあったという感じです。
──また今回、芸劇のシアターイーストが会場となります。下見されたそうですが、どんな印象を持たれましたか?
本橋 毎回、ある場所で何かやるということをやってきたので、特に何ら違いは感じないですね。
山本 広いなと思いました。でもそれ以上に劇場が置かれている場所が都会だなって(笑)。人がいっぱい来るところに建っている、すごい建物だなって思いました。
中島 私も、広いところにポーンと投げ込まれた感覚になって「ひえー」って思ったんですけど(笑)、思い返すと高校演劇をやってたときは、1000人くらい入るようなホールでやっていて、当時は顧問の先生の好みもあり、舞台美術を作り込み声を張って、空間を埋めよう、声を届けようとがんばってたんですけど、大学に入っていろいろな演劇を知って、いいへんじの作風も何となくできてきた今は、逆に広いところにポツーンといる感じでやろうと、下見の帰り道に決めました。
作り手として成熟した3人
──3団体それぞれカラーが違っていて、とても楽しみになりました。今回はショーケースなので、それぞれの共通点や違いも浮き彫りになると思いますが、現段階でお互いをライバルと感じていますか、それとも仲間という意識ですか?
山本 協調性はあまりないかもしれないですけど(笑)、かといってライバル視するにもまだ作品を拝見したことがないので、未知の世界に飛び込む感じです。
中島 このまま、それぞれがそれぞれのまま存在している感じがしますね。
本橋 優しい人たちだと思いつつ、今回の企画でそんなに仲良くなることはない気がしてるんですよ。でも、まだわかりませんけど、実はのちのち仲良くなりそうだとも思います。
──徳永さん、そんな3団体の皆さんにどんな期待を感じていらっしゃいますか?
徳永 一番最初の打ち合わせのときに皆さんにはお伝えしたのですが、“弱いい派”というくくりやコンセプトに寄せるのではなく、作りたいものを作ってくださいと。それが自然と“弱いい派”の具体例になると思っているので。と言ったところで山本さんの悩みは消えないかもしれませんが(笑)。今回の「もしもし、こちら弱いい派」は、過去2回の「芸劇eyes番外編」、2011年の「20年安泰。」、2013年の「God Save the Queen」(参照:演劇ジャーナリスト・徳永京子が語る「芸劇eyes」&「eyes plus」の10年<その2>)より参加団体が少ない分、1団体あたりの上演時間が長くなり、ご覧いただく方にも腰を据えて楽しんでいただけるのではないかと思います。合同リハーサルの日程が限られていたり、感染症対策などで皆さんには負担をおかけしていますが、皆さん苦しみながらも楽しんでやってくださっているようで、そういう点では作り手として成熟している人たちだと感じています。クオリティに関しても、まったく心配していません。“弱いい派”という枠組みを取っても、それぞれに素晴らしい才能を1度に3組観られる企画ですので、ぜひ多くの方にご覧いただきたいです。
- 中島梓織(ナカジマシオリ)
- 1997年、茨城県生まれ。劇作・演出家・俳優。2016年にいいへんじを結成。
- 本橋龍(モトハシリュウ)
- 1990年、埼玉県生まれ。劇作・演出家・俳優・ウクレレ吟遊詩人。2012年に創作ユニット・栗☆兎ズを結成、2016年にウンゲツィーファに改名。
- 山本正典(ヤマモトマサノリ)
- 1982年、福井県生まれ。劇作・演出家。2007年にコトリ会議を結成。第9回せんがわ劇場演劇コンクール劇作家賞、第27回OMS戯曲賞大賞受賞。