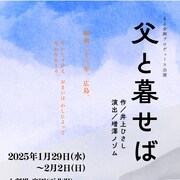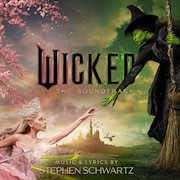2016年に「夏の夜の夢」で「市民と創造する演劇」に挑んだ扇田拓也が、8年ぶりに同シリーズに登場する。扇田にとって3回目の演出となる「地を渡る舟」に向けて、作品への思いや「市民と創造する演劇」にかける思いを聞いた。
豊橋での上演が“まさにぴったり”な「地を渡る舟」
──今回、まず扇田さんに演出のお話があり、その後作品が決定したそうですね。扇田さんは「地を渡る舟」の初演から演出を手がけていらっしゃいますが、今回「地を渡る舟」を上演することになり、どう思われましたか?
制作の吉川さんから「地を渡る舟」はどうかと提案いただいて、驚きつつも「ああ、その手があったか」と思いました。というのも、本作には「花祭」というお祭りが出てくるのですが、「花祭」は本作に登場する民俗学者たちが大好きな、愛知の奥三河で700年以上前から行われている古いお祭りなんです。てがみ座のツアーで豊橋に来たときも「ああ、ここは花祭の場所に近いところだね、見に行きたいね」という話が出たくらい。なので、吉川さんから「『地を渡る舟』はどうでしょう?」と提案いただいたときに、三河地方の豊橋で「地を渡る舟」をやるのは理にかなっているなと思いました。また劇中では“名もなき人びと”という言い方をされていますが、民俗学は農民や漁民など古い暮らしを続けて来た人たちの文化が消えてしまわないように、ちゃんと保存することを目指す活動です。そんな「地を渡る舟」の作品世界と、市民が演劇の舞台に立つという「市民と創造する演劇」のコンセプトが合致すると思ったんです。
──「地を渡る舟」は第58回岸田國士戯曲賞、第17回鶴屋南北賞にノミネートされた作品です。長田育恵さんが描く歴史を背景にした奥行きのある展開、重みのあるセリフの数々が印象的ですが、市民劇で上演する演目としてはかなり難しい戯曲なのではないでしょうか?
そうなんですよ、難しいんです(笑)。てがみ座で上演したときもそう感じたのですが、セリフ量だけでなく設定もかなり繊細で難しい作品です。当たり前に軍国教育を受け、でもいつの間にか戦争が起き、「日本が絶対に勝つ」と信じていた時代。そんな時代の中でも、民俗学者たちは未来を見据えていました。そういった人物を演じる以上、戦争のことはもちろん、当時のことをよく調べ、理解しないといけないし、そうすることによって初めて役を演じられる、という部分もあると思います。なので、出演者の方たちには課題図書のような形でいくつも資料を読んでもらっていたりしているのですが、皆さんものすごい熱量で稽古に臨んでくださるので、その“成長の伸び代”に期待をしています。
また、今この作品にチャレンジしてみたいと思ったのは、てがみ座で「地を渡る舟」を上演してからもうずいぶん経っているのと、僕も市民の方たちと交わるお芝居を何年も続けていること、豊橋の市民の皆さんも市民劇を何度も何度も経験されているので、挑戦できるのではないかなと思ったから。実際、稽古も順調に進んでいます。
発見にあふれた創作環境で、より良い作品を立ち上げる
──扇田さんがお感じになっている、「地を渡る舟」という作品の魅力はどんなところですか?
太平洋戦争が起きようとする状況下で、文化がいかに大事なものかということに注目していた民俗学者たちが、戦争によって文化が失われてしまうことを危惧し、それを回避しようと奔走します。彼らの姿は、インターネットやSNSが発達し、不必要と思われたものはどんどん切り捨てられていく、2024年の私たちにも感じるものが多いように思います。今、人と会わなくても仕事が成立しますし、それで便利なところはありますが、人に会って話すことや手触りの感覚が失われる怖さもあります。そういったことを、「地を渡る舟」という作品を通して感じられたらと思います。
──本作では、2023年夏に出演者募集とオーディションワークショップ、12月に出演者ワークショップが行われ、今年1月から本格的に稽古がスタートしました。稽古の手応えをどのようにお感じですか?
ものすごい熱量を感じていますね。市民の出演者さんには「だまされたと思って、バーンと思い切ってやってみてください」と言っているんですが(笑)、すると本当に思い切ってやってくださり、すごく大きなものを発見してくれたりするんです。どこまでいけるかわかりませんが、素敵なお芝居を目指すということは今、できていると思います。
最近の僕の演劇を作るモチベーションは、評価されるための演劇創作ではなく、稽古場で作っていく過程が楽しく幸せであるということ、いろいろな発見にあふれた創作環境を作り出すことなんです。そういう環境ができれば、自ずと良い作品が立ち上がるんじゃないかと思うので、1日1日、とにかく素敵な創作現場を作り出したいなと。
──確かに出演者の方たちは、とても楽しそうに生き生きと稽古されていました。
(笑)。あと、作品の難しさには、長田さんのセリフという部分もあって。長田さんが描くセリフは、なんでもない日常的なセリフのようなんですけど、1人の人物が一生をかけてもなかなか出てこないような、その人が一生に一度しか口にしないような、引力が強いセリフが多いんです。ものすごく選び抜かれた言葉遣いだったり、強烈な言葉なので、楽な身体では吐けないというか、それを発するのに必要な身体や精神を作り上げないといけない。そういった身体を出演者の方たちには作ってもらうということも意識しています。
演奏も市民たち、棚川寛子が作り出す音楽の力
──また今回は、棚川寛子さんの音楽も一番大きなポイントです。
そうですね。「地を渡る舟」に限らず、てがみ座で僕が演出するときは僕が音楽を選曲していますが、今回は書き下ろし、かつ生演奏なので、「ここにはこういう音が入ると素敵なんじゃないか」「セリフがこうだからもっと柔らかいニュアンスにしたい」といった細かい調整が可能なのが良いですね。今回、演奏も市民の皆さんがされるんですが、演奏する様子も客席から見えるようにしたいと思っていて。棚川さんもまさに同じように考えていてくださったので、単純にお芝居に合わせて音楽を作ってもらうということではなく音楽と登場人物が一体となる舞台になるんじゃないかと。実際、音楽からもらえる熱もありますし、俳優たちも「この音楽が入るならもっとパワフルに演じないとダメだな」という感じで、お互いに共演者という感覚で作っているのがいい刺激になっていると思います。
──扇田さんにとっては3回目の「地を渡る舟」となります。ご自身にとってはどんな思いで臨まれていますか?
今回は大庭さん、百花さん以外に、セリフが多めのメインキャスト12名と、11名のアンサンブルキャストが出演してくださり、さらに演奏する方も含めると33人の規模感になるので、てがみ座では叶わなかった集団創作ということができています。またこの作品では民具がたくさん出てくるのですが、「何かいい民具はありませんか」と募集すると、東京だったら集まらないだろうなっていうようなものすごい数が集まるんです(笑)。そうして集まった民具を見ていると、どれも木か鉄、布でできていて、日本人ってやっぱり植物や木材などをうまく使って生活を成り立たせていたんだなとか、手間暇かけて1つひとつのものを大切に作っていたんだなということを実感します。
そして8年前に「市民と創造する演劇」で演出したときにも感じたことですが、「オーディションをします!」と言ったときに、高校生から会社員、年配の方までこんなに人が集まってくれるのはすごいなと。で、いろいろな世代の人たちが話し合いながらお芝居を作っている姿は、地域にとってもすごく良いことなんじゃないかなと思います。出演者の中には毎年この「市民と創造する演劇」に参加してる人もいますし、参加したことがきっかけで東京の演劇系の大学に進学し、豊橋に戻ってきてまた市民劇に参加している人もいたりして、劇場が市民とつながろうとしてくれているのが良いなと思いますし、それがPLATの魅力になっているんじゃないかと思います。
──今回の上演は、てがみ座で上演された「地を渡る舟」をご覧になった方も、「市民と創造する演劇」シリーズのファンの方も注目していると思いますが、どんな上演となりそうでしょうか。
作者の長田育恵さんは、NHKのテレビドラマ「らんまん」で脚本の魅力を感じた方も多いと思いますが、長田さんの出発点は演劇でありてがみ座で、その長田さんの情熱が注がれた初期の作品を実際に観られる機会はなかなかありません。そういう意味で、「らんまん」ファンの方は皆さん観に来たほうが良いと思います(笑)。
またこの作品には、文化や戦争をどう考えるか、世界情勢をどう見るかという、日本人にとってとても大切なことが描かれていると思うのですが、そこに市民の皆さんがある意味、命がけで取り組んでいる。その命の輝きを見ていただきたいです。
そしてこの舞台をご覧になって、市民劇は素敵だなと思われた方は「あなたも出られますよ」とお誘いしたい。次はぜひ、参加していただきたいです。
プロフィール
扇田拓也(センダタクヤ)
1976年、東京都生まれ。演出家、俳優。1996年にヒンドゥー五千回を旗揚げし、全作品の構成・演出を担当。2018年の最終公演と同時に空 観(くうがん)に改称し、活動スタート。てがみ座、名取事務所、趣向、日生劇場ファミリーフェスティヴァルなどの公演で演出を担当。俳優座研究所の講師、演劇系大学での非常勤講師や市民劇、沖縄での滞在制作を積極的に行っている。
“名もなき人たち”が作り出す演劇と音楽のエネルギーで、劇場を満たしたい
──棚川さんは今回、作品のどのような点を意識して作曲をされましたか? また、二十数曲作曲された中で、例えばすぐイメージが形になった楽曲、あるいはとても悩んだ曲など特に思い入れがある楽曲があれば教えてください。
今はまだ仮に音を付けた段階ですのでまだまだこれからです。
初めて台本を読んだ時には、音楽をどこに入れるか、あるいは入れないか、場面ごとの芝居の内容や作品全体との関係、市民さんが生演奏で参加する意味などを考えました。
音楽隊8名の協力で生まれた楽曲をここから芝居に合わせて調整し、底上げしてきます。
どの曲にも思い入れがありますが「列島が発光する」という曲と、ラストの「行けるところまで」が特に好きです。
──演出の扇田さんとやり取りされる中で印象的だった言葉、エピソードがあれば教えてください。
長期滞在制作ということで扇田さんと制作助手の方と私の3名で共同生活をしているのですが、扇田さんは生活と演劇、芸術がひと続きになっている方だなと感じます。
生活があって演劇ができるし、演劇があって生活ができる。そんなふうに考えていらっしゃるんじゃないでしょうか?
──芝居チームと音楽隊の合同稽古を経て、本作において、音楽や音楽隊はどのような役割を担うと棚川さんは感じていますか? これから作品をご覧になるお客様に向けて、音楽が加わることでどのように本作の可能性が広がりそうか、ヒントになるメッセージをいただけますと幸いです。
第1次稽古では芝居と音楽が別々に作業していましたが、第2次稽古のこれからは合同になっていきます。
芝居と音楽がお互いに影響し合って全体の強度が増し、劇場空間全体をエネルギーで満たせたら良いなと思っています。
また、戯曲の中に出てくる「名もなき人たち」という言葉。それがまさに音楽隊やアンサンブルの皆さんとも重なります。その「名もなき人たち」がこの芝居で、またこの国の文化や民俗においても、決して脇役ではないのだということを伝えられたらなと思います。
プロフィール
棚川寛子(タナカワヒロコ)
舞台音楽家、演劇音楽家。宮城總演出作品の音楽を多数手掛けている。音楽を担当した主な作品に「マハーバーラタ~ナラ王の冒険~」「アンティゴネ」「極付印度伝マハーバーラタ戦記」、映画「かぞく」など。