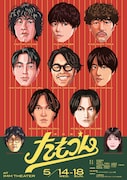答えを教えるのではなく、答えを一緒に探す関係に
──皆さんも研究所のご出身ですが、ご自身が研究生だったときと現在で、違いを感じるところはありますか?
手塚 僕が入った頃は、特に実技の授業だったりすると講師の方が良いと思ったものを「これが答えだ」と示されることが多くて、でも僕たちがやってもそれと同じものにはならないから成り立たない、ということがあって。劇団に入ってからは、「ああ、あれはあの人がやるからいいんだろうな」って思うようになりました。そのことがすごくひっかかっていたので、研究所に関わるようになってからは、答えを示すのではなく研究生本人が気づくようにアシストするというか、答えを一緒に探して寄り添っていくようにしたいと思っています。
植田 僕らの時代って、講師の方が世代的にも随分上だったし、手塚さんがおっしゃるように明確な答えを示されてそれにどう近づくかという授業が多かったと思うんですよね。でも確かに研究生たちが持っている言葉にできない何かを引き出したり、それが言葉にできるような時間や機会を与えたりすることが大事なんじゃないかと僕も思っていて。時代としてもそういう傾向なんじゃないかと思います。ただ授業時間や発表会の稽古時間が、その分かかるようになってきていて……。
一同 わかる!
植田 昔だったら講師や演出家が「ここはこう動いて、ここでこうやって」と指示する感じで短かったんですよね。でも今はまず自分で考えてやってみるという教え方で、「それだとうまくいかないから、じゃあこうしてみたらどうかな?」という感じで、答えをどう見つけるかに並走していく感じがある。そこはだいぶ前と違うんじゃないかなって。
小泉 例えば演出家が「はい、そこで右に2歩、そこから前に歩いて」って言ったら、研究生はおそらく「なんでそうするんですか? そうするときの登場人物のモチベーションがわからない」って言うと思うんです。でも発表公演のときなど外部の演出家がくることがあり、そういうときに彼らは戸惑ってしまう。もちろん、演出家の指示とモチベーションをつなげるのは役者の仕事なんですけど、研究生たちは授業で教わることと実際とが結びつけられないことがよくあり、そこは課題だなって。
手塚 確かに僕らくらいの年齢になると乗り越えられることでも、そこで行き詰まる子はいますね。ただこの5年、研究生も自分が思ったことを言葉にする訓練をしてきているので、変な気遣いなく、堂々と意見してくれるようになりました。そこがかなり変わりましたし、おかげでこちらも気楽になりました(笑)。
嶋田 社会的にも、例えば答えがないゲームとか、進め方によって永久に続けられるゲームも増えてきていますよね。だから、授業の中で「これが答えだ」と示したときに「what’s?」ってなる人が増えているように思います。
植田 そもそも研究所で教わることって、今流行っている価値観とは違うものだったりするところがありますしね。僕が入ったときは、「父帰る」とか「海神別荘」のテキストをいっぱいやっていて、実はびっくりしたんです(笑)。その思いから、今自分が教える側になって、油に乗って自分が活躍しているときの価値観が、研究生にとっては決してトレンドではないという前提で語らなきゃいけないなって思っています。
手塚 最近、特にそう思いますね。
嶋田 もちろん歴史として大事なものもあるとは思いますが……。僕、新劇の“新”ってなんだろうなと思うことがよくあって。
一同 そう!
嶋田 時代に合った“新”を取り入れていくのが新劇じゃないかなって思ったりしますね。
植田 そうですね。俳優養成に関わる以上、今後の演劇界が良くなるとか、もっといろいろな作品が出てくることに向けて注力したほうが良いんじゃないかとは思います。
小泉 僕が研究生だった頃、「ゆる体操」っていう授業があって、それは身体をリラックスさせる授業なんですけど、講師の方に「そこ、ゆるゆるしてない!」って怒られるんです。リラックスするための授業なのに逆に緊張してしまって(笑)。
一同 あははは!
小泉 そのころは理不尽だなあと思っていたし、カリキュラムを刷新したときにその授業はなくなったんですけど、俯瞰すると面白い授業だったな、あれはあれで良かったのかなと思ったりして……。
植田 それは難しい問題だよね。例えば文学座で今、小泉さんと同世代の劇団員に「自由に研究所のカリキュラムを変えてもいいよ」と言ったとしたら、自分たちがやりたいものや面白かった授業を残すと思うんだけど、一方で講師陣と話していて必ず話題になるのは、研究生が知らないものや経験したことがないことを経験させる重要性もあるということ。実際、そのときはよくわからなくても10年経つと驚くほどよくわかることもあると思うし、文学座で言えば20年前までは和物の授業が多かったんですけど最近は着物の授業が減っていることもあって、和物の現場に行ったとき、ある世代から和物の芝居ができる分量がまったく変わっているんですよね。和物ってある意味では型とか作法とかがあり、男尊女卑だったり身分の差があったりと理不尽な時代なものを扱っているから、経験していないとできない作品が出てきてしまう。嶋田さんのお話でいえば新劇の“新”って引き継いできたものの中にあって、それがないともはや“新劇人”ではなくなってしまうことがあるんじゃないかとも思ったりします。
手塚 円の場合は、“もはや新劇かどうか”という部分もあるかもしれません。そもそも何かを教わるとか引き継いでいくというより、それぞれに学んでいくという集団なので。
──確かに円・演劇研究所の公式サイトには「創立メンバー達が、『劇団という枠にとらわれず、役者自身がもっと自由にやりたいものを創れる場所』を求めて設立した団体です。わたしたちは劇団ではありません、演劇集団です。役者個々が組織によりかかることなく、自立した個々として作品に関わっていく……この考え方がわたしたち集団の原点です」と明確に書かれていますね。
植田 劇団によっては、劇団員が劇団に対してある意味依存しがちになるけれど、円はそういう感じがしないですよね。
手塚 劇団員それぞれが自覚を持って関わるようにしようという意識はありますね。
嶋田 研究生も劇団に近いところにいる感じがする。
手塚 所長が変わってからその傾向がさらに強いかもしれないです。研究生の要望があれば、時間が許す限りとことん付き合うという姿勢だし、だから卒業してからも公演や研究所の授業の見学に来る子もいます。
一同 へー!
植田 それは珍しいね!
手塚 スキルを教えることはしないけれど、観たいなら観てけっこうですよ、というオープンな感じはあって、そこで交流も生まれますね。
この機会に…それぞれに聞きたいこと
植田 改めて伺いたいんですけど、それぞれの研究所が一番重要だと考えている考え方は、どんなことですか?
手塚 円は“嘘をつかないでいる”ということを大事にテキストに臨むようにしています。相手をよく観察して、そこからどう影響を受けるかということが大事だと考えているので、例えば名前を言い合う鬼ごっこをウォーミングアップとして必ずやるようにしたりしてますね。
植田 シーンスタディのようにテキストに当たるのではなく、シアターゲーム的なことをされているんですか?
手塚 はい。週1回程度ですけど、1年間通してやります。
植田 文学座でもシアターゲーム的なことって入所した直後にはやるんですけどそのあとはテキスト中心なんです。でもテキストばっかりやっていると気詰まりになるところもあるから、年間通してシアターゲームをやるというのは、当たり前のようだけどいいのかもしれませんね。俳優座は?
小泉 俳優座は、シアターゲーム的な授業をすごく増やしたんですよね。ロシアでは研究生1年目はセリフをしゃべらせずに、シアターゲームとか身体的なトレーニングをずっとやるそうです。例えば左手をずっとプラプラさせている子がいたとして、それを注意して直すんじゃなくて、両手の指を1本ずつ開いては閉じて、開いては閉じてするという動きを練習させるんです。そうすると、意識しないでも指先に意識がいくようになり、手がプラプラしなくなるんですね。というような動きの訓練によって身体の癖を矯正していく。戯曲に取り組むのは、そのあとです。僕が研究生だったら耐え難かったかもしれませんが(笑)、その分、研究生たちの発表会での爆発力がすごくて!
一同 あははは!
植田 みんなしゃべりたいと思っているわけだから、それはそうだよね。文学座は逆に、徹底的にセリフの訓練をするので身体的な意識がちょっと薄くなりがちで。
手塚 いやでも、文学座の俳優さんは皆さん本当にセリフがうまくて……。
植田 セリフについては本当に徹底してやりますからね。
嶋田 青年座でも1年目の終了公演間近までセリフ以外の稽古に力を入れる、というやり方をしていた時期があるんですが、そうなると研究生があまりにセリフがしゃべれないという問題が起きたので、今は前期からセリフの授業もやるようになって。塩梅は難しいですね。力を入れている授業、という点では青年座は「発声」の授業をもう40年くらいやっています。ロングランにも対応できるような自然な声を見つけていくというもので、習得するまでに非常に時間がかかるのですが、この授業を目的にうちの研究所に入ってくる人も多いです。あと、僕が入ってからですが、脳科学とかスポーツ医学の考え方を取り入れるようになりましたね。例えばスポーツの世界が飛躍したのは、科学の理論を取り入れたことが大きく影響していると思うので、さっきの小泉さんの話に近いと思いますが、自分にはまだどの回路が備わっていないのかを、芝居を通してではなく科学の理論を通して学んでいく。それを今後、強みにしていけたらと思っています。
植田 それは面白いですね。精神論だけになるのは危険だし、でも理論や体系だけになってしまってもダメだし、研修期間も授業数も決まっている中で、何を学んでもらいたいか、よく考えていかなければと思います。
嶋田 ……と考え続けていると、「もう授業を全部やめて、1年間みんなで遊び続けるのもいいんじゃないか!」と思ってしまったりして!
一同 あははは!
手塚 確かに自分も演劇は楽しいものだと思って始めているから、みんながきゅっと萎縮してしまうことは避けたいなって。
植田 それに、演劇の現場や稽古場で不調になるときって、大概が生活の部分に関係あると思っていて。結局どういう生活をしているのか、どういう日常を過ごしているかが表現に出てしまうということがある。例えば研究生の場合は、恋愛の部分でモチベーションが上がったり下がったりすることもあるし、でもそれを禁止することも僕はおかしいと思うので、そういった研究生の気持ちの部分と表現とをどうリンクさせていくのか、どう生かしていくのかを考えてあげないといけないなって。
嶋田 確かに、研究生から相談されて「これは演劇の問題じゃないけど、これを解決しないと、多分この子の悩みは解決しないんだろうな……」って感じることとかはよくありますね。
植田 だから僕は、自分の授業では生活のことを話したりしてます。研究生のときってどういう芝居をしたいか以上に、俳優が普段何をしているのか、どういう生活をしているのか、気になると思うんです、だってそれを仕事にしていこうと考えているわけだから。俳優も演出家も、基本的には稽古場にいる間は「プライベートはありません、365日24時間演劇に捧げています」という感じの人が多いけれど(笑)、生活を考える時間も僕は大事だと思っていて。
嶋田 日常を演じますからね、私たちは。
植田 そうそう、生活している人を演じるわけなので。だから日常生活から得られるものも大きいんじゃないかと思っています。
求めるのは、劇団の垣根を超えて共に変化を楽しめる人材
手塚 僕は……新劇はこれから、どうなるんだろうなと思っていて。研究所が続いている間は後輩たちが入ってくるわけで、これから入ってくる人たちのことを思うと、新劇の未来はどうなるのかな、どこにつながっていくのかなということをよく考えます。
小泉 昔、仲代達矢さんのインタビューを読んで、仲代さんは俳優座の先輩で憧れる人はいなかったけれど、劇団民藝の滝沢修さんや宇野重吉さんに憧れていたとおっしゃっていて。そのように、自劇団に関わらず、他の劇団に憧れがいるっていうのもいいなって思ったんです。なので、劇団単位ではなく新劇というジャンル全体で活躍の場が広がれば、未来への希望が持てるんじゃないかなと思います。
手塚 僕もそのイメージは、思い描いたことが何度もありますね。
小泉 もちろんすでに新劇交流プロジェクト(編集注:文学座、文化座、民藝、青年座、東演といった長い歴史を持つ劇団がそれぞれの垣根を超えて舞台を創造することを目指すプロジェクト)などがありますが、各劇団が共存共栄するために、さらにシビアなフルキャストオーディションをするとか、もっと切磋琢磨し合えるような関係性を作れたら良いなと思ってます。
植田 劇団の歴史が長くなると劇団員の年齢の幅が広くなるし、今新劇の旗を振って劇団を牽引している人には六十代、七十代の人が多いと思うんだけど、新劇が本当に一番新しいものをどんどんやって攻めていた時代って、新劇の一番コアな世代は今の僕たちくらいの年齢だったと思うんですよね。という点で、新劇の“新”はそれをスタートした時代の人たちのエネルギーだし、先人の考えをただ守るんじゃなく、どう書き換えていくかが大事なんじゃないかなって。そのためにも研究所や養成機関で新しい考えを持った新しい人材を育てていくことが大事だし、そういう人たちがいずれ劇団に所属することで、劇団も変わっていくと思っています。
──秋になり、2024年度募集の詳細が、各劇団の公式サイトなどで発表されます。これから研究所の受験を考えている方々に向けて、メッセージをお願いします。
小泉 俳優座に入りたい人はもちろん大歓迎ですが、俳優座に関わらず演劇界を背負っていきたい、牽引していきたいと思う人に来ていただきたいなと思います。
嶋田 劇団や研究所、養成所もいっぱいあってカリキュラムもいっぱいあるので、ほかの劇団や専門学校を含めてとにかくいろいろ見て経験して、自分が良いと思ったところに足を踏み込んでほしいですね。そしてその1つとして、青年座研究所も考えてもらえたら。最初から青年座だけに絞らなくていいと思うし、今日のお話を聞いていても各劇団それぞれに、本当にうらやましいところがいっぱいありますから!
一同 あははは!
手塚 今日こうやって4劇団で集まれたことも象徴的ですが、円を卒業してほかの劇団で活躍している方もたくさんいますし、続けていればこうやってつながっていけるので、嶋田さんがおっしゃったようにいろいろな劇団を見ていただいてから円に入っていただくのももちろん良いと思うし、でもどこに行っても演劇の楽しさは学べると思うので、安心して選んでほしいなと思います。
植田 今日のお話を聞いて、各劇団がこの数年、本当に何かを変えなきゃいけないという強い思いがあって、どんどん新しいことを始めているんだなと実感しました。新しい力や価値観は新しい人材にしかないと思うし、どういう人が入ってくるかによって劇団は変わっていく。変革期の今が“ねらいどき”だと思うので(笑)、この状況を面白そうだなと感じてくれる新しい人材には、ぜひ来てもらいたいなと思います。
プロフィール
植田真介(ウエダシンスケ)
1982年、広島県生まれ。俳優、文学座附属演劇研究所主事。2000年に文学座附属演劇研究所に入所し、2005年に座員となる。現在は舞台を中心に多方面で活動。劇団公演の傍らプロデュース公演などにも出演。近年の主な出演作に「有頂天作家」、「T Crossroad 短編戯曲祭<花鳥風月>夏」、文学座「昭和虞美人草」など。
文学座附属演劇研究所 (@bungakuzakenkyujo) | Instagram
小泉将臣(コイズミマサオミ)
1986年、東京都生まれ。俳優。2013年に俳優座研究所に入所し、2018年に劇団員昇格。近年の主な出演作に劇団俳優座「猫、獅子になる」「ボタン穴から見た戦争」、新国立劇場「斬られの仙太」、名取事務所「ペーター・ストックマン~『人民の敵』より」など。「幽麗塔と私と乱歩の話」では演出も務めた。
小泉将臣 (@masaomi_koizumi) | Instagram
劇団俳優座演劇研究所 (@haiyuzakenkyujo) | X
嶋田翔平(シマダショウヘイ)
1982年、沖縄県生まれ。俳優、劇団青年座研究所事務局長、プレイングマネージャー。2007年に劇団青年座に入団。近年の主な出演作に劇団青年座「シェアの法則」、新劇交流プロジェクト「美しきものの伝説」など。10月13日から22日まで、劇団青年座「同盟通信」に出演。
嶋田翔平 shimashow* (@shoheishimada) | X
劇団青年座研究所 公式 (@seinenzastudent) | X
劇団青年座研究所 (@seinenza_theater_laboratory) | Instagram
手塚祐介(テヅカユウスケ)
1981年、奈良県生まれ。俳優。2001年に円・演劇研究所に入所、2003年に演劇集団 円会員に昇格。近年の主な出演作に演劇集団 円「河童の三平」「ぼくは人魚」「ヨーコさん」など。声優や吹き替えの仕事も多い。