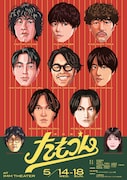演劇を学ぶには、どんな手段があるか? 手軽なところではワークショップやカルチャースクール、本格的に学ぶなら専門学校や大学を目指すのも良いだろう。そんな多彩な選択肢の1つとして、劇団の研究所に入るという手もある。例えばこの座談会の登壇者、植田真介は文学座、小泉将臣は劇団俳優座、嶋田翔平は劇団青年座、手塚祐介は演劇集団 円の劇団員で、それぞれ研究所を経て劇団に入団した。彼らが所属する4劇団は、明治末期、歌舞伎を中心とした“旧劇”に対する“新劇”として誕生し、文学座は1937年、俳優座は1944年、青年座は1954年、演劇集団 円は1975年に創設された。長い歴史を持つ4劇団にはそれぞれ俳優養成機関があり、各々の理念に基づいたカリキュラムで“未来の後輩”たちの育成にあたっている。
しかし時代と共に、求められる舞台作品や俳優にも変化が。本特集では、そんな変化の波を、自らも俳優としてダイレクトに受け止めつつ、研究所担当として日々研究生たちと向き合っている文学座附属演劇研究所主事・植田の呼びかけで、同じ立場にある他3劇団の面々が集結。研究所の今、そして未来を語る座談会を行った。
取材・文 / 熊井玲撮影 / 川野結李歌
劇団との出会い、そして研究所の担当として
──まずはなぜ現在の劇団に入団されたのか、また研究所に関わられるようになったのがいつからか、教えてください。
手塚祐介 僕は円の研究所の前に別の演劇の学校に通っていました。そこに特別講師として、円の仲谷昇さんと岸田今日子さんがいらして、今日子さんが詩の朗読の授業をしてくれたんです。その朗読が魅力的だなと思って、今日子さんに惹かれて円を受け、2001年に円・演劇研究所に入所、2003年に円の会員になりました。研究所にかかわるようになったのは、渡辺穣さんが研究所の主任になった5年前くらいからです。
嶋田翔平 僕も青年座の研究所に入る前に声優学校とミュージカルの専門学校に行っていまして、ミュージカルの専門学校のときに、声楽の先生だった方が青年座の研究所でも教えていたんです。その方に、「芝居がやりたいなら青年座に行くと良いのでは」と言われて、いろいろ探すというよりも恩師に従って青年座の研究所を受けたという感じです。青年座には2007年に入団し、研究所の担当は、コロナの初年からなので3年目です。
小泉将臣 僕はまず日本映画学校(現・日本映画大学)の俳優コースに入り、いろいろな監督から2年間指導を受けたのですが、卒業前に講師から「お前たちは新劇の俳優には勝てない。あいつらは歩くのに3年かけている」と言われて、2年間勉強させてもらっても新劇の俳優に勝てないと言われたのが心に残りまして。それと高倉健さんが好きなのですが(笑)、高倉健さんも東映ニューフェイスとして東映に入社した後、俳優座養成所に入って半年間修行したというエピソードを聞いて、俳優座を受けてみようかなと。ちなみに受験するまで俳優座の舞台を観たことはなくて、受験会場に行ったら思ったより受験者が多くてびっくりしました(笑)。
一同 あははは!
小泉 俳優座に入団したのは2013年で、研究所に関わるようになったのは、2年前くらいに演出家の眞鍋卓嗣が研究所の所長に就任して研究所を一新しようということになったとき、準備会のメンバーに選ばれて、それからです。
植田真介 僕はもともと子役をやっていました。高校生1年生のときに出た舞台の演出助手が文学座の演出家で、その方から「舞台が好きなんだったら文学座とかがいいんじゃない?」と言われたことが心に残って、高校卒業のときに文学座附属演劇研究所を受けて今に至る、という感じです。2005年に文学座の座員になり、研究所に関わり始めたのは2010年。少子化の影響でどうしても受験者数が下がってきたことと、劇団の中でWebを活用した宣伝をやるチームができて、そのリーダーとしてTwitterやFacebookをやるようになったんです。そのときに、研究所こそ若い人たちが対象になるからWebを使ったほうが良いんじゃないかということで、研究所の宣伝方法を一新することになり、そこからだんだんと生徒との関わりが増え始めて、2018年に主事になりました。
時代と共に変化する理念やカリキュラム
──募集要項や公式サイトを見ると、研修期間やカリキュラム、対象年齢や理念など違いがありますが、それぞれの研究所の特徴について教えてください。
植田 文学座は1961年の創立以来、本科1年、研修科2年というシステムは基本的にほぼ変わっておらず、カリキュラム自体もそんなに大きくは変わっていないと思います。
嶋田 青年座も、各講師の方に得意なものを教えていただく感じでずっと続けてきました。ただ、劇団に入ったあとに習ったことがつながっていないということを身をもって感じたので、僕の授業では今、各授業をつなぐような実習をやっています。俳優座は、だいぶ変えたんですよね?
小泉 そうですね。2年前に日舞以外は、講師の方々もカリキュラムもガラッと変わりました。一番の原因は、やっぱり俳優座も受験者数が減ってきたということがあり、俳優座に入りたい人だけを対象にしていてはいけないなと。あと所長の眞鍋さんが他劇団や他団体の人たちから助けられてきたという思いがあって、俳優座だけじゃなく演劇界に貢献するような人材を育てたいという理念があり、それによって刷新したんです。その柱になったのが、講師の1人であり、カリキュラムアドバイザーに入っていただいた横尾圭亮さんです。横尾さんはロシアで演劇を学ばれていて(編集注:横尾はロシアのライキン高等舞台芸術大学俳優学科卒業後、ロシア国立シェープキン演劇大学大学院首席、終了時に優秀者ディプロマを取得した)、ロシアの演劇教育には体系があり、それらを取得していった人が俳優になれるという明確な方法論があるんです。俳優座研究所ではその考えに則ってカリキュラムを編み直しました。
植田 とすると、もともとあった俳優座研究所の理念はどうなったんですか?
小泉 理念……あまりはっきりなかったと思うんですよね。少なくとも僕が研究所にいた頃は講師それぞれだったというか。例えばロシアでは、「1.相手役との交流、2.小道具や大道具との交流、3.観客との交流」というようなステップがあり、相手役と交流するために演技術の授業があり、物との交流についてはステージムーブメント的な肉体的動作、観客との交流のためには声が通らないといけないからボイスの授業という感じで目的ごとに授業を確立していきます。もともとの俳優座研究所のカリキュラムにもそれぞれそういった授業はありましたが、体系としてつながってはいなかったと思います。なので今は、横尾さんと眞鍋所長のもと講師間の連携を取るようにしています。ただロシアの考え方をすべての講師の方が全部理解しているわけではないので、まだ発展途上という感じではあるなと。あと、劇団に入りたい子たち以外も対象にしたことで、これまでと少し研究所の雰囲気が変わってきたところはありますね。
植田 それはあるでしょうね。研究生1年目ってそもそもプロになることを考えていない子もいて、文学座だと現役のお医者さんや社会人の方がこれからの社会活動に対するスキルアップとか、コミュニケーションを学ぶために来ましたと面接ではっきり言う人もいて。目的がそれぞれだと大変なところもある。でもいろいろな人がいたほうが楽しそうには見えるけれどね。
手塚 円ももともとは舞踊や日舞、ダンス、声楽、あとミーム……ってありましたか?(笑) そういった授業があったんですが、5年前に新しい所長になって、それらの授業を一新し、生徒たちが望むもの、豊かな研究所生活を過ごすにはどうしたら良いかということを考えて新しいカリキュラムにしました。今、円・演劇研究所の養成期間は1年なんですが、まずは1年間お芝居に触れてもらって、そこで面白いと感じたらもう1年続けてもらい、さらに入りたい意欲がある人に残っていただく、という考えでやっています。円では、技術を教える1年ではなくて、例えばお芝居自体が嘘だから、セリフや身体は正直にいるという姿勢をまずは教えています。またその姿勢を、これから生きていく中でも考え続けてくださいと伝えています。
植田 1年で養成を終えるって、劇団の研究所としてはかなり衝撃的な短さですよね。
手塚 そうですね。以前はほか3劇団のように2年とか3年、養成期間をとっていたのですが、9年前にアトリエが浅草から三鷹に引っ越して場所が取れなくなったこともあり、1年でやってみることにしました。
小泉 劇団の中で反対する人はいなかったんですか?
手塚 もちろんいろいろ意見はありましたが、仕方ない部分もあって。ただやっぱりもう1年間研究生を見てみたいという声が増えてきたので、2年になるかもしれません。
小泉 実は俳優座も2024年度募集から、3年だったのを2年に変えたんです。
嶋田 青年座も稽古場の建て替え問題があり、2024年度は2年次のみの募集に変更になりました。円さんは1年に変えたことで研究生たちの変化はありましたか?
手塚 現在は研究生1年目の人と2年目の人が研究所の中で混ざっているんですけど、いい方向に働いていると思いますね。2年目の子も1年目と同じことをやっているんですけど、1年目にわからなかったことがわかるようになって自分の成長過程が見られるというか。
嶋田 同じカリキュラムをやるというのは、発見があってよさそうですね。
植田 文学座は養成期間は3年ですが、本科から研究科に上がるときに4分の1くらいに人数が絞られます。シビアかもしれませんがやっぱりこの世界は誰もがなれるわけでもないし、本当に大変なのは入団して俳優として活動していくとき。やっぱり自分で主張して勝ち取っていかないといけないということで、研究生の間にある程度そういう環境でありたいということは常々考えています。競争はあるし、主張しなければ埋もれていってしまうということを実感してもらうというか。なので本科の1年は、1年間の壮大なワークショップをやっているような感覚があります。誰が残るかというのは劇団の都合も本人の希望もあるので、授業や発表会を通して、お互いに今後について判断していく。そういう点では、円と文学座は近いと思うんですよね。
手塚 そうですね。円も例え研究生であってもすぐに現場に行くつもりでやらないと時間がもったいないから、アピールしてほしいということは常々言っています。そこは一緒かもしれないですね。
植田 文学座は研修科に進級するとマネージメントの対象になるので、外の現場に行くことも出てくるのですが、外の現場に行くことを一番の目的にし始める子もいて、でも、研修科の2年を終えるときには劇団に所属できるかどうかの査定があるので、発表会でちゃんと実力を見せてくれないと困る。それに全員が仕事をもらえるわけでもないので現実を知るというか、考え方が変わってくるということはありますね。
嶋田 青年座は、昔は研究生も外の現場を踏んでいたようですが、基本的に外部出演は出来ない状態でした。昨年からは稽古に被らなければ自分で見つけてきた仕事は行えるようになり、経験した生徒を見るとやっぱり外の考え方にも影響を受けているなという感じがします。また青年座は本科1年、実習科1年の計2年ですが、経験者であれば実習科から入ることができるんです。いつからそのシステムがスタートしたのか僕はわからないのですが、2年目に外の風を入れて刺激を与えようと考えた人がいたのではと思います。なので皆さんの研究所からも来てくださる方がいるのですが(笑)。
一同 あははは!
植田 でも僕らも劇団公演と外のプロデュース公演では心境の違いみたいなことがあるじゃないですか。そういった意味で、よその劇団のことを知れるということはプラスになりますよね。
次のページ »
答えを教えるのではなく、答えを一緒に探す関係に