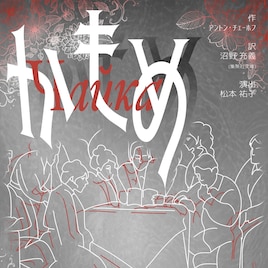樹木希林や黒柳徹子など、そうそうたる面々が卒業生として名を連ねる文学座附属演劇研究所。“理論と実践”を軸に、演劇界の第一線で活躍する講師陣による授業が週6で行われ、生徒は仲間たちと共に切磋琢磨し、研修科への進級を目指す。“名門”と誉れ高い文学座附属演劇研究所だが、どのような理念に基づいて運営されているのだろうか? 所長の坂口芳貞と主事を務める植田真介が、まもなく60周年を迎える研究所のこれまでとこれからについて語った。また特集の後半では、本科の授業レポートや現役生の声を紹介する。
[坂口芳貞×植田真介 対談]取材・文 / 興野汐里 撮影 / 櫻井美穂
[授業レポート]取材・文・撮影 / 櫻井美穂、興野汐里
文学座附属演劇研究所の生徒にとって、最も身近な存在である所長・坂口芳貞と主事・植田真介が、ざっくばらんにトーク。“Web説明会”をテーマにした今回の対談では、「文学座附属演劇研究所ってどんなところ?」という質問に、2人が“ぶっちゃけ話”を交えながら答えていく。
こんなに発表会をやっているところはない
──坂口さんは、戌井市郎さんの跡を継いで2011年に文学座附属演劇研究所の所長に就任されました。研究所には、いつ頃、どのようなきっかけで携わることになったのでしょうか?
坂口芳貞 文学座創立メンバーの三津田健さんに「研究所に関わってくれないか」と言われたのが、桃井かおりや松田優作がいたときだから、11期から12期にかけてくらいかな。その頃に代用教員のような形で入って、だんだん自分のやりたいことをやらせてもらえるようになって、27期からは宮本研さんの「俳優についての逆説」を使った授業を継続してやっています。来年が60期だから……そう考えると、もうだいぶ長くなるな(笑)。
植田真介 坂口さんは3期ですから、代用教員になったのは座員になってからそんなに経たない頃ですよね?
坂口 うん、そのあたり。
──植田さんは高橋正徳さんたちがいらっしゃる40期のメンバーですが、どのような経緯で主事を務めることになったのでしょう?
植田 僕の場合、いくつか段階があって(笑)。2010年に文学座附属演劇研究所開設50周年の大同窓会があったんですが、その実行委員として関わったのが最初です。その頃、ちょうど研究所の受験者数が減ってきた時期で、「Webを使って宣伝してみたらどうか」と当時の主事に提案して、Twitterやブログを使って研究所の情報を外に発信するようにしたんです。なので最初は広報的な立場で関わってました。それで53期あたりからは生徒との関わりが深くなってきて、55期で主事補佐に、昨年の58期のとき主事に就任しました。
──受験者数が減少したというお話がありましたが、生徒数を増やすにあたって、どんな取り組みをされているのでしょうか?
植田 元々、文学座の研究所って「こういうことをやっています」って積極的に情報を出すことがあまりなかったと思うんです。でも今の時代ってやっぱり、どんなカリキュラムがあるのか、研究生はどんな1年間を送っているか、そういったことがわからないと不安に感じる子が多い気がして。こちらが取り組んでいることや求めているものをつまびらかにして、それに魅力を感じてもらえたらと思っているので、バンバン情報を出していくようにしていますね。
坂口 あと、うちはなるべく授業料を上げない方針でなんとか踏ん張ってる。
植田 そうですね。週6日授業があって、年に4回発表会をやるとなると、今設定している年間53万円っていう金額がギリギリ。とにかくうちは、いろいろな劇作家の書いたテキストと格闘して、いろいろな演出家や俳優と出会うことを大事にしているのと、人に観てもらえる機会が多いのが強みだと思います。
坂口 そこは圧倒的だよね。こんなに発表会をやってるところはないもの(笑)。
──研究所の発表会では、文学座の財産演目である「女の一生」や、ソーントン・ワイルダー作「わが町」などが多く上演されているイメージがあります。演目は、どういった流れで決定されるのかについて教えてください。
植田 「わが町」と「女の一生」は毎年必ず本科で行います。卒業発表会に関しては、担当する演出家を中心に、「今年はどういう子たちがいるかな」ということを考えながら配役についても決めていく感じですね。研究所の1年間のカリキュラムに関しては、「この講師の授業をこの時期にやったほうがいいだろう」ということを考慮しつつ、講師の皆さんにスケジュールを伺って予定を組みます。前年と違うことをする場合は、事前に「昨年、この時期にこれをやったと思うんですが、来年はこの時期にこれをやったらどうでしょう?」と相談しますね。
坂口 真介くんはそのへんの調整がすごく優秀だから(笑)。
植田 ははは、ありがとうございます(笑)。
好きな授業は人によってバラバラ
──狭き門ゆえに、文学座附属演劇研究所は“演劇界の東大”と形容されることがありますが、中には未経験で入所される方もいらっしゃるのでしょうか。
植田 まったくの未経験者もいるし、部活やサークルでの経験はあるという程度の方もいます。経験者でないと文学座は受からないと思われがちですが、必ずしもそうではないということだけは言っておきたいですね。未経験者でも光るものを持った人はたくさんいます。でも、未経験者だけでクラス編成をするのは違うかなという気がしていて。経験の違いや年齢の差があってこそ、文学座附属演劇研究所は成り立っているのだと思います。
──現在の59期でいうと、大学を卒業して入所した方が多いんですね。
植田 今年は22歳がすごく多いですね。傾向として、数年前は大学卒の年代がスポッと抜けている時期があったんですが、ここ最近は大学卒の子や18歳で入ってくる子、大学で勉強しながら通う生徒が年々増えてきている気がします。特に夜間部には、ダブルスクールしている子がけっこういますね。大学1・2年生もいますが、やはり3・4年が多いです。あとは働きながら通っている生徒もいて、そういう子たちは夜間部が始まる18:00にギリギリに着いて授業を受けています。
坂口 そういう子たちは本当に熱心。ギリギリまで仕事をして、授業もがんばって。
──今回の対談では、説明会等であまり触れない部分のお話も伺えたらと思っています。生徒さんの多くは、やはりアルバイトをしながら研究所に通っていらっしゃるのでしょうか。
植田 ほとんどの人がしていると思います。昼間部の場合は夕方から夜にかけて、夜間部の場合は朝から昼過ぎまで働いている子が多いようです。
坂口 16:00に昼間部と夜間部の入れ替えがあって、夜間部は16:00から18:00まで稽古場を自由に使っていいことになってるんだけど、バイトのあと16:00に稽古場に来て、カーテンの陰で寝て、17:00頃からウォーミングアップを始める、みたいな子がけっこういる。熱量がある人が多い期はやっぱり面白いよね。
──坂口さんは長きにわたって研究所で教鞭を執ってこられました。その中で生徒さんたちの“熱量”の変遷を感じることはありますか?
坂口 年代によって考えていることがずいぶん違うなと思う。自分が担当している授業では毎年、夏休みの宿題として3分間の一人芝居を作ってきてもらってきていて。自分の経験を書いてもいいし、好きな戯曲から抜粋して自分なりに変形して書いてもいいっていうふうにしてるんです。もうだいぶ前だけど、全体のうちの3分の2くらいの生徒が自殺や死をテーマにした年が2年くらい続いて、それぞれの生き方に根ざした作品作りを目の当たりにした、というのかな。あのときはすごく面白かったね。最近は比較的健康的な題材が多い印象だけど、今の子たちも抜群に面白いものを書いてくるんですよ。「これ、このまま作品にできちゃうんじゃないの?」っていうような。
植田 そこで書いた一人芝居を、夏休み明けに稽古場発表会で披露するんですよ。衣装も小道具も何もない状態で、みんなが囲む円の中で1人で演じるっていう。
──演技部だけでなく、演出部や制作部の方々も……?
坂口・植田 もちろん(笑)。
──生徒さんたちにとって充実した夏休みになりそうな課題ですね。坂口さんの授業も大変魅力的ですが、生徒さんから反応のよい授業、というものはあるのでしょうか?
植田 これは文学座のいいところで、おそらく人によってバラバラになると思います。寺田路恵さんの朗読が好きな人もいれば、鵜澤秀行さんのこだわり抜いた授業が好きな人もいるし、小林勝也さんの自由な授業が好きな人もいる。授業の内容というよりも、どの講師の言葉が自分に一番フィットするかが重要なんじゃないかと思っていて。
坂口 そうだね。研究所で教えている座員はみんな「生徒たちにとって一番いいことをやろう」という思いで真剣に向き合っているし、「やりたいことがあったら言って」と生徒たちにきちんと伝えている。実現できるかは別としてね(笑)。そういうことを許さないのは一番面白くないと思うから。
植田 運営側がすべて決めるのはつまらないことだし、やりたいことをやりたいと言える環境を作ってあげたいなと僕も思っています。
坂口 中には、その気持ちをなかなか表に出せない子がいる。だけど活発な期だと、思いを口に出せずにドロップアウトしそうになる子を、なんとかすくい上げようとする子たちが出てくるんだよね。
植田 みんなそれぞれ強い気持ちを持って入ってくると思うんですけど、入所して実際に週6日の授業、年4回の発表会をやっていく中で、「やりたい」という気持ちだけでは続けられなくて、途中で離脱する人はやっぱり毎年出てきてしまいます。
坂口 でも、ほかの養成所と比べたらドロップアウトする人は少ないんじゃないかな。
植田 僕もそう思います。あと、休みがちな状態から復帰後に見事に生まれ変わる子ってたまにいますよね。何かを捨てたのか割り切ったのかわからないんですけど、ものすごく面白くなって帰ってくるみたいな。
坂口 ドロップアウトしかけた子が、のちに劇団の戦力になってるケースはけっこうある。自意識過剰だったり他人が怖かったり、そういう感覚って「演劇をやりたい」とか「こういうものを作りたい」っていう創作意欲の源泉みたいなものだったりするから、大事にしなくちゃいけない。そういうセンス持った子が苦難を乗り越えると、やっぱりほかの人とは違うふうに化けるからね。そこがまた素敵だなって思うんだよ。
次のページ »
一番カッコいい研究所の卒業の仕方は……
- 文学座附属演劇研究所
-
1961年、文学座の創立25周年の記念事業の1つとしてスタートした文学座附属演劇研究所。授業では文学座座員たちによる演技実習をはじめ、各専門家を招いての音楽、体操、ダンス、アクション、能楽、作法のレッスンや、演劇史を学ぶ座学もあり、広く舞台で活動していくための基礎教養を学ぶことができる。なお、研究所は本科と研修科に分かれており、本科の卒業公演後、選抜されたメンバーのみが研修科に進級する。
関連特集
- 坂口芳貞(サカグチヨシサダ)
- 1963年に文学座附属演劇研究所へ入所し、1967年に座員となる。近年の出演作に、Ring-Bong「逢坂~めぐりのめあて~」(演出:藤井ごう)、文学座5月アトリエの会「青べか物語」(演出:所奏)、Pカンパニー「別役実の男と女の二人芝居 日替3本立て」(演出:山下悟)があるほか、文学座附属演劇研究所「阿Q外傳」(演出:鵜澤秀行)に特別出演している。吹替えではモーガン・フリーマンやショーン・コネリーの声を担当。2019年7月に行われた研究所本科昼間部、夜間部の「わが町」では演出を務めた。
- 植田真介(ウエダシンスケ)
- 2000年に文学座附属演劇研究所へ入所し、2005年に座員となる。近年は、ティーファクトリー「エフェメラル・エレメンツ」(演出:川村毅)、「クイーン・エリザベス -輝ける王冠と秘められし愛-」(演出:宮田慶子)などに出演。10月には、ティーファクトリー「ノート」(演出:川村毅)の公演を控えている。