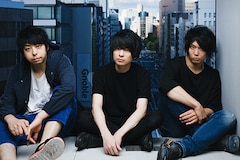2019年10月に12thアルバム「カルぺ・ディエム」を発売したTHE BACK HORN。そこからの2年半は、彼らにとって決して楽なものではなかった。アルバムを携えてスタートさせたツアーは山田将司(Vo)の声帯ポリープ発症を受けて中止に。その後、振替公演を予定するも新型コロナウイルスの影響で開催を断念せざるを得なくなり、ほかのアーティストと同じくライブを行えない日々が続いた。そんな中でも彼らは2020年6月に配信シングル「瑠璃色のキャンバス」を発表し、8、9月にはバンド初の無観客配信ライブを行うなど精力的に活動してきた。
手探りの活動が続く中、THE BACK HORNは2021年に「カルぺ・ディエム」ツアーの再振替公演を含む3本のツアーを実施し、同年12月には4年5カ月ぶりとなるCDシングル「希望を鳴らせ」を発売。そしてこの度ニューアルバム「アントロギア」を完成させた。音楽ナタリーでは、「カルぺ・ディエム」以降の歩みを振り返ってもらいつつ、新型コロナウイルスの影響を色濃く映しながらもポジティブなムードがあふれる「アントロギア」についてじっくりと話を聞いた。
取材・文 / 丸澤嘉明撮影 / 山崎玲士
コロナ禍で抱えていたそれぞれの思い
──音楽ナタリーに4人が登場するのはアルバム「カルペ・ディエム」以来となります(参照:THE BACK HORN「カルぺ・ディエム」インタビュー)。この2年半の活動を振り返っていければと思うのですが、2019年11月に「『KYO-MEIワンマンツアー』カルペ・ディエム~今を掴め~」が始まったあと、山田さんの声帯ポリープ発症を受けてツアーが中断されました。その後、2020年5月にツアーの振替公演をやろうとしたら今度は新型コロナウイルスの影響で中止せざるを得ない状況となって。バンドとしてしんどい時期を過ごしてきたと思うのですが、当時のことを改めて振り返ってみていかがでしょうか?
松田晋二(Dr) 2018年から2019年にかけて結成20周年のアニバーサリーイヤーでさまざまな活動をしてきた中で、「カルぺ・ディエム」ツアーで俺たちはまたここから先に進んでいくぞという思いをファンの皆さんと共有しようとしていたんですけど、それを中断する形になってしまって。もちろん残念な思いはありましたが、強引に突き進むのではなく一度しっかりと時間を取り、そしていつか完走するぞという気持ちはありましたね。
山田将司(Vo) まあ悔しかったですね。今までは喉の調子が悪くてもなんとしてでも歌ってきたんですけど、さすがにライブ中に一切声が出なくなってしまったので、泣く泣くツアーの中止を決断しました。今までのボーカルスタイルがあったから喉を痛めつけてしまった結果でもあるし、でもそれがあったからこそいろんな人との関係を築けてきた部分もあるので、なかなかすぐにはスタイルを変えられないというか、割り切れなくて。そういう意味で、コロナ禍になったことで冷静に考えて気持ちをリセットする時間を与えられた気はしましたね。
菅波栄純(G) 自分も緊急事態宣言が出されて外出自粛になったときは「俺は音楽で何を一番やりたいのか」を改めて考える期間になりました。それで自分は曲を作ること自体が一番の喜びなんだと気付いたんですけど、コロナ禍で思うように活動ができないバンドの状況や将司の喉の具合を想像して、これからどうなっていくのか一抹の不安は正直あって。ファンに対して何も表現できない時期が続くのかなと思っていたら将司から「瑠璃色のキャンバス」を発表したいという提案があって、それが自分の中ではターニングポイントになりました。俺は自分からメンバーに「何か行動を起こそう」とは言えなかったんですけど、将司から言ってもらえたことで音楽家として使命を与えてもらった気がして。「瑠璃色のキャンバス」のギターアレンジを考えているときに「音楽っていいな」と噛み締めていた記憶がありますね。
岡峰光舟(B) 自分も栄純と近い感覚があって、山田の喉の不調とコロナでツアーが中断されてから、山田が「新曲を届けたい」と言うまではあまり物事を考えないようにしていました。むしろ音楽以外で趣味とかに時間を使うしかないかなと思っていたくらいで、俺も自分からは「曲を出そうぜ」とは言えなかったんですよね。体調面はもちろん、精神的にも山田がしんどいのはわかっていたので、無理に発破をかけたくなかったというか。そこで山田から「音楽を届けたい」と言ってきたのがすごく意味のあることで、バンドとして一歩を踏み出せたと思います。2020年の5月あたりから意思を持って動き出した感覚はありましたね。
楽な道ではなくやりがいのある道を選びたい
──2020年6月に配信リリースされた「瑠璃色のキャンバス」は、コロナ禍で不安を抱えているリスナーに向けたTHE BACK HORNからのメッセージというだけでなく、バンドにとっても非常に重要だったんですね。山田さんはどういう思いでこの曲の制作に取りかかったのでしょうか?
山田 2020年の年始にツアーを中断して、気が付いたらコロナの影響で世の中のステージから音楽が止まっている状況があって。お客さんが今どういう気持ちでいるのかを想像したり、お世話になってきたライブハウスのことを1つひとつ思い浮かべたりしたんですよね。それで、今はお客さんとライブハウスで会えないけど、またあの場所で一緒に歌おうという気持ちで書きました。それと、自分が死ぬ直前にどんな人生だったら満足するかなということも考えて、楽な道ではなくやりがいのあるほうを選んで、とことんやり切ったと思える人生にしたいという気持ちになって。自分が止めてしまったTHE BACK HORNの活動だったから、自分がきっかけを作らないといけないと思っていたし、バンドのために曲を作りたいという気持ちもありました。
──「瑠璃色のキャンバス」をリリースしたあと、8、9月にそれぞれスタジオとライブハウスから配信ライブを行いました。「カルぺ・ディエム」ツアーが中断されて以降バンドとして初めてのライブで、しかも慣れない無観客生配信という形でしたが、やってみていかがでしたか?
山田 目の前にお客さんはいなかったけど、胸が熱くなりましたね。
松田 しかも8月に行ったスタジオ編は、立ち位置が向かい合ってやる形だったのですが、今まであまりあの形でやることがなくて。自分はいつもメンバーの背中しか見えてなくて、メンバーもドラムの音を背中で感じながら客席に向かって演奏しているけど、それぞれのプレイを見ながらできたのは新鮮であり、思いを共有している感覚はありましたね。
山田 配信ライブ自体も初めてだったかな?
岡峰 配信だけというのは初めてだったよね。おそらく俺らって、ライブハウスでお客さんと対峙して、そこで生まれるグルーヴがTHE BACK HORNらしさというイメージを持たれていると思うんです。でも配信ライブをやった実感としては、無観客だったけどお客さんを感じられて。リハーサルとはまったく別物で、あれは確実にライブだったんですよね。こういう形がTHE BACK HORNでもありえるんだと気付けたのはいい経験でしたね。
山田 スタジオでやった1回目はもちろん、ライブハウスでやった2回目は、会場にクルーしかいなかったけどそのカメラの向こうでお客さんが観てくれていることがより想像できましたね。ちょっとカメラに向かって歌いすぎたかもしれないですけど(笑)(参照:ライブハウスに帰ってきたTHE BACK HORN、魂の叫びを響かせた熱狂の一夜)。
震災後に完成した「リヴスコール」を今振り返る
──2021年に入り、1~4月に「カルぺ・ディエム」ツアーの再振替公演、5~6月に「『KYO-MEIストリングスツアー』feat. リヴスコール」、そして10~12月に「マニアックヘブンツアーVol.14」と、実に3本のツアーを行いました。
松田 次から次へとツアーしてましたね(笑)。
岡峰 それぞれコンセプトが違ったから余計濃く感じるよね。
山田 いろんな曲をプレイした年だったな。
──ストリングスツアーをやるきっかけはなんだったんでしょう?
松田 もともと会場のスケジュールなどの関係で早い段階で準備しないといけなくて、「2021年にひさしぶりにストリングスツアーをできたらいいね」という話はしていたんです。コロナがどういう状況になっているか未知数ではあったんですけど、実際に公演日が近付いてきて、自分たちが望むならばやれるという状況だったのでそのまま決行することにしました。
岡峰 2012年にリリースした「リヴスコール」の曲を演奏しようと決めたのは2021年に入ってからですね。去年は東日本大震災から10年というタイミングでもあったし、震災を経て完成した「リヴスコール」を、コロナ禍の今やったらどういうふうに鳴らせるんだろうという思いもあって。
──まさに震災直後の社会的な激動期と今回のコロナ禍の社会状況で重なる部分もあると思うのですが、ストリングスツアーを通して「リヴスコール」と改めて向き合ってみて、このアルバムにどういう印象持ちました?
菅波 自分は今回の「アントロギア」を作り終えた段階でなんとなく比較して思ったことで、ツアー中は特に意識してなかったんですけど、「リヴスコール」は混沌とした部分がより刻み込まれている気がしました。決して前向きだけではない、ドキュメンタリー要素が強いアルバムという印象ですね。
松田 4人それぞれの思いが、楽曲しかり歌詞しかり細かいアレンジしかり、ものすごい密度で詰まったアルバムだなと思いましたね。アルバムを聴いたみんなが楽曲に心を重ね合わせる余白みたいなものよりも、「俺たちの思いを聴いてくれ」という側面が強く出ていたなと。それくらい1つの音だったり言葉だったりに思いを込めていたんだと感じました。
──ストリングスツアーではバラードはもちろん、「ジョーカー」のようなダークな曲にもがっつりとストリングスが入っていて、楽曲の新しい形を提示していましたね。
山田 2016年にストリングスを入れてライブしたときも、「悪人」や「ブラックホールバースデイ」、インディーズ時代の「カラス」に同じように入れていたんですよね(参照:THE BACK HORN、優しさと激しさの両面で惹き付けたストリングスツアー終幕)。THE BACK HORNのドロドロした曲にストリングスが絡むことによって、さらにその混沌さが増幅されるというか、血が通う感じがしていいなと思っていたので、今回もそうしましたね。
岡峰 今回のストリングスツアーは自分たちと銘苅(麻野)さんをはじめとするストリングスチームとの結束力が回を重ねるごとに更新されていって、それがサウンドにも表れる感じがしてよかったですね。音の深みが増していったと思います。
次のページ »
THE BACK HORN流ダンスナンバー「ユートピア」