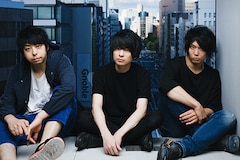クライマックスのあとが好き
──住野さんは今回初めての恋愛長編に挑戦してみていかがでした?
住野 前に栄純さんが「一番読みたいのはすごく盛り上がってイチャついたそのあとだよね」と言っていたことがあって、僕もそうなんですよ。今回も、クライマックスのあとにほんわかしてるカヤたちを描いてるシーンがあって、カヤが水を吹き出しちゃうところとかすごく好きなんですよね。こういうシーンのためにまた恋愛小説を書くのもいいなと思いました。
菅波 そのシーンすごくいいですよ。まだ読んでない読者の皆さんに先に言っておきます(笑)。俺はもちろん住野さんの作品は全部読ませてもらってますけど、この小説が一番好きですね。この作品に関わらせてもらったとか、ラブコメ好きな俺のニーズに合致してるという理由もあるんですけど、住野さんの描くキャラクターって、煮込みまくったカレーのようにすごく複雑な旨味があるんですよね。主人公のカヤは「こいつ腹立つな」と思うときもあれば「めっちゃ好きだな」と思うときもあって、でも人間ってそんなものだなとも思うし。
──この作品は恋愛小説ですが、ヒューマンドラマでもありますよね。
菅波 そうですよね。恋愛というのはフックの1つで、本筋は住野節が炸裂した人生の話だと思います。人間臭いキャラクターが住野さんの作品の魅力だし、THE BACK HORNでも俺はそういう人の曲を書きたいと思っていて。だからTHE BACK HORNのことが好きで、もしまだ住野さんの作品を読んだことがない人がいたらぜひ読んでほしいです。
また人を傷付けるところだった
──主人公のカヤは、異世界に住む爪と目しか見えない少女・チカとコミュニケーションを図ってお互いの理解を深めようとするわけですが、その関係はまさに小説と音楽という異なるバックグラウンドを持つ住野さんとTHE BACK HORNの関係と重なりますよね。
住野 カヤがやがて少女に向ける感情は僕がTHE BACK HORNに向ける気持ちと極めて似ています。カヤにとってのバス停が僕にとってのライブハウスで、姿が全部見えるわけじゃないけど、自分を変えてくれるかもしれない相手というのが僕にとってのTHE BACK HORNであり、これまで出会ったほかのバンドの皆さんなので。それに加えて、カヤと少女の関係には輪廻の考えもあって、いずれカヤが少女を思うように、僕の読者さんが僕のことを思ってくれることがあるかもしれないし、その読者さんのことをほかの誰かが思うこともあるかもしれないし。そういうことを描けていたらいいなと思います。
菅波 なおかつ、住野さんはおおっぴらに言うのは好きじゃないかもしれないけど、この作品には社会的なコミュニケーションの問題に関しても大事なメッセージが込められていると思います。異なる考えを持った人たちがどうコミュニケーションを取って一緒に生きていくべきか、これまでちゃんと向き合ってこなかったから、今悲しい事件が起きてるわけで。俺らTHE BACK HORNもそういう曲を作らなきゃいけないと思っているところですね。
住野 どこまで直接的に言うべきかは常に考えますね。たとえ対立したとしてもその先でわかり合える世の中だったらいいと思うんですけど、それが分断されがちなので、小説で書く距離感も難しくなってくる。あまり直接的に物語上で登場人物に社会的な意見を言わせると、ある一定の主張をするための小説と思われるんじゃないかという危惧があって、その線引きはすごく迷います。
菅波 それは俺もすごく思う。俺は日々の暮らしの中で異常に腹が立つときがあるんだよね。優しい人ほど地獄を見たりするので。そういうのを目の当たりにしたときに曲にしようと思うんだけど、一方でただそれだけを言う曲は書くべきじゃないと思う自分がいて。しっかり噛み砕いて作品として昇華させないといけない。だから怒りに任せて書いた曲はけっこうボツにしてる。
住野 そういう選定があって「心臓が止まるまでは」みたいな曲が生まれるわけですね。
菅波 「あいつ死ね」って書きたいけど、20年プロとして生きてきた俺の筆が「罵詈雑言土鍋で 三、四日ほど煮込んで」という歌詞に昇華してくれて、(左手で右手を押さえながら)「あぶなかった……! また人を傷付けるところだった」みたいなことはある(笑)。でも、今回のコラボでもう1曲書く時間があれば本当にクズな人間の曲も書きたかったな。そういう話もちょっと出てたよね。
住野 出ました出ました。もう1曲書いていただけるなら、僕、自分の作品が映画化されたときにはいつも番外編を書くんですけど、この作品の番外編で何を書くかはもう決めてるので、そのときぜひお願いしたいです。誰かこれを読んでる大人たちぜひ映画化お願いします!(笑)
菅波 そのときはクズな曲を書き下ろしたいですね。住野さんもクズを書くのがうまいので。
住野 人を傷付けるセリフを書いてるときって楽しいですよね(笑)。
菅波 わかる! 俺も最近腕が鈍ってきてるからな。
共鳴する力を信じている
──“共鳴”がこの小説の1つのキーワードだと思うのですが、THE BACK HORNも2007年から「KYO-MEI」をテーマに活動していますよね。なぜこの言葉を掲げるようになったのでしょうか?
菅波 簡単に言うと、それまでは自分たちのことしか考えてなかったんですよ。自分たちが納得するものができたらそれでいいと思っていたんですけど、ライブとかを重ねていく中で自分たちだけで生きているわけではないという、当たり前のことを身にしみて感じるようになったのがその頃なんです。
──初めて「KYO-MEI」という言葉がブックレットに登場したのが6thアルバム「THE BACK HORN」のときでした。
菅波 まさにそのときのアルバムがセルフタイトルになったのは意味があるんだと思います。メンバーとの話し合いの中で、「『共感』じゃなくて『共鳴』のほうがしっくりくるね」となって「KYO-MEI」を選びました。俺らの場合、話し合いが論理的に進むことはあまりなくて、ひらめきや感情で決まっていくので、辞書とかで意味を調べることもなく「わかる! ギュンギュンくる感じだよね!」みたいなノリで決まったんですけど(笑)。ただ、不思議なもので普段「共鳴、共鳴」って思いながら曲を書いたりライブをやったりしているわけではないけど、自分の名前みたいに心のどこかでずっと感じているというか。「KYO-MEI」を掲げ始めたことで自分たちのバンドの進む道も変わったと思いますね。ライブも、よりバンドとお客さんとで作っていく意識になりましたし。
──今は新型コロナウイルスの影響でリアルなライブを行うことがなかなか難しい状況になりましたが、「KYO-MEI」に対する思いの変化や、改めて感じることはありますか?
菅波 いよいよ本領が試されるときが来たなと思っています。俺たちが掲げていたこの言葉が偽物だったらそれが明らかになるだろうし、本物だったら何も心配はいらないな、と。実はけっこう気が楽になったところもあって。THE BACK HORNは5月から8月にかけて過去のライブ映像をYouTubeにアップする企画をずっとやっていたんですけど、そのコメント欄で起きてる明らかな熱の高まり、共鳴を目の当たりにして、俺たちは音楽に思いを込めればいいんだと思えたんですよね。コロナになっていろいろ考えなきゃいけないことがあって頭がパンクしそうになったときもあったんですけど、これからも一生懸命音楽をやって、音楽でつながろうとすることだけに集中すれば大丈夫だと最近は思ってます。もちろん、ライブのやり方は試行錯誤していかなきゃいけないけど、とはいえ俺らは音楽の共鳴する力を信じてやっていけばいいんだなって。
住野 僕はファンの立場で言うと、ライブに行くことを趣味にしていたので、その趣味が完全に断たれたんですよね。今はライブがないのになんで仕事しなきゃいけないんだろうくらいの気持ちなんですけど(笑)、YouTubeで公開されたTHE BACK HORNのライブ映像を観たり、iPodに入っているいろんな曲を聴いたりして、ライブがなくても自分たちに音楽はちゃんとあるんだとコロナ禍で改めて思えました。この方たちが残してきた音楽が好きだなと改めて気付いた期間でしたね。
菅波 1冊の本が誰かの人生を支えることだってあるだろうしね。本も音楽も、誰かの人生に共鳴して、前に進むために背中を押してるだろうって、逆にコロナになってからより思ってるかもしれないです。もちろん今まで信じていなかったわけじゃないけど、より強くそれを信じるようになっていますね。