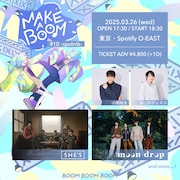SIRUP初のフルアルバム「FEEL GOOD」が5月29日にリリースされた。収録されるのはBIMやTENDREを客演に迎えた楽曲も含む全12曲で、ブラックミュージックやヒップホップを当たり前のように自身の音楽として濃密に昇華するSIRUPが送り出す、リアルかつコンテンポラリーなポップミュージックが詰まった1枚に仕上がった。音楽ナタリーのインタビューでは、彼の音楽的なルーツから今作の制作秘話までじっくり語ってもらった。
取材・文 / 三宅正一 撮影 / 永峰拓也
何事も地続きであることが重要
──KYOtaroからSIRUPに名義を変えて活動を開始したこの1年半は激動だったと思います。
そうですね。でも、蓋を開けてみたらいろいろあったとは思うんですけど、何かが変わった、みたいな実感はそこまでないんです。ただ、どんどんSIRUPとしての活動がいい感じになってきましたね。
──活動の様相はどんどん華々しくなっていると思うんですけど、しかし何よりここまで現場でプロップスを得てきた説得力が重要だと思うんですね。
そこはKYOtaro時代から意識してきたことでもあるんです。自分が経験してきたことで間違いないと思うことの1つが、現場でしっかりやる意義で。それは人間関係においてもそうですね。何事も地続きであることを大事にしています。全然会ったことがない人と曲を作ることはまずないし、どのライブに出演するかに関しても本当に共鳴する部分がないとそもそも深いコミュニケーションを取らない。そういう意味では、SIRUP名義になってから自分が関わっていきたいシーンのイベントに呼んでもらえるようになったんですよね。
──それは具体的にどういうシーンなんですか?
ちょっと話が広がっちゃうんですけど、大丈夫ですか?
──もちろん。
例えばクラブで日本人の曲を普通にかけられる環境が少なかったと思うんですよ。どちらかと言うと「あえてかける」という感じで。
──わかります。
仲間がやってる曲をかけて盛り上がるということはあったと思うんですけどね。去年は「こいつめっちゃいいねん」ってSIRUPの曲をクラブでかけてくれるDJがいっぱいいて、フロアで盛り上がったからイベントに呼ぼうというケースがいっぱいあったんです。そのオファーを受けて僕がライブをしに行くとフロアがめちゃめちゃ盛り上がってくれる。そういう流れが実現できたことが自分でも本当によかったと思っていて。それはずっと僕の目標でもあったから。去年は、特に地方はそういう匂いがする現場に積極的に出向きました。そうやって1つのシーンを感じることができたんですね。
──すごくいいことだと思います。
あと僕は大阪で今もSoulflexというクルーをやっていて、そのメンバーはSIRUPのバックバンドのメンバーでもあって。現場と地続きの活動を仲間と一緒にできていることが重要なんですよね。
ハートが反応するのは“歌しかできない”人
──「FEEL GOOD」はそういった現場感によって蓄積し成熟された、2019年の日本においてリアルなポップミュージックだと思うんですね。
ありがとうございます。
──この5年くらいで日本のポピュラーミュージックシーンにおいても、ブラックミュージックがマイノリティのものではなくなっていって。それはいろんなアーティストによる功績であり、成果であると思うんですけど。このアルバムもその流れの中にある大きな1枚になると思います。
ブラックミュージックをブラックミュージックとしてちょっと難しく捉えていた時代がかつてあったけど、ブラックミュージックを特別なものではなく純粋に楽しむ時代が日本にも来たと実感しています。僕、実はけっこう年齢がいっていて……(笑)。
──年齢って公表してないですよね?
わざわざ公表はしてないですけど、聞かれたら言っています(笑)。今、32歳です。僕は昔から普通にMr.Childrenを「めっちゃエモい」と思いながら聴いてる一方で、ディアンジェロも同じく「めっちゃエモい」と思って聴いていたんですよね。あとは日本のロックもけっこう聴いていました。9mm Parabellum BulletとかNICO Touches the Wallsの初期とか、GO!GO!7188もめっちゃ好きです。自分のハートがいいなと思ったらなんでも聴いてましたね。
──そのハートが反応するポイントってどこにあると思います?
うーん……結局、歌なんだと思います。その人しか持ってない歌力に惹かれます。極端に言うと、「この人は歌しかできないんやろうな」と感じられるボーカリストが好きです。例えばそれはエイミー・ワインハウスもそうだし。ジャンルとか本当にどうでもいいと思っていて。日本でもやっと、そういう“歌しかできない”人が音楽を作る世代であり、聴かれる時代になったのかなと思います。
次のページ »
チャンス・ザ・ラッパーがSIRUPに及ぼした影響