ネガティブがポジティブに転じた場所
──小林さんは前回を振り返っていかがですか?
小林 前回は……ああ、そうだ。初日から36日間、雨がずっと降り続いたって知ってた?
コムアイ 嘘でしょ?
小林 宮城県の新記録更新だったそうです。
コムアイ 小林さん、雨男ですね(笑)。そういえば毎日雨だった。
小林 誰の行いのせいかは置いておいて(笑)。都市と比べて、例えば駐車場を降りて一歩踏み出すと、整備されてないところもたくさん見える。そこに雨ばかり降ると、自然の顔というか、不便さが露呈してしまうわけです。だけど来てくれた人たちはクレームを言うこともなく、「自然ってそういうものでしょ?」と受け入れてくれました。しかも100m以上の断崖を階段で降りて、のり浜にある島袋道浩くんの展示作品「起こす」を観に行ったりしている。「サバイバルですよね?」と言われたりもしたんですけど(笑)。
──過酷だったんですね。
小林 でもそういう場所だからこそ、土壌みたいなものができた感じがありました。会期中に口コミが広まっていき、後半もお客さんの動員が落ちなかったし、むしろ伸びたんですね。僕としても、そういう都市ではできないことをやらなくちゃならないという思いがすごくあったので、それはうれしかったです。36日間連続の雨とか、そういう一般的にネガティブなことからポジティブな感情が生まれていった。そういったことを本当に実感できましたね。
──むき出しの自然が、オリジナリティにつながっていったのかもしれません。
小林 本当にそう。それに1回目にして名和晃平くんの「White Deer(Oshika)」みたいな、メジャー感がある作品も生まれました。あの作品、地元の人たちが誇りにしてくれているようで。前回、地元の漁師さんが「あの白い鹿、漁をしているときに海から見えるんだけど、それがすごくいいんだよね」って、それを見せるためにお客さんを船に乗せたいって言い出してくれたりして。1回目でああいうシンボリックな作品ができたのはラッキーだったと思う。今回のポスターはその白い鹿を夜に撮った写真なんですけど、地元のカメラマンの方が撮ってくれたもので。
コムアイ 星、すごい!
小林 CGじゃないんです。なんの細工もしてない。そのカメラマンの方がこの写真を名和くんの事務所に送ってきたそうで、名和くんが「小林さん、こんな写真を地元の人が送ってくれた」って。それで僕も「これ、使わせて」と頼んだんです。
コムアイ オフィシャルのカメラマンの作品じゃなかったんだ。すごいですね。ここ、浜が真っ白なんですよね、牡蠣の貝で。
Salyu そうそう。貝でできた浜なんだよね。
コムアイ だから夜も明るくて。貝殻の白いところがオーロラみたいに光ってて本当に好き。
音楽の力で伝える賢治のニュアンス
──ここからは「四次元の賢治」について伺います。「四次元の賢治」は中沢新一さんが脚本、小林さんが音楽を担当される“ポストロックオペラ”ということで、前回上演された第1幕にはSalyuさんは賢治の妹・としこ役で出演されています。今回は2幕と3幕が新たに加えられた完結編とのことで。
小林 はい。僕自身、作業になかなか入れなかったんですけど、4、5日前に中沢さんが脚本を上げてくださいました。それを踏まえて全体のイメージは今日の午前中に見えてきて……最後までの流れを想像したときにすごく難しいポイントがあって、これはスタッフと中沢さんとでミーティングが必要かもしれないと話しているうちに、だんだんとスタッフの言葉が鏡になって解けてきました。僕の中では少し不完全に思えた3幕も、素晴らしい流れでいけそうだな……となった段階です(笑)。
コムアイ ……ちょっとひと安心ですかね(笑)。見えてきたんですね。
小林 そうだね。だから今はまだ本があるくらい。でも僕がいないところで演者たちが集まって、感触をつかむためにキー合わせなどをやってくれているみたいです。僕からしたら「そんなに焦りなさんな」みたいな思いもあるんですけど(笑)。
コムアイ いや、焦りますよ(笑)。私なんかオペラとかやったことないから。でも私、本を見てオチにびっくりしました。これからどうなっていくんだろう。楽しみだな。内容についてはあまり言えないですけど。
Salyu そうそう。本が先に渡されるので、まずは「どんな音楽になるんだろう」と想像するんですけど、小林さんから音が上がってくると、活字のみで想像していた世界観が立体的になっていく。前回はその過程で感じた感動が、私の中で一番インパクトがありました。文字を読んで、想像が頭の中で果てしなく大きく膨らんでいる中で、そこにメロディとハーモニーが与えられて立体化していくという感動。
小林 僕もいろいろなことをやってきていますけど、この作品の面白さは独自のものです。中沢さんのフィルターが通っていることはもちろんですが、やはりその奥にいる宮沢賢治。日本人として、賢治を理解するというのはどういうことなのか。賢治について考えることは、例えば太宰治や三島由紀夫について考えることとは少し違う。賢治はマルチにいろいろなことをやっていて、亡くなる前は農業の営業のようなこともやっていたそうなんです。こもって作品を作っているわけではなかったんですよね。
コムアイ 作曲もしていたんでしたっけ? 「あかいめだまのさそり~」の歌。
Salyu そうそう、「星めぐりの歌」ね。作詞作曲が宮沢賢治の。
小林 今回は「星めぐりの歌」に新しく曲を付けて、子供たちに歌ってもらうシーンがあります。それはそうと、第1幕をやって思うのは、作品の中に“日本のポピュラー音楽にはなりそうにない言葉、のようなもの”がゴロゴロ転がっていること。ああいったものは、なかなか日常的に使うような言葉にはならないから、普通のセリフ劇でやると流れてしまうんじゃないかな、と。そこにメロディを乗せることでファンタジー的なフィルターが通って、受け手側のいろいろなところに入り込んでくるものになる。だから一般的なセリフのお芝居とは違うものですよね。
コムアイ 今回は全部歌ですよね。
小林 そう。今回は満島真之介くんがいるからセリフでもやれると思うんです。でも個人的には歌のみのほうがいいかなって。難しい言葉を使っているから、言葉をタイポグラフィとして見れるような演出や映像も必要ですけど。言葉の意味がわからなくても、漢字の持つニュアンスみたいなものを通して伝えるというか。
──メロディやビジュアルなどを効果的に活用して、ニュアンスを伝えていくと。
小林 そうです。土とか、芽吹いてくる何かとか、鉱物とか、宇宙とか、そしてそれらに命が反応していくような……さらに仏教なのか、もっと西洋的なものなのか、独特の宗教観が加わってくる。そんな賢治が持つ雰囲気って、あまり噛み砕きすぎないほうが伝わるんじゃないかなと思っていて。
コムアイ 賢治の世界観にはキリスト教文化の要素も感じますよね。そういえば、日本の能って、例えば何かを恨んで、悔しい思いをして死んでいった人の念のようなものをこの世に降ろすことで、それを体感するみたいな表現ですよね。一方で「四次元の賢治」は、そういった“人間じゃない何者か”をこの世に呼ぶという表現じゃなくて、“人間も、そうではないものも全員で旅をする”という描かれ方。そこにすごくファンタジーを感じます。しかも賢治の「銀河鉄道の夜」って死者の国を旅するような話ですよね。改めて原作を読んで、今回やることがようやくわかってきました。小林さんや中沢さんが宮沢賢治をテーマにしたい理由もわかる。震災のイメージの残る石巻で、死んでいった人とこれから生きていく人を全部包み込んで、三途の川みたいなものを1つの海の中でかき回す……そんな感じ。だから私たちが死者の国に旅に出て、お別れを言って帰ってくるような……もっと言えば、私も死んでいるか生きているかわからないし、死んだ人も生きているかもしれないしっていう。そういう旅。
──そんなイメージで解釈されているんですね。
コムアイ 先日中沢さんとお会いしたときに伺ったのが、今回の脚本はタイタニック号の事故の影響を受けていて、その描写が入ってるって。「銀河鉄道の夜」の原作では鉄道に濡れた子供たちが乗ってくるんですけど、その子供たちは海でほかの子供たちに小さい船を譲って、助からなかった子たちなんです。主人公のジョバンニが列車の中でその子たちと一緒になるけれど、ジョバンニは列車を降りて帰ってくる。列車は死の国というか神様の国というか、とにかく現実ではない世界に行く。そういう内容をああいう場所で表現して、お客さんに実感してもらうことは本当にやりがいがあるなと思ってます。
小林 それで言うと、いまだに頭の中には大川小学校のことが残っていますよね(編注:石巻市立大川小学校。東日本大震災の際、津波の被害で多くの児童を失った)。そのことをあえて大きな声で言うわけじゃないけれど、中沢さんにもその思いがあるんじゃないでしょうか。劇中に川ガニたちが出てくるのですが、それは大川小の子供たちでもあるんだ、みたいな。
コムアイ あのカニたちは……いや、これから観る人がいるからこの話はしないほうがいいかな。
小林 それは言っちゃダメかもしれない(笑)。まあとにかく、劇自体はいろいろな賢治の話がサンプリングされたようなもので。それがすごく面白いですね。
次のページ »
満島真之介が演じる賢治






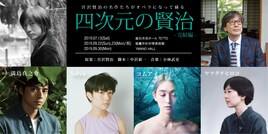


















![[週間アクセスランキング]来ないという選択はなかった](https://ogre.natalie.mu/media/news/music/2024/1118/9.jpg?impolicy=thumb_fill&cropPlace=Center&width=180&height=180)

