私、気分で動いているので
──新曲「give it back」についても伺いたいのですが、その前にちょっと振り返ると、去年の11月にリリースされたミニアルバム「LITMUS」が、前作の「PURE」からすごく変化した作品という印象で。「PURE」までのCö shu Nieは中村さんの頭の中にある世界を鮮やかに再現している印象があったんですが、「LITMUS」はもっと肉体的な感じがしたんですよね。
中村 「PURE」はロックメインで作った感じだけど、「LITMUS」は、持っていたいくつかの引き出しを、今の感覚で開けてみたという感じでした。ただ、曲の作り方自体は変わっていないんですよ。私がデモを出して、みんなに聴いてもらってアレンジを深めていくっていう。
──そうなんですね。歌詞は最後ですか?
中村 最後ですね。メロディが美しいことが私にとってはすごく重要なので、最後にメロディにハマるような言葉を持ってきます。
──「LITMUS」は、それまでに比べても歌が前に出ている印象があったんです。
松本 確かに「より歌を聴かせたい」というのは「LITMUS」のテーマとしてあったんですよね。そういうことを踏まえながらアレンジも考えていって。
中村 うん。「曲のよさ」がしっかりと伝わるように。音数の問題もあるけど、「LITMUS」は今まで以上にメロディを立たせるのがいいなと思ってアレンジしました。「PURE」はバンドというものをしっかりと前に出したかったからアレンジもバンドらしく、なおかつテクニカルなことも盛り込んでいったんですけど、「LITMUS」は引いて聴いたときに曲が強くなるように意識しました。
──「LITMUS」ではなぜそういう作り方を望んだのでしょうか?
中村 気分です。
──気分?
中村 はい。私、気分で動いているので。
──一番説得力がある答えのような気がします(笑)。ただ歌詞の内容的にも、外に向けて放たれる力が強くなっている気がしたんですよね。
中村 そうですね。内々だけではなくなってきました。音楽に引っ張られているのかもしれないし、私のモードだったのかもしれないけど。「LITMUS」を作った頃は外向きだった気がするんですよね。最近はまた内向きになってきている感じもするんですけど(笑)。
──そこもまあ、“気分”ですかね。
松本 中村の場合、曲によって変わる部分は大きいかもしれないですね。大まかに音から作りまくるというよりは、最初に表現しようとする題材が漠然とあって、それを掘り下げて物語にしていく。「その物語をどういうふうに持っていこうか?」と考えていく段階で、きっと中村のモードは変わっていくんだと思うんです。
中村 確かに。何もないところから音だけを作っていくことはないからね。さすがによく見てくれていますね。
知らぬ間に中村の手の上
──Cö shu Nieのすごいところは、歌を前に出したときに、それを合理的にサポートするためのベースとドラムというよりは、リズム隊もめちゃくちゃ“歌って”いるんですよね。
中村 そう、見事に表現しきっている。
──それによって、歌もメロディもリズムもすべてが自然に重なって、聴いていて気持ちのいい抑揚が生まれている。それが本当に見事だなと思うんです。
中村 そう思ってもらえるのは本当にうれしいです。“生”だからこそ表現できる抑揚みたいなものを生み出したくてバンドをやっているようなものですからね。
──松本さんと藤田さんは、中村さんのメロディや歌のリズムをすごく敏感に感じ取られているんだろうなと。
中村 私も相当細かくリズムを感じ取っているほうではあるんですけど、2人は私が感じているリズムよりもさらに細かいレベルで感じていると思います。それを汲んだうえで、1つひとつの音符を配置してくれる。だからすごく心地いいんです。
松本 そもそも中村の作る曲には面白いリズムが敷き詰められていて、それに対しての最善を感覚的に選んでいるんだと思います。そうすることで中村が敷いたレールに乗せられるというか、知らぬ間に中村の手の上で踊らされているというか(笑)。「ここだ!」と思ってレールを進んでいくと、「そうそう、正解」っていう表情で中村が待ち構えているんです(笑)。だから自分たちが「こうしてやろう!」と特別意識しなくても、中村の手にかかればこういう形になるのかなと思っちゃいます。
──なるほどなあ。
松本 「LITMUS」は特に音数を少なくしようというテーマがあったので、そういうところで、リズムの部分もうまく聴いてもらえたのかなと思いますね。生々しさがある作品になったと思います。
──藤田さんのドラミングもメロディの抑揚に対して見事な柔軟さを持っていると思います。「PURE」の取材ではブラジル音楽も素養にあると仰っていましたよね(参照:Cö shu Nie「PURE」インタビュー)。
藤田 そうですね。ブラジル音楽もいろいろあるんです。例えば最近だったら、サンバの進化形の「パゴーヂ」というジャンルが主流だったり。そういう音楽を自分が聴くときに何に惹かれているかといったら、結局は“歌”なんですよ。僕はポルトガル語がわかるわけではないんですけど、ブラジル音楽を聴くときにも、歌やメロディに引きこまれているんですよね。そのくらい僕は昔から歌が好きなんです。J-POPもたくさん聴いてきているし、ジャズやブラジル音楽、ラテン音楽も聴いてきましたけど、いろんなジャンルを聴いてきたうえで自分を形作っているのは、いわゆる歌モノなんです。結局はそこに返ってくる。
──なるほど。
藤田 自分でドラムを叩き始めたときはカナダのRushっていうロックバンドが好きだったんですけど、Rushのドラマーもあくまで歌モノの中で怪物的なドラムを叩くセンスを持った人だったんです。テクニックもすごいけど、なにより歌を持ち上げる力がすごい。思い返すと、僕はそういうドラマーに惹かれてきたなと思いますね。Cö shu Nieに入る前はスムースジャズのバンドにいたこともあって、そのときのフロントマンはサックスでしたけど、それでも感覚的には歌モノという感じで向き合っていたし。インスト音楽でも歌心のあるドラマーに惹かれてきた部分はあるんですよね。
──聞けば聞くほどCö shu Nieは本当に奇跡的なトライアングルですよね。
中村 うん。バンドなんです、私たちは。バンドであることがすごく好きなんですよね。
次のページ »
失うものなんて何もない










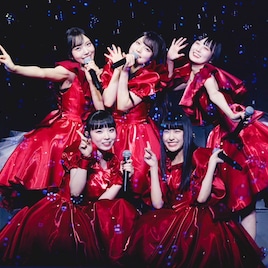







![[Alexandros]インタビュー|信頼と衝動で作り上げた最高傑作](https://ogre.natalie.mu/media/pp/alexandros07/alexandros07_thumb_2.jpg?imwidth=240&imdensity=1)










![[週間アクセスランキング]ノノガ出身者の活躍](https://ogre.natalie.mu/media/news/music/2025/0421/sub8.jpg?impolicy=thumb_fit&width=180&height=180)
