1人だけポップスじゃないやつがいる!
──そうやってさまざまな音や感情を複雑に、重層的に鳴らしながら、展開もひと筋縄ではいかない、キメラ的な、カオティックな楽曲が生み出されていますよね。こうした複雑な音像を自分たちが必要とするのは、なぜだと思いますか?
中村 全部にとは言いませんけど、あらゆる音に意味があるんです。例えば「ここに音符が入ってくることで、切迫感や焦燥感を出したりできる」みたいな感じで。拍を1拍抜いて11拍にすることにも、音符を普通に8分で詰めないことにも、そのタイミングでそういう表現をすることで、歌詞とのリンクや世界観をより深めていく意味があります。あと、大きいのはベーシストのプレイスタイルですね。彼がもともと持っているものを生かして、自分たちの色にするにはどういう音楽がいいのかということを考えながら、Cö shu Nieの特性を決めていった部分もあります。バンドとしての“個”の部分と、メンバーの“個”としての部分のギリギリのラインを攻めたいんですよね。
──中村さんにとって松本さんのベースにはどのような魅力があるのでしょうか?
中村 私がポップスバンドで弾いている彼を見つけてCö shu Nieに誘ったんですけど、当時から彼は異質だったんですよ。「1人だけポップスじゃないやつがいる!」みたいな(笑)。
松本 (苦笑)……そもそも自分の中にギターやベースという概念がなかったんですよね。曲を聴くと音が全部つながって聴こえていたんです。まさかベースがルートを弾いているなんて思っていなくて、ボーカルのメロディと同じように、永遠に動いている音っていう認識だった。いろんな楽器が交わることで、1つの音楽を作っているという認識が自分の中になかったんです。なので、ベースを弾くときも勝手に音を重ねていってしまったり、動きたがっている音を追ってしまうんです。特にCö shu Nieの初期の頃は同じ音を弾くということが理解できなくて、頭のネジが外れていたなって自分でも思うんですけど(笑)。
中村 ふふふ(笑)。
松本 当時は協調性よりも爆発という感じで弾いていたので、あまりよろしくなかったなと思うんですけど(笑)。好きなベーシストも激しめな動きのある人が多くて。最初に好きになったのはRancidなんですけど、Rancidのベースってすごく動くしメロディックなんですよね。それから“ザ・動くベース”という感じですけど、L'Arc-en-Cielを聴いて、「こんなに美しいフレージングがあるんだ!」と思って。そういう音楽を聴きながら段々と「どうやったら曲の中でベースを美しく見せることができるんだろう?」ということを突き詰めて考えるようになっていったんです。最近ようやく“支えつつ動く”という自分のプレイスタイルができてきたような感がしています。
──藤田さんは去年正式メンバーとして加入されました。中村さんと松本さんが10年近く蓄積してきたものに入っていけるということは、プレイヤーとして相当相性がよかったということですよね。
中村 めちゃくちゃ相性いいよね? 特にこのリズム隊の相性は最高だと思う。
松本 そうだね。音で会話できるというか、演奏していたら同じ気分になって「ここはこうだよね?」ということを、目を合わせずとも同じタイミングで語り合える。そういうことを体感で共有するのって、誰とでもできることではないんですよね。うまいからできるっていうことでもないし。なので、相性はめちゃくちゃいいと思うし、僕もそう思われていると思います(笑)。
藤田 思ってます(笑)。
中村 (藤田が加入するまで)紆余曲折あったんですけど、ずっと口説いていたんですよ(笑)。お互いタイミングが合わなかったんですけど、やっと落ち着いたところで、Cö shu Nieに入ってくれて。
こんなに自由でいいんだ
──藤田さんのドラムの魅力はどんなところにありますか?
中村 “どこまでも連れていってくれる”というところですね。機械のように正確なドラムと言われることもあるんですけど、それにプラスして、音に感情を乗せる表現力の幅が広いし、それに細かいんですよ。ある意味、気分屋みたいなところがあって。そこがグッとくる魅力になっているんですよね。それに「面白いフレーズないかな?」って相談すれば、いっぱいアイデアが出てくるし、宝箱のようなドラマーだと思います。出会った頃から彼は表現者然とした、内なるパッションを持っているドラマーだったんです。でも当時はそれを封じ込めている感じだったよね?
藤田 そうですね。
中村 だから「一緒にバンドやろうよ」とずっと誘っていたんです。「絶対、楽しいよ」って。
藤田 僕はもともとすごくシンプルにドラムを叩くのが好きだったんですけど、Cö shu Nieに入ってからはシンプルなイメージを保ちながら、複雑に手数の多いドラムを叩くということを無意識的にできるようになった感じがしていて。それまではずっと形式のあることをドラムでやり続けていたんですけど、今はデモ音源をもらうとドラマー目線では考え付かないようなフレーズがたくさん出てくるんですよね。でもそれがすごく曲にマッチしていてカッコいいんだなって、勉強になることがすごく多い。逆に僕はブラジル音楽なんかを通ってきているので、そこからのエッセンスをCö shu Nieの曲に入れてみたら意外とハマったりして。「こんなに自由でいいんだ!」と思いながら楽しんでいますね。
──お話を聞いていると、松本さんと藤田さんはそれぞれの人間性がそれぞれの楽器と分かち難く結び付いていることがわかるし、だからこそ中村さんはお二人を必要としたんだなと理解できます。
中村 魂の入ったものが好きなんです。オートクチュールのような音が好き。電子音楽でもすごくこだわって作られたものだと、それを作った人の色がすごく色濃く出るじゃないですか。そういうものを聴くと、すごくテンションが上がるんです。この2人もそうですけど、「どうやっているんだろう?」と思ってしまうような、自分がわからない仕組みのことをいとも簡単にやってのける人たちに対してのリスペクトは常に持っていますね。
次のページ »
ずっと、愛そうとしている







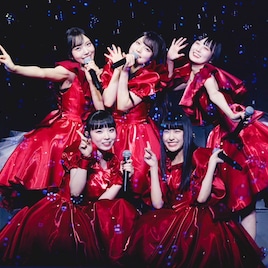










![[Alexandros]インタビュー|信頼と衝動で作り上げた最高傑作](https://ogre.natalie.mu/media/pp/alexandros07/alexandros07_thumb_2.jpg?imwidth=240&imdensity=1)










![[週間アクセスランキング]ノノガ出身者の活躍](https://ogre.natalie.mu/media/news/music/2025/0421/sub8.jpg?impolicy=thumb_fit&width=180&height=180)
