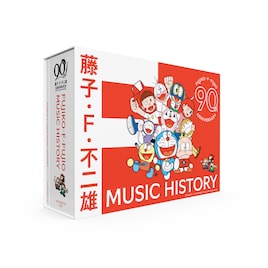2018年に発表した「世界の中心~We are the world~」では1990年代後半に一世を風靡したユーロビートを基調にしたサウンド、パラパラをはじめとするギャル文化をふんだんに盛り込んだミュージックビデオで話題を集めた青山テルマ。近年はポジティブなキャラクターをバラエティ番組で生かしつつ、映画「シュガー・ラッシュ:オンライン」の日本版エンドソング「In This Place~2人のキズナ」や與真司郎(AAA)とのコラボ曲「好き好き好き」の発表、UVERworldの楽曲「SOUL」への客演など、幅広い分野での活躍を見せている。
そして青山は自身の誕生日である10月27日、9枚目のオリジナルアルバム「Scorpion Moon」をリリースした。本作は彼女の音楽の代名詞ともいえるバラードをはじめ、ヒップホップサウンドもふんだんに盛り込んだ、バラエティ豊かな作品となっている。音楽ナタリーでは本作の発売に合わせ、青山にインタビューを実施。「Scorpion Moon」の制作背景をはじめ、大きな転換期になったというアルバム「Lonely Angel」前後のエピソード、ボーカルトレーナーとして出演したオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」での体験談などを語ってもらった。
取材・文 / 高橋拓也撮影 / 笹原清明
「みんなで作る」ことが私のライブのモットー
──2018年に発表されたアルバム「HIGHSCHOOL GAL」、特にミュージックビデオも公開された楽曲「世界の中心~We are the world~」のインパクトはすごかったです。これまでテルマさんはバラード調のラブソングを多く手がけてきましたが、「世界の中心~We are the world~」はユーロビートを基調とした楽曲で、かなり作風が異なりましたよね。
実は音楽性が大きく変わったのは「Lonely Angel」(2014年発表のアルバム)からなんです。このアルバムで初めてラップに挑戦したり、これまで使ってこなかったビートを採用していて。
──「Lonely Angel」は全体的に渋いムードのアルバムで、ヒップホップ系のサウンドを大々的に用いたり、英詞のみの楽曲が初めて制作されたのもこの頃でした。
このアルバムを出す前はバラードものが中心で、あまり自分のことをオープンにする機会もなくて。その反動なのか「面白いことがしたい」という意識が強くなって、「Lonely Angel」は自分の思うがままに作ったんです。一方で「HIGHSCHOOL GAL」はライブを盛り上げることをコンセプトにしたアルバムで、アゲアゲな曲や「ONIGIRI」のようにみんなで歌えるような曲をメインにしました。私はライブパフォーマンスがずっと強みだと思っているし、ファンと一緒に話したり盛り上がれることが好きで。「HIGHSCHOOL GAL」は「ウチらのライブはこんな感じ」というものを表現した作品でもありますね。
──作風が変わってから、ライブの雰囲気も変化したのではないでしょうか?
そうですね。もちろん今でもバラードは歌うけど、踊ったり歌ったりすることで楽しめる曲もバランスよく盛り込めるようになりました。初めて観る方にも「オモロイな」と感じてもらえるライブができるようになったんじゃないかな? それから「みんなで作る」が私のライブのモットーなので、誰でも楽しめるものにしたくて。音楽って「カッコいい」「共感できる」とかいろんな側面があるけど、今は「面白い」と感じてもらえることを大事にしたいし、それが私の強みなのかなって思います。
──SNSでの生配信やテレビ番組でも、テルマさんはとてもフレンドリーですよね。そのムードはライブでも生かされているんですね。
むしろ私のキャラクターが一番発揮されるのはライブかもしれないです。テレビやラジオではいろいろな側面が見えると思うけど、ライブではそれが凝縮されるので。自分もお客さんもオープンになれますからね。
──テルマさんはInstagramでよくファンからのメッセージに返信していますが、その数の多さに驚きます。ほかのアーティストではなかなか拾わないような内容、例えば「学校でいじめられそう」という悩み相談もあれば、「テルマってどうやってモチベあげてる?」のような妙にフランクな質問にも丁寧に答えていますし。
みんなの話を聞くのは好きだし、とても楽しいんですよ。同じエンタメ業界で活躍する人たちのお話も面白いんですけど、私とは違う世界で生きている人たちの悩みや考え、視点はとても興味深くて。だからほかの人がスルーするような悩みや質問にも答えちゃうのかも。
「そばにいるね」大ヒットがもたらした苦悩
──2019年に発表した著書「人生ブルドーザー」はご機嫌なタイトルとは裏腹に、クォーターであることによって幼少期に受けた差別、テルマさんの名を一躍広めた「そばにいるね」リリース後の苦悩も赤裸々に書かれていて衝撃的でした。特に声が出なくなってしまったり、鬱のような症状に悩まされていた時期のお話は壮絶で……。
あまり他人に心配されたくないので、当時のことはあえて話さないようにしていたんです。でも、私の明るい部分だけ紹介されるのもどうかと思って。
──当時の状況は相当ハードだったこともあり、振り返るのはかなりつらかったのではないでしょうか?
やっぱり大変だったし、すごくしんどかった。だけどその体験を発表することで、少しでも誰かの力になれたり、生きるヒントになったらいいなって。それに今では「体験できてすごくよかった」と思えるんです。いろんな出来事を経て今の自分がいるので。今後のことも考えて、どうやって苦難を乗り越えてきたか、この機会に書き残しておきたかったんです。
──これまでの作品を振り返ってみると、2ndアルバム「Emotions」の収録曲「KEEP ON」や3rdアルバム「WILL」の収録曲「23」では自身の生き方に対する悩みが歌われていて、「人生ブルドーザー」でも触れられていた当時の心境を垣間見ることができました。そういう意味では、テルマさんのアルバムはどれもドキュメンタリー的な要素がありますね。
自分の書く歌詞は実話に基づいているものが多いですからね。もちろん架空の物語を想像することも好きですけど、体験していない出来事を歌詞に落とし込むのはあまり得意じゃなくて。一番素直になれるのは歌詞の中かもしれない。
初心を忘れないことより、自分を更新し続けることが大切
──一連の苦悩はのちにアルバム「Lonely Angel」の作風へと結実していくのですが、テルマさんが編集長を務めたフリーペーパー「DREAM PAPER」が2012年から刊行されたことも、大きな節目になったかと思います。
当時は日本国内の音楽番組が減っていたし、雑誌もどんどん休刊していて。その状況を見ていて、なんとなく「自分の居場所は自分で作る時代になるんだろうな」と考えていたんです。そうこうしているうちにSNSを使うのが当たり前になって、ミュージシャンもスタッフの力を借りるだけでなく、本人が発信することがすごく重要になりましたし。
──この数年で相当状況は変わりましたね。
ええ。昔だったらCMを放送したり、街中に宣伝トラックを走らせてもらうことで認知度を高めたけど、今ではアーティスト自身が発信するSNSのほうが、影響力も大きいです。そんなSNSが普及する前に、本のように紙で残る媒体で自分の居場所を作りたいなって思ったんです。それが「DREAM PAPER」を作るきっかけになりました。
──「DREAM PAPER」はテルマさんご自身がデザインを手がけ、スナップショットやコラージュを駆使した読み応えのある作品でした。
自分でデザインできることも大きいですが、やっぱり雑誌だと、出たいタイミングで掲載させてもらうのは難しくて。あとは自分だったらどうやって紙媒体を駆使するのか、それを試してみたかったのも「DREAM PAPER」を作り始めた理由の1つですね。
──「Lonely Angel」の初回限定盤にはCDに加え、「DREAM PAPER」の特別編とも言える「MY DREAM PAPER」が付属していました。この形態は今見ても珍しいですね。
わがまま言って作らせてもらいました(笑)。どれだけ売れるかはもちろん大事だけど、「Lonely Angel」は私が残したいものを作ることを重視したんです。「みんなが求めているから」みたいなマインドを一度捨てて、「自分はこれがいい」という気持ちを大切にしました。結果自分が求める表現をとにかく追求できたし、次の活動につなげられたと思います。
──逆に「Lonely Angel」発表以前は、制限されていたことが多かった?
正直そうでしたね。曲調だけでなく発言や着る服、ネイルの色や髪色も制限されていました。スタッフが私のことを守ってくれたからこその制限だったけど、本来の自分と理想の自分、繕っている自分でそれぞれギャップが生まれてしまって。どれかが間違っているわけではないので、それらを1つにまとめたい気持ちは徐々に強くなりました。でも、それって誰かに頼めることではなくて。理想像があるなら自分自身で目指すべきだし、誰かに「こうしてほしい」と求めるのは違うので。一旦すべての責任を背負って「ここを変えるべきだな」と把握し、次に生かしていく。そのマインドは今でも大事にしています。
──「Lonely Angel」はロサンゼルスに赴き、スタッフやスタジオを自ら準備して制作したそうで。
全部自分でオファーすることで、スタジオ代やトラック制作にどれだけお金がかかるかわかりましたね。周りが環境を与えてくれた頃は恵まれていたんだなって痛感しましたし、「今ある環境でどうありたいのか」「環境がなかったらどう作っていくか」を考えるようになりました。
──ご自身の意識を大きく変えるきっかけになったわけですね。
はい。「初心を忘れるな」という言葉があるじゃないですか。正直初心は忘れてしまうものなので、私はあんまり好きじゃなくて。デビュー当時のことをすべて思い出すことはできないし、それよりも自分がどういう人間でありたいのか、常に意識することが重要だと思います。
母性本能ってこういうことかも?「プデュ」出演の舞台裏
──お話を聞いていくと、テルマさんは非常にストイックですよね。ご自身に対して厳しい一方、ファンや後輩に対してはとても優しく、真摯に接していて。例えばボーカルトレーナーとして今春出演された「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」(以下「プデュ」)でも、練習生1人ひとりへのアドバイスをびっしりメモ書きしていたり。
そんなこともありましたね(笑)。「プデュ」はオファーがあったとき、自分にできるか不安だったんです。今までボーカルトレーナーを務めたことはなかったし、後輩にもあんまり口を出さないタイプなので。
──後輩へのアドバイスを避けていたのはなぜ?
私が「そっち行ったらコケるよ!」と教えたとしても、1回自分で失敗してみないとわかんないことってたくさんあるから。だから後輩とは適度な距離感を保っています。「プデュ」も同じ距離感で臨もうとしたんですけど、初回にずらっと並んだ60人の練習生の姿を見たときに、「全員『プデュ』に懸けて来たんだ」というのが一瞬で伝わってきて。こっちも緊張しちゃって「最後までできるかな……」と頭をよぎってしまうほどでした。最初のトレーニングも、まず何を教えたらいいのかわからなくて手探りでしたし。回を重ねることで伝えるべきポイントがつかめてきて、1人ひとりがどんな心境なのかわかるようになりましたね。
──テルマさんご自身もトレーナーとしての能力を発揮していった。
でもそうなったら、今度は寝ても覚めても「プデュ」のことしか考えられなくなっちゃって。アルバムの制作が全然進まなくなっちゃったんです(笑)。
──そんなにのめり込んだんですか(笑)。
どの現場に行っても、ずーっとスタッフと「あいつ今日声出るかな?」とか話してましたよ。母性本能ってこういうことなのかもしれない。もう大勢の子供を一気に生んだ感じ(笑)。でもトレーナーと生徒という距離感は絶対に崩さないようにしました。みんながちゃんと失敗できる環境を作る、と言えばいいのかな。あとは指導するとき、自分ができていなかったら説得力がないので、課題曲は必ず歌い込んでいって。ちゃんとお手本になれるよう気を付けましたね。
──「プデュ」への出演を受け、今後トレーナーのオファーも増えそうですよね。
いやあ、どうだろうな……。ホンットにメンタルをやられちゃうので(笑)。いつだったか「このオーディションだけがすべてじゃない、次もあるよ」と言ってしまったことがあったんです。でもチャンスがあるとしても、あの子たちにとっては「プデュ」がすべてだから。家に帰ったあと「言ってよかったのかな」と反省しました。あとはレッスンが終わったあと、夜遅くまでメンバーの相談を受けたこともありましたし、泣いてる子がいると「おいおい、どうした?」って声をかけて話を聞いたり。テレビで観ているよりも100倍大変だから、次回の開催が決まったら、トレーナーさんにアドバイスしたい(笑)。
──トレーナーとしての活動は、ご自身の音楽活動に影響を与えましたか?
レッスンする曲を全部覚えたり、音楽にストイックに向き合う機会になったので「この体験、超大事だな」と感じました。オーディションを受けた彼らにとっても、あそこまで競い合う経験ってそうそうないと思うんです。朝から夜までレッスンするだけでも大変なのに、家族には会えないしスマホを持つこともできない。1つのことに向き合い続ける日々は、とても意義のある挑戦になったんじゃないかな。
次のページ »
再び「自分が聴きたい音楽」を集めたアルバムを作りたい