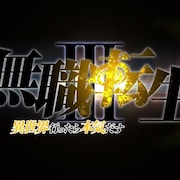僕は “眠くない”じゃなくて、“眠い”なんです(笑)
──「マロニエ」の最新3巻と同時に、岩本さんの画業を振り返る書籍「岩本ナオ 古今東西しごと集」も発売されました。
素敵なイラストを大きな版で、しかもカラーで見られるのはすごくうれしいです。岩本先生のこの淡い色遣い、すごく綺麗ですよね。あと、この単行本に収録されている短編「紅い果実と花飾り」が面白かったです。ついにヒロインが一言もしゃべらないという(笑)。「Yesterday, Yes a day」の多喜二もほぼしゃべらないぐらいな感じではありましたけど、本当に一言もっていうのはすごいなと(笑)。
──このお話の設定もすごいですよね。やむを得ず兄や姉より弟・妹が先に結婚する場合は、兄や姉は木と結婚しなければならないという……。
そうそうそう。だから本当に着想のスタート地点がすごいんですよね。でも、精霊とか風習とか、空気に漂う「何か」の存在を感じたりするような感覚はすんなり身体に馴染むというか。あとは特典ペーパーのような、集めないと読めないものがいっぱい載っているのもうれしいですね。貴重なラフ絵も掲載されている。
──貴重というと、「天狗の子」の秋姫と瞬ちゃんの10年後のイラストも載っているんですよね。単行本の最終12巻の限定版に掲載されていたものですが、これは買い逃した人も多かったのではないかと。
うわあ! マジか。いやあ、これはエモいなあ……。「天狗の子」はアニメ化したら絶対もっと人気が出ると思うんですよね。純粋にいちファンとしても、アニメーションになったものはすごく観てみたいという気持ちがあります。それをきっかけにでも、もっともっと多くの方に作品を読んでほしい。
──あと、「しごと集」はカバーをめくると、これまでの作品のラブシーンがピックアップされているんです。もどかしいながらもキャラクター同士が触れ合うシーンにキュンとする読者は多いと思うのですが、斉藤さんはどういうふうに見られていますか?
いやあ、それはもうキュンですよ。この、「天狗の子」の「好きだぞ、秋姫」のシーンも。……やっぱり界人くんでしか再生できない、なんだか複雑な気持ちです(笑)。
──(笑)。ちなみに、斉藤さんはどんなときにマンガを読まれるんですか?
移動中か、一番多いのは寝る前です。でも僕は “眠くない”じゃなく、“眠い”なんですよ(笑)。眠いんですけど、続きが気になる気持ちのほうが勝って、ついつい読みふけってしまいます。
──新しいマンガを買うときはどのようなきっかけで手に取るのでしょう。
ジャケ買いすることも多くて、それは趣味みたいな感じですね。表紙と内容が大きく乖離してるってことって、それほど多くはないじゃないですか。なので特にマンガはすぐに買ってしまいますね。最近はもう完結している、かつて読んでいたマンガをもう一度読むのにハマっていて。Kindleで買うことが一番多いんですが、いつでもどこでも買えるし読めるので、便利だなと思っています。
──巻数が多い作品は、改めて紙で集めるのもなかなか大変ですもんね。
そうなんですよ。移動中に読みたいときも、持ち運べる数には限界があるので。だけど、僕はやっぱり本という媒体そのものが好きでもあるんです。紙の質感やページをめくる音、そういったものが好きなので、これは紙で手元に置いておきたいと感じるものは単行本を買っています。それこそ、この「古今東西しごと集」も紙の状態で持っておきたいものですよね。電子と紙、どちらも良さがありますし、マンガを読む間口も広がっていると思います。僕自身、いろんな形でもっとマンガを楽しく読んでいきたいです。
少しだけ心を軽くしてくれるような、素敵な作品たちばかり
──改めて、斉藤さんがマンガと、そして岩本さんの作品がお好きなことが伝わりました。
とにかく本が好きなのでいろんな作品を読むんですが、ごくたまに論理などを超えて、感じるとしか言いようがない、波長が合うと思える作品に出会うことがあって。岩本先生の作品は自分にとって、どれもそうなんです。
──言葉では表せないような感情を、読んでいるときにも味わえる。
例えば僕は自分で曲や文章を書いたりもするんですが、マンガや音楽、あるいは文学も、まだ名前の与えられていないものに名前を付けるのではなく、そのもの自体をいろんな形で表現するというのが、創作物のひとつのやり方なのかなという気がしていて。翻訳みたいなものですかね。まだ名付けられていないその感情を、マンガで翻訳するとこう、曲で翻訳するとこうなる、というような。世界を別の形で翻訳するというのも、ひとつの創作物のあり方かなと思います。
──そういったご自身の創作活動の中で、何か影響を受ける部分はありますか?
直接的に創作活動に影響を受けるというよりは、無理なく気分を上向きにしてくれる存在だと感じています。例えば疲れているときに作品を読んで、感動して涙を流すと、少しエネルギーが充填される感覚があって。結果的にそれが創作活動のみならず、「明日は少し早く起きてみよう」というような、次の前向きな行動につながっていると思います。
──では最後に、まだ岩本さんの作品に触れたことがない人に向けて、改めて魅力をプレゼンするとしたら、どういったところをオススメしたいですか?
岩本先生の作品には、自分に真剣に、人に誠実に生きている人たちがたくさん出てきて。読んだときに、“人を思うこと”について考えさせられるんですよね。最終的には、言ってしまえば“愛”ということなんだと思うのですが、その愛というのも恋愛だけではなく、親愛の気持ちであったり、自然や植物を愛でる気持ちであったり、いろんな愛の形がある。その“愛”のおすそ分けをしてくれる作品だと思っています。マンガを読み終えて現実世界に帰って来たときに、いつも気持ちが少し前向きになっている。そんな、少しだけ心を軽くしてくれるような素敵な作品たちばかりだと思います。そういうところが、先生の作品の魅力なのではないでしょうか。
斉藤壮馬から岩本ナオへ質問

岩本先生がどういうところから物語やキャラクターを思いついて構築されているのか、すごく気になります。あとは、好きなモチーフやシチュエーションはあるのでしょうか。例えば僕で言うと団地や屋上、巨大なものや宇宙が好きで。そういった個人個人が郷愁や切なさを感じるものってあると思うんですが、岩本先生にもおありだったらお伺いしてみたいです。
ご質問ありがとうございます。
物語やキャラクターの構築ですが、私の仕事は少女漫画なので恋愛要素が入る場合、何かモチーフがあって話が少しでも固まってきたら、主人公の女の子がくっつく相手は幼なじみかそうでないかが問題になってきます。(←ここが一番重要でモチベーションを左右します。)
眠くないは一番はじめだったので、お客様に絶対面白いと感じてほしかったので、相手役を幼なじみにしました。お話については、ここ数年、絵本や民話から着想を得ることが多いなと思ってます。
好きなモチーフ、シチュエーション、郷愁を感じるものですが、あまり意識したことはなかったのですが、アネモネやヒナゲシが好きで前から扉絵などではちょいちょい描いていたのですが、最近ヨーロッパのほうの一面のヒナゲシ畑が一番描いてみたいモチーフなことに気がつきました。モネのヒナゲシみたいなやつです。
実家がとんでもなく田舎で、家の裏が見えなくなるとこまで自分ちの畑で、よくたくさんのケシの花やコスモスが咲いていたりしていたからかなと思います。